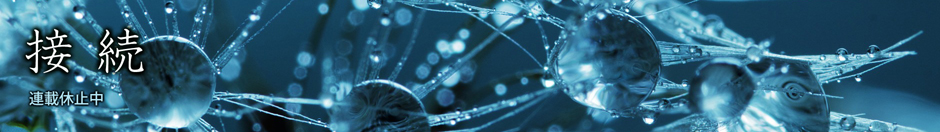
act.32
次の瞬間、櫻井はその場にいた人間全てから笑いものにされた。
櫻井の目の前に立つ掃除夫はもちろんのこと、ボディガード達もさも面白いジョークを聞いたかのように声を出して笑った。
ここで笑っていないのは、櫻井と蓮花だけだった。いや、櫻井に言わせれば『偽物の蓮花』だが。
「お前、どんな目をしてやがるんだ。そんなひげ面の下働きが華見歌壇のトップスターだって?!」
ボディガードの一人は目に涙を滲ませながら、櫻井を指さして笑った。
「今までいろんな言い草を言いながらミス・蓮花に近づいてくる男はごまんといたが、他の人間・・・ましてや男を捕まえてミス・蓮花だなんて言った愚か者は、お前が初めてだよ」
更にその場がどっと盛り上がる。
掃除夫は、ひょいと肩を竦ませてその場を去ろうとする。
ボディガード達もそれを見てさっさと蓮花を車に乗せ、走り去って行った。
結局、その場で櫻井がポツリとひとり残される。
櫻井はその場に立ちすくんでいたが、やがて溜息をついて大通りに向かって歩き出した。
── やはり、自分の勘は間違っていたのだろうか・・・。
刑事時代からこの勘に助けられたことは幾多あった。櫻井自身、その勘を裏付けにして確信を持ったことはひとつやふたつではない。しかし今回ばかりは、あまりに突拍子のない思いつきだったのか。
櫻井は、今後どうすればいいのかと考えあぐねた。
あんなことを言い出した手前、蓮花に近づくのは前より容易でなくなった。
自分の手際の悪さに、自己嫌悪に陥る。
意外なほど落ち込んでいる自分に驚いて、櫻井は帰り道の深夜営業の食堂で一杯引っかけて、ホテルに帰った。
深夜のホテルの廊下は異様なほど静まりかえっている。
櫻井は宿泊している部屋にカードキーを差し込んで入った。
部屋の中は真っ暗闇。すぐさま櫻井は、部屋の電気を入れた。
その瞬間、はっとして櫻井は身構えた。
窓際のソファーにいるはずのない人影を見つけたからだった。
「 ── な・・・?」
櫻井は驚きの余り息を呑んだが、同時に自分の勘がやはりあっていたことを再確認したのだった。
目の前に座っていたのは、他でもないあの掃除夫だった。
彼は人を食ったかのような飄々とした表情を浮かべ、戸口に立ちすくむ櫻井を見つめてきた。
「お前さん、何者だい」
男が放った第一声は、それだった。
完全に男の声だった。
そしてオマケに、完全に綺麗な発音の日本語だった。
櫻井は、眉間にシワを寄せる。
「あなたこそ・・・、何者なんです?」
櫻井の問いかけに、男はふっと笑った。
「蓮花だろうが。お前さんが言ったんだ」
男はそう言うと、櫻井の目の前で顎に手をやり、あれよあれよという間に顎一面に生えていた無精髭を『剥いだ』。
精巧な付け髭の向こうから現れたのは、確かにあの美しい面差しだった。
化粧していない分ステージ上の華やかさはないにしても、確かにあの顔だ。
でもまさか、こうして改めて男として目の前に現れたとなると、それなりに衝撃がある。
これで本当に男なのなら、かなりの女顔だ。
整形でもしているのか。
櫻井は、向かいのソファーに座った。
「なぜあなたはそんなふうにしているんです? なぜ性別を偽る必要が? それに、どうやってこの部屋に入ったんです?」
男は、薄汚い作業着から細巻きのタバコを取り出すと、ゆっくりした動きでタバコに火を点けた。その仕草は恰好が粗末でも随分と優雅だ。やはり彼の資質としてそういう方が本当の彼なのだろう。それが分かると、作業着の汚れた恰好が変に浮いて見える。
男は、ひとつ煙を吐いて、窓の外に広がるネオンに彩られた景色を眺め、ひとつ咳払いした。
「待ちな。質問はひとつずつ。今度はこっちが質問する番だ」
櫻井は頷いて姿勢を正した。
確かに男の言い草ももっともだ。
互いに謎が多すぎる。
「どうぞ」
櫻井が畏まってそう言うと、男は少し表情を緩めた。
「全く、お前さんは随分と変わってる。本当に一体何者なんだい?」
櫻井は自分の身元をはっきり言うべきかしばし考え込んだ。
一応、痩せても枯れても公安職員だ。日本国内はおろか国外でも秘密裏に行動するのが常の商売である。
しかし男はそんな櫻井の心境を鋭く察知したらしい。
「俺から情報を引き出そうっていうんなら、そっちも正直に吐いてもらわないと。闇の世界でも、取引に『信頼』は大事だ」
射抜くような目で見つめられ、櫻井は腹を決めた。
「自分は、日本の警視庁公安部外事課に所属する特務員です」
男はクイッと眉を引き上げた。口笛を吹く。
「特務員ねぇ。── 随分と懐かしい響きだ」
男はそう言ってクックッと笑う。
櫻井は目を見張った。
「あなたは以前も会ったことがあるんですか? 日本の公安工作職員に」
「会ったどころか。昔はひとつのチームとして働いたこともあったな」
それを聞いて、櫻井は大きく息を吸い込んだ。
櫻井の頭の中で、今まで得た様々な情報ソースが入り乱れて、やがてそれぞれのピースがひとつの盤面に填り込んだ。
「蓮花って・・・蓮花がコード・ロータスへの橋渡しではなく、蓮花自身がコード・ロータスだったんですね」
男の表情が変わった。
そしてマジマジと顔を見られた。
「お前さん、超能力者か何かか? 随分と察しがいいものだ」
「じゃ、あなたがコード・ロータスなんですね。米国CIAの諜報員で極東アジアの全域の諜報活動の統括者」
「一見すると不器用なヤツだと思っていたが。ただの不器用者という訳ではなさそうだ。やはり日本警察の精鋭の一員である理由はちゃんとあるということか。以前俺と仕事をしていた特務員の野郎も、最初は俺の正体を見抜くことができなかったからな」
「公安幹部は、蓮花がコード・ロータスへの橋渡しだと自分に告げました。彼らは蓮花とコード・ロータスが同一人物であることを知らないですか?」
「むろん彼らは知っている。昔共同捜査を行った仲だ」
「じゃなぜ彼らは最初から・・・」
「なぜなら、それは俺がそういう条件を出したからさ」
男はそう言ってまたタバコを吸うと、繊細な指の動きで灰皿に灰を落とした。
「条件?」
「日本政府からCIAに捜査協力の要請は来ていた。公安特務員の一人が行方不明になったので、捜査の協力をして欲しいと。むろんその要請は、すぐさま俺のところに回される。だが、俺だってどこのどいつか分からない若造に自分の姿を晒してまで協力をするなんて優しさは持ち合わせていない。姿を晒すことは俺のような商売の場合、即命取りに繋がることもある。そんじょそこらのヤツに容易く名乗れる身分でないんでね。だから俺がお前さんを試したんだ。俺の正体が・・・いや蓮花の正体が見破れるかどうか」
男はそう言った後、おかしそうにフフフと笑った。
「しかしこうもあっさりと見抜かれるとはね。最低でも二週間かそこらかかると思っていた。どうして分かった?」
「蓮花さんが・・・いえ、蓮花さんの替え玉になっているあの女性が自分に教えてくれたんです」
「クリスが?」
「クリス? クリスと言うんですか? あの女性は」
「ああ、クリスティ。俺の双子の妹だ」
なるほど。道理で顔つきが似ているはずだ。
「ではステージに上がっているのは彼女ですか?」
「だから蓮花は俺だって言っただろ? クリスティに踊りは踊れない。アイツ、もの凄いリズム音痴だし、なんでもかんでも恐ろしく不器用なんだ。だからアイツが蓮花として立ち回るのは無理だ」
なるほど、クラブを訪れる百戦錬磨のVIP達を無言ながらも虜にする手管は目の前の男の太々しさが必要・・・ということか。
「で? クリスティが教えてくれたっていうのは・・・」
「最初に店の裏口で俺が声を掛けた時、彼女、耳に手をやったんです。まるで耳に仕込んだイヤホンで誰かの指示を仰いでいるような仕草でした。一時潜入捜査で民間ボディガードの職に就いた時、ああいう仕草はよく見ていました。SPやボディガードは、よくそういう仕草をしますから。そしてあのメモ。『真の姿を見極めなければ、欲するものは手に入らない』とメモには書いてありました。それが最大のヒントです。彼女はホンモノの蓮花ではないと思ったんです。ホンモノの蓮花は他にいると」
男は、櫻井の言葉を聞きながら腕組みをして唸り声とも溜息ともとれる息を漏らした。
櫻井は続けた。
「でも、その時点であなたがホンモノの蓮花だとは分かりませんでした。そうじゃないかと思ったのは、翌日です。自分が彼女のボディガードに跳ね飛ばされた時、自分は彼女の目を見返しました。同情するような瞳で見つめ返す彼女は、一瞬だけあなたに目をやったんです。ほんの一瞬ですが。その時に自分は、蓮花であるクリスティさんが店を出入りする時、必ず掃除夫であるあなたが同時に出入りすることに気がつきました。そして、初日、突発的に自分がクリスティさんに近づいた時も状況を的確に把握して指示が出せたのは、その場に居合わせたからだと確信したんです」
「なるほど。それで一番体格の近い俺に声を掛けてきた、ということか」
櫻井は頷いた。
「ボディガードの連中はあまりにも体格が違いすぎる。ダンサーの女の子達は、初日その場にいなかった。いずれも立ち会っていたのは、あなただけでした」
それだけ聞くと、男はバツが悪そうにカリカリと頭を掻いた。
「 ── ちょっと出入りする時の段取りを考え直さなきゃならねぇなぁ・・・」
男は、英語でそう愚痴った。
「で、自分は合格しましたか」
櫻井が強い口調で言いはなった。「ん?」と男が目線だけ櫻井に向ける。
「協力していただけますか」
男の返事如何のよって、香倉を無事に救出できるかどうか決定することを櫻井は十二分に理解していた。
それだけに男のもたらすしばしの沈黙がもの凄く長く感じたし、怖くも思えた。
男はその美しい面差しにニヤリと不適な笑みを浮かべると、ゆっくりと手を差し出した。
「俺の本当の名前は、クライド。クライド・リーだ」
櫻井はその手を握り返す。
「高橋です。高橋秀尋」
そう答えた櫻井だったが、不思議と相手は反応しない。
櫻井が怪訝そうにクライドを見返すと、クライドはこう言った。
「手のひらが妙に汗ばんでるぜ。── 俺はお前に本当の名前を教えてる。お前の本当の名前はなんだ」
どうやら、相手の洞察力もなかなかのものらしい。
櫻井は観念して再度自己紹介をし直した。
「櫻井正道といいます」
「オーケイ、マサミチ。言っておくが、俺が本当の名前を教えるなんて特別だぜ。その代償は高いから、覚悟しておけよ」
クライドはそう言って、さも楽しそうに握った手を上下に揺り動かしたのだった。
接続 act.32 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
先週は、お休みしてすみませんでした。
一応、一週間経って落ち着きました。
久々に人の死というものに立ち会って、なんというかかんというか、いろいろ考えました。
毎日見ている日常の世界は、結局絶対同じじゃないんだなぁというか。
見た目は同じなのに、この世界にはもうあのお父さんは(妹の義父のことです)いないんだなぁと思うと、同じ世界ではないんだと感じてしまいました。
でもきっと、毎日誰かがどこかで亡くなってるんだと思うから、結果的に同じ世界は二度とない、と。
そう思えば、なんとなしの毎日も貴重なものだなぁと思うのです。
昨日はいたのに、今日はもういない。
人の死って、悲しいよりも残された者にとって凄く寂しいものなんだなぁと痛感させられました。
── そう、寂しいんだよ。もう会えなくなると思ったら。
ね、羽柴君。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
