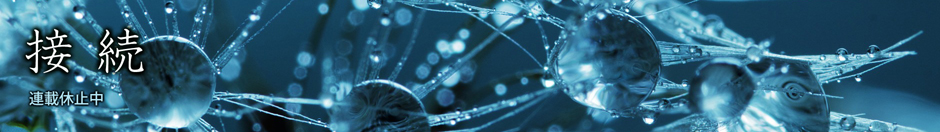
act.17
もう耐えられないんだ。
そう彼は言った。彼 ── ドクが。
僕らは、作業部屋で会う度に、白い人達の目を盗んでは話し込むようになっていた。
残念ながら僕はまだ自分が誰なのかを思い出せずにいたけれど、ドクが言うには日々毎日、彼は新しい記憶を取り戻してきていると言う。あの注射を打つことをやめていさえすれば、きっと僕もそのうち記憶を取り戻せるとドクは僕を励ましてくれた。
そしてドクは、一際周囲の視線を気にすると、安全を確認して僕にこう耳打ちしたんだ。
「僕は近いうちに、ここを出ていく」
僕は心底驚いた。
ここを出ていくだなんて、思いつきもしなかったからだ。
第一、ここは一体どこで、ここを出たらどんなことになっているなだなんて、想像もできない。
でもドクは本気だった。
ここを出られれば、きっと何とかなる。
外の人達にここのことを知らせれば、協力してくれる人がいるかもしれない。
そうすれば、ここにいる仲間みんな、助けられるってそう言うんだ。
そうかもしれない。
ドクの言うことを聞いていたら、僕もどんどん、そんな風に思えるようになってきたんだ。
ドクは、彼自身ジャングルの側の村で育った子どもだったと僕に話してくれた。
だからきっとここを出ても、周囲はジャングルなのだから、ドクはきっと逃げおおせる。
そうすれば僕も、きっと本当の僕自身を取り戻して、自由になれるんだ。
櫻井が井手に再会した翌日、櫻井はセイフティ・ユニゾンの本社事務所に出勤していた。
警備対象の河田が出国した今、山田が宣言した通り、河田についていたチームは比較的ゆっくりした時間を持てるようになったのだ。
とは言っても、隣のデスクでは山田がこれまで貯めてきた報告書を片付けるために、うなり声を上げながら頭を抱えている。
元々機動隊出身の山田は、どうも肉体重視派のようでデスクワークが苦手らしい。
その点、日頃からデスクワークも比較的マメに行っていた櫻井は、上司の陣野が読み終わった朝刊を受け取って、自分のデスクでそれを広げた。
いつも早朝に河田の家に出向くため、新聞を読むのは昼休みになってしうまうのが常日頃だが、今日はゆっくりと新聞を読める。それだけでどこか、ゆったりした気分になれた。それに、井手と再会できて自分が生きていることを知らせることができたのが、何より気分を楽にさせていた。
今、こんな自分がいるということは、それなりに自分がそれを『重荷』に思っていたのだということを櫻井は自覚した。
── まったく、自分自身の気持ちについてこんなに疎いだなんて、本当にしょうのない人間だ、俺は・・・
櫻井は内心、苦々しく思った。
自分の生存が井手にばれたことについて、昨日の段階ですでに榊には正直に報告していた。
隠し立てしたって、どうせすぐにばれる。それならば、自分から申告した方がいい。
そうした櫻井の判断は、あながち間違いではなかったらしい。
榊は、「あ、そう」と言ったきり、その後その件には触れてこなかった。
あまりにあっさりしていたので、さすがの櫻井も拍子抜けしたが、相手が井手だったということで許されたのだろうか、とも思った。
以前香倉から聞いた話ではあるが、榊は井手のことが気に入っているらしい。気に入られすぎて、時に面倒なことを井手は榊に押しつけられているとも言っていた。
── こんなことを思うと、きっと井手さんには怒られるだろうけど。
櫻井はそう思いながらも、実はあの二人、根本的にはよく似ているのではないかと櫻井は感じていた。
見た目は美女と野獣で雲泥の差があるが、芯の強さと、その熱さがどことなく似ている。
それに、どことなく『俺様』なところも。
「そんなこと言ったら、間違いなく殺されるよな・・・」
櫻井がふいにぼそりと呟いた独り言が、山田の耳に届いたらしい。
「なに、何だよ。誰が殺されるって?」
櫻井に向けてきた顔つきが爛々と輝いている。
「いや、別にこっちのことです」
櫻井が慌てて切り返すも、山田は報告書を仕上げる作業をさぼる口実ができたとばかりに、突っ込んでくる。
「昨日の彼女だろ。お前も隅に置けないな。あんな年上のお姉様が好みとは。確かに、浮気なんかしようものなら殺されそうなほど気が強そうだったけど、あれぐらいの美人じゃ、我慢しちゃうよな」
どうやら山田の中では、井手と櫻井が付き合っているのが確定しているらしい。
「あの、違いますよ。自分は・・・」
「テレんなよ。いいじゃねぇか、年上好みでも。どうだ、熟女のテクニックってのは」
話はどんどん下世話な方向に転がり始めている。
その手の話は、今だ櫻井は苦手だ。
公安特務員の訓練所でも、男ばかりの宿舎なので夜はそういう話になることもあったのだが、櫻井はまるっきりついて行けなかった。そういう話をしていると喉の奥がつっかえたような気分になる。
今もそんな感覚を覚え始めていたので、櫻井は「新聞の三面記事の話ですよ」と言い切って、この話題を止めた。
山田は、「なぁんだ」と見るからに残念がって、自分のデスクに向き直る。
櫻井は、言い訳にした三面記事に目をやった。
その中で櫻井は、殺人事件を扱った小さな記事に目をとめた。
夕べ起こった殺人事件だ。
所轄署が、潮ヶ丘署だったことが櫻井の目を惹いた。
潮ヶ丘署は、櫻井が勤めていた所轄署だ。
そこでは今なお、高橋警部や吉岡刑事が日々様々な犯罪を追いかけている筈だった。
櫻井は、その小さな記事を読み込みつつ、「おや」と思った。
被害者の名前。
田中省三(43)。
── どこかで聞いた名前だ・・・
そう思いつつ、その後の被害者の職業を読んでハッとした。
フリーライター・・・。
櫻井の脳裏に、ぼさぼさの長い髪を無造作に束ねた男の顔が浮かんだ。
櫻井は、とっさに自分のデスクの引き出しを開ける。
そこにお目当ての名刺がなくて、櫻井は少し舌打ちをした。
そういえばあの時貰った名刺は、報告がてら阿部に手渡していたのだった。
記事には被害者の顔写真がついていなかったので何ともいえなかったのだが、あの独特の胸騒ぎがわき起こってきていた。
そう、刑事時代、何度となく味わってきていた感覚。
大抵こんな胸騒ぎが起こる時は、その情報の中に大事な手かがりが潜んでいる。
自分でもそれがどこからくる感覚なのか、今ひとつ裏付けがなかったが、それでもよく小さな情報から決定的な手がかりを掴みだし、よく吉岡に感心されていたものだった。
── これがもし、あの『ぼさぼさの長い髪を無造作に束ねた田中省三』だったとして。そしてもしそれに、オゾッカが関係しているのであれば。
ガタリ!
突如立ち上がった櫻井に、山田はびっくりしたようだ。
「おい、どうしたんだよ、驚かすな」
山田にそう言われ、櫻井は小さく「すみません」と謝った。
だが、心中はそれどころではなかった。
何の確証もないが、いやな予感が胸をつく。
── 井手さん・・・大丈夫だろうか・・・。
櫻井がそう思った時、陣野に呼ばれた。
「河田さんが帰ってくるまで、別の担当のフォローについてくれ・・・」
陣野に新しいクライアントの話を聞きながらも、櫻井は背筋に浮かぶ悪寒を止めることはできなかった。
その日井手は、問題の患者と向き合っていた。
問題の患者とは、例の夢を見続けている八人の中の一人だ。
患者の名前は岸本緑といい、華道のとある流派の家元で、息子は代議員という経歴の持ち主だった。
それだけに身なりもきちんとしていて、若い頃はそれ相当の美人だったことを伺わせる顔には薄いブルーがかった上品なメガネをかけている。髪の色は染めておらず白髪が目立ってはいたが、それもまた彼女が上手に年を重ねていることが伺えるほど、美しく整えてあった。華道の家元ではあるが、髪型は活動的なショートヘアで、今日の服装も洋服であった。
井手が、いまだあの夢を見続けているのかと訊くと、彼女は「ええ」と頷いた。
「毎日、ジャングルの中にある建物のなかで、ウォーキングマシンで歩いたり、簡単なパズルをして遊んだり。呑気な生活をしていますわ」
彼女はどうやらあの夢のことを受け入れているようで、不気味には思ってはいても、怖がってはいない様子だった。もっとも、毎晩同じ夢を見ているのだから、嫌でも慣れてきてしまった・・・と言ったところだろうか。
「岸本さん、同じ夢を見るということに関して、原因は何かの薬物中毒ではないか、という意見があることについては、以前にもお話しましたね」
井手がそう言うと、岸本緑は「ええ」と頷いた。
井手はそれを確認して、製薬会社から取り寄せた投薬リストをカルテファイルの中から取りだした。
「岸本さんの他に七人の方が、岸本さんと同じ症状を訴えているということも、既にご存じですよね」
「ええ。それはもう。本当に不思議なお話ですわ」
「皆さんに共通することを、私はずっと探してきました。この現象の原因はどこにあるのか、と。病気には必ず原因があります。原因がわからないと、治療ができないからです」
井手がそう言うと、岸本緑は感心したように仕切りと頷いた。そんな緑に、井手は言い放った。
「そして私は遂に見つけたのです」
緑の表情が変わりきる前に、井手は畳みかけるように言った。
「オゾッカ製薬と繋がりがありますね」
一瞬の間が空いた。
「オゾッカ、製薬?」
緑は小首を傾げる。
「外資系の製薬会社です。主に医療専門の薬剤を卸している会社です」
井手がそう言うと、緑はああと声をあげた。
「私、以前大病を患っておりましてね。病院に長いこと入院しておりましたの。その時にお世話になっていたのかしら」
「まさにその通りです。岸本さんへの投薬記録を調べてみたら、オゾッカの薬品が使われていました」
「まさかその薬品が、この夢の原因だと?」
逆に井手はそう訊かれ、井手は首を横に振った。
「残念ながら、他の八人は岸本さんと同じ薬剤を使用していませんでした」
「あら、そうなんですか。それじゃ原因とは違いますわね」
緑は強い口調でそう言う。どうやら触れられたくないことでも突いたのか。
井手は一転して、気さくな笑顔を浮かべると、
「ごめんなさい。なんだか尋問のようになってしまいましたわね。近頃、刑事ドラマにこっちゃって、他の患者さんにもからかわれたんですよ」
と言った。緑も井手の思わぬ柔らかい笑顔に表情を緩ませる。
「本当ですよ、先生。まるで取り調べ室に座っていたみたい。いやぁね」
「ごめんなさい」
井手がふふふと笑うと、緑も同じように笑った。
そんな砕けた空気の中、井手は最後にこう訊いた。
「では、オゾッカ製薬の方とは直接お会いにはなってなかったのですね」
岸本緑はぴたりと笑うのをやめると、「ええ。会っていません」と答えたのだった。
岸本緑はそう答えたが。
実のところ井手は、そう考えてはいなかった。
岸本緑とオゾッカの社員は、間違いなく病室で顔を合わせているはずだ、と井手は考えていた。むろん、それは岸本緑だけではない。他の七人も、だ。
井手は、以前病院で見かけたオゾッカ製薬の営業マンの姿を思い起こしていた。
確かに通常の製薬会社の営業が出入りするのは、医局やナースセンター、薬剤部が主な場所で、彼らプロパーが病室に立ち寄ることはほとんどない。
その点で言えば、岸本緑の言ったことは自然なことだった。
── だが。
井手は彼女自身の目で、オゾッカの営業マンが病室に立ち入るのを見ていた。
それも重病患者の病室へ。
あれはほんの偶然だったのだろうか。
あの営業マンの知り合いが入院していたとか?
しかし、井手の頭の中には、端からそんなことは思っていなかった。
あの公安がマークしている製薬会社が、こうして今、井手の患者にも関係していること自体、もはや自然なことではない。
絶対に何かある。
きな臭くて、仕方がない。
井手は、岸本緑に対してオゾッカの名を口にした時の彼女の表情を思い浮かべた。
一瞬、完全に時が止まったかのような、こわばった顔つきをしていた。
実はそれは、岸本に限っての話ではなかった。
岸本の他にも既に五人、同じ話をしていた。
そして五人の誰もが、緑と同じ顔つきをしていた。
── もう一度、オゾッカに行って確かめる必要がある。・・・さて、どんな風にアプローチしたらいいかしら。
井手はそう考えあぐねながら、受話器を取って、オゾッカ製薬の番号を押した。
接続 act.17 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
いや~~~~~~~~~~、始まりましたね。男児バレー。あ、ミスタイプ。男子バレー。女子は見事北京を決めましたが、男子はやはり世界のレベルが高くて厳しい闘いが予想されます。
でも、見ちゃうのよねぇ~。ちょもなが氏がかわいいから。監督、漢前だから(笑)。
ってか、今日の対戦相手のイタリアって、男子なのになぜユニフォームがピッチピチなんでしょう。あれはフェロモン系を意識してるんでしょうか(笑)。日本人にはないぴっちりさ。すごい。ビーチク、目立つし(青)。あれじゃ集団シャラポアだ。
さっすがイタリア男。みな無精髭で、伊達男のこぃいフェロモン出しっぱなしです。
頑張れニッポン! あんなフェロモンに負けるな!!!
日本男児の心意気を見せるのだ、監督!!!!(←チームの中で唯一『漢』をムンムン感じさせる存在)
そして皆さん、オギノアニキのふっさふさな前髪もご注目ください(笑)。
(ああ、なんて邪な視聴者だろう・・・)
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
