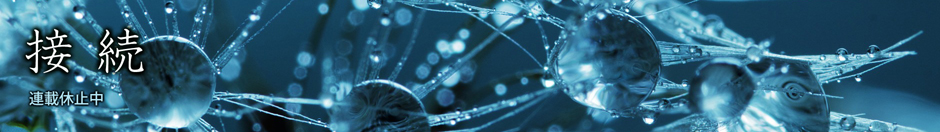
act.16
僕だけじゃなかったんだ。
ここがおかしいところだっていうことに気づいているのは、僕だけじゃなかった。
今日、いつもの作業棟でいつもの運動をしている時、向かい合わせのマシンで運動していた男の子が僕をじっと見ていた。
その目は明らかに他の仲間達と違って、何か言いたげに僕のことを見ていたんだ。
僕が怪訝そうに眉を顰めてみせると、彼は僕が視線に気がついたことを喜んだのか、少し笑った。
そして二人で、密かに周囲の白い人達の様子をうかがった。
幸いなことに白い人達は、僕らが視線で会話をしていることに気づいていない。
彼は僕より少し若い感じがした。
僕より後からここに連れてこられたに違いない。
彼の口が動いた。
声は出せなかったから、僕は必死に彼の唇を読んだ。
彼も僕が彼の言葉を理解するまで、何度も何度も必死になって同じ言葉を無言で繰り返した。
そうして僕は、やっとその意味を理解したんだ。
── 僕の名前は、ドクです・・・・
彼はそう言っていた。
彼は僕よりずっと前に正気を取り戻していて、自分の名前まで思い出すことに成功していたんだ。
名前・・・名前。
そう、僕にもきっと名前があるはずだ。
彼みたいに、僕にも僕だけの名前が。
僕らの宿舎は別棟だったので、それ以上彼と話をすることはできなかったが、少なくともここが『おかしい場所』だということに気づいている人間が僕の他にもいたことに、僕は感動したし勇気が湧いてきたんだ。
今に僕だって、きっと彼のように僕自身の名前を思い出すだろう。
僕は早く、ドクに僕の名前を教えてあげたいと思った。
久しぶりに降り立った異国の地の空気は、日本では経験できないほどの湿気があって、ねっとりとしていた。
季節は春から初夏にかけての頃だったが、温度自体はもう夏といっていいほど蒸し暑く、普通にしていてもサウナに入っているような気分になった。汗で白いTシャツが素肌に張り付く感触が、益々東南アジアの地に到着したことを痛感させてくれる。
外国には、その国独特の匂いがするとよく言うが、ここカンボジアにも特有の匂いがあるようだ。それは香倉が空港に降り立ったその瞬間に感じた。
例えればそれは、雨に濡れた木々の青臭い香りとほんの僅かな線香の香り、そして南方独特のスパイスの香りが入り交じったかのような匂い。
香倉は、いよいよ自分が確信を得る現場に来たのだと感じて、身が引き締まる思いがした。
以前海外で活動していた時は、毎日が緊張の連続で気を休めることはしなかった。
それほど危険な任務だったし、海外は明らかに日本での任務とは違っていた。
公安本部からのフォローアップはごく限られたものになり、特務員はほとんど自力で捜査を遂行しなければならない。
万が一そこで何が起きようと、責任を取るのは自分自身でしかない。
時には、自らの命で責任を取る形になることも実際のところなくはないのだ。
香倉も、歴代の先任者の中で世間に知られることなく殉職していった先輩の存在があることを十二分に知っていた。
幸い今回の任務は、香港にいた時のものとは比べようがないくらい危険性は低い。
今はオゾッカと利賀のつながりとその理由を知るための情報収集が最終目的で、具体的に何か行動を起こす必要があるという訳ではなかった。だからその分いくらかは気が楽だったが、その気の緩みが我が身を危険に晒すことになるのは分かっていたので、だからこそ香倉は気を引き締めたのだった。
空港を出た利賀と香倉は、まず利賀がいつも定宿としているプノンペンのホテルへと向かった。
そこは観光客が泊まるような小綺麗なものではなく、バックパッカーが使うような安宿だったが、寝起きするだけなら十分の設備を備えていた。値段の割に部屋もきちんとしているし、部屋の外にあるトイレも意外に清潔感があった。さすがカンボジア歴の長い利賀だけはある。地元の事情には詳しいようだ。
ひとまず互いの部屋に荷物を置いた後、二人で食事に出た。その時点で既に日没を迎えていたから、具体的な研究活動は明日からということだ。
街には、夜になっても多くの小型バイクが騒がしい音を立てて走っていた。その中にちらほらと車も混じる。素朴なエンジン音と甲高いクラクション、人々の熱気・・・一昔前の日本も丁度こんな感じだったろう。
利賀と共に近くの市場にある屋台まで向かう道すがら、学校帰りの子供達の姿も見かけた。小綺麗な制服を着ている。都市部だとそうした裕福な家庭もあるのだろう。
しかしそんなこの国でも、つい30年ほど前まではこの国も共産国だった。悪名高きポル・ポト政権下の元、恐怖政治が行われていた。今でもこの国には、その頃の名残でプノンペンには『毛沢東通り』という道があるし、国中のあちらこちらに今だ地雷原が残っている。
屋台に着くと、店主が利賀に挨拶をしてきた。
利賀も流ちょうなカンボジア語で返事を返す。
どうやらここは馴染みの店らしい。屋台といっても、きちんとしたテーブルと椅子が店先にいくつか並ぶ、オープンエアの軽食屋といった風情である。
慣れた様子で席に着く利賀に続いて、香倉もその向かいに腰を下ろした。
「さすがに慣れてますね」
香倉がそう言うと、利賀はテレくさそうに笑った。
「何十回と来てればね。いやでも慣れるよ。東城君は言葉大丈夫なの?」
「それが・・・。広東語はいけるんですけどね。東南アジアの言葉は・・・」
それは嘘だった。
利賀ほど流ちょうとは言えずとも、日常会話程度なら理解できたし話せた。
香港にいた頃、任務上カンボジアやタイ、ベトナムの人間と取引することもあり、基本の会話は一通りできるように学んだ。主にその土地土地の女達から。
それでも香倉が言葉が不自由であると言った理由は、そのことで利賀が気を許し、現地の人と話す内容を知るためだった。ここで香倉が言葉が分かるとなると、利賀だって話す内容が変わってくるだろう。
利賀は香倉の言ったことを素直に信じたらしい。
「そうなのか。でも大丈夫だよ。明日訪ねようと思っている王立農業大学には日本語が話せる学生がいるから」
「そうなんですか。それは助かるなぁ。じゃ、誰か通訳を探すようにしてみますよ」
「僕が頼んであげようか」
「いいえ。利賀さんもご自分の研究に早く取りかかりたいでしょう。今回の研究旅行費には通訳代は含まれてませんから、俺のポケットマネーで何とかしますよ。話せない俺の方がいけないんですからね」
香倉がそう言うと、利賀は益々安心したように頷いた。
これで香倉が本気で自分と別行動を取ろうと考えているのが改めて理解できて、ホッとしているのだろう。
「何なら明日、王立農業大学に行くのは俺一人で行くようにしましょうか」
香倉は畳みかけるように言った。
「利賀さん、ホント言ったらそこには用事、ないんでしょ」
それは図星だったらしい。
利賀の目が輝いた。
「いいのかい?」
「ええ。そのかわり、利賀さんの名刺をください。それと誰を訪ねて行ったら話が早いかを教えてもらえると助かります。そうすれば、アポイントも俺が取りますよ」
香倉がそこまで言った時、料理が運ばれてきた。
独特の香りがする青々とした香草の炒め物と長細い米、串焼きの肉が青いチェックのビニールクロスの上に並べられていく。どれもかなりのボリュームだ。
料理を運んできたのは、さっき利賀と言葉を交わした店主だった。
料理を置いたついでに、利賀と言葉を交わす。
香倉は、香草を柄の太い箸で口に運びながら、何気なく二人の会話に耳を澄ませた。
店主は利賀に、「もうメイのところには顔を出したのかい?」と利賀に訪ねていた。
どうやら、利賀の女はカンボジア人らしい。
利賀も、香倉がカンボジア語は分からないことで気を許したのか、「まだ行ってないよ。まだ同僚が一緒だからね」と答えていた。
店主は「メイはあんたが帰ってくるのを首を長くして待ってるよ。早く帰ってやりな」と利賀の肩を叩く。利賀は苦笑いしながら、「もちろん、今夜帰るようにするよ」と苦笑いした。
── 帰る・・・帰るか・・・。
香倉は、ポーカーフェイスのまま食事を続けつつ、しきりと考えを巡らせた。
ひょっとして利賀は、こちらで家庭を持っているのかもしれない。そうでなければ、「帰る」だなんて表現は使わないだろう。
── カンボジアに、現地妻か。
利賀もなかなかやるじゃないかと内心思いつつ、そんなことをお首にも出さず香倉は利賀に笑いかけた。
「なかなか美味いですね、これ。彼に美味いって言ってるって伝えてくれますか」
利賀もリラックスした笑顔を浮かべ、店主に再び向き直るとカンボジア語で「同僚が美味いって褒めてるよ」と言った。店主は香倉に向き直ると、親指を立て「オイシネ」と片言の日本語で返してきた。香倉も同じように親指を立てると、「yas、オイシ」と返した。
店主は満足したように、キッチンへと帰る。
利賀も安心したようにハッと息を吐き出して、食事を始めた。
そんな香倉の視界に、小学生ぐらいの男の子がビニール袋を持って客が席を立ったテーブルを回っている姿が見えた。
裸足で薄汚れた洋服を着た彼は、客が残していった料理を次々とビニール袋に入れている。
店の店主はいつもの光景なのか、気づいていても何も言わない様子だ。
利賀が香倉の視線に気づく。
「ストリートチルドレンだよ」
利賀が手短にそう言った。
「都市部と農村部の貧富の差が近年益々酷くなってね。貧困や虐待に耐えられなくなった農村部の子どもが、都市部にやってくるケースが後をたたない。彼らはもちろん学校なんて行ってないし、誰も彼らを守ってくれない。こういう子ども達が麻薬や人身売買なんかの犯罪によく巻き込まれるんだ。この国が抱える最も深刻な問題だよ」
「そうなんですか・・・」
むろん香倉も、知識では知っていた。
カンボジアに来る前に一通りの予備知識は頭に入れてきた。
だが文章で読むのと実際に見るのでは衝撃が違う。
思えば、香港の九龍城でもこのような子ども達が息を潜めて暮らしていた。
しかし、カンボジアではその数の多さが際だっているという。
利賀が言ったように、確かにそういった子ども達が攫われ、人身売買されるケースも多々あるだろう。彼らの中の誰がいなくなったって、それを気にかける大人がどれほどいることか。カンボジアの警察当局も、彼らの身に起こる危険にどれほど対処できていることか。分かってはいるが、実状はどうしようもない・・・と言ったところだろう。
── この世の中には、不条理なことが多すぎる。
人間・・・それは往々にして大人達の仕業だ・・・の愚かさを痛感させられる光景だった。
香倉は結局、自分の分の串焼きに一切手をつけず、席を立ったのだった。
接続 act.16 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
皆様、ただいま帰って参りました。
無事に九州旅行から帰宅でございます。
十二分に羽を伸ばして、二回目のドラリオンも堪能してまいりました。いや~、おもしろかった。二回目も。
さて、今回の「接続」は、非常に社会派色が強い回になりました。
国沢は実際にカンボジアには行ったことがないんですが、一度はアンコールワットを見に行きたいと思っている美しい国だと思います。
でも、現実には今だ本当に地雷原を抱えていたり、ゴミの山で暮らす子ども達がいたりと、ヘビィな問題を抱えていたりするんですよね。カンボジアは。
でもそれは決して人ごとではない問題なんだなぁと思います。(そこで何もできないところが自分の不甲斐ないところというか・・・)
しかし、モーホースキーな小説でこんな重いシーンを書いてるオイラって一体・・・(汗)。
国沢は、毎回お話を書く度に、国沢自身の中で「裏テーマ」を作るようにしているのですが(表テーマはもちろんモーホーラブがメインっすよ!)、今回はえらくヘビィーなことを裏テーマにすげちゃったな・・・と思ったりもしてます。
ま、もっとも、裏のテーマなので、読み手の方に絶対理解してもらわなければならない・・・というものではありません。
読み手の方には、それぞれがそれぞれで感じてもらったものを大切にしてもらえれば・・・と思っています。や、そんな偉そうなこと、言える立場じゃござんせんが。
たかがモーホースキー小説。されど、モーホースキー小説。
なんてな。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
