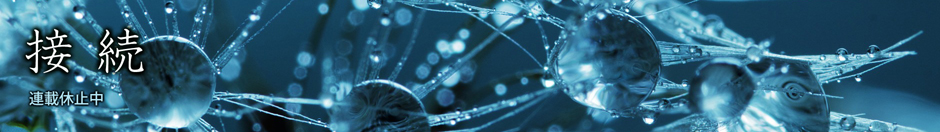
act.10
<第二章>
何だか、身体が重い。
今日も同じようにあの注射をきちんと打っているのに、何だか身体が怠いんだ。
いつものように並んでゾロゾロと歩き始める頃には、僕の心臓はドキドキし始めた。
なぜなら、僕はこう思ったからだ。
身体が鈍く感じるのは、僕が何かの病気にかかったんじゃないかって。
そうなると僕は、黒い腕章の人たちに連れて行かれてしまう。
そして二度とここには戻ってこれなくなる。
僕は、そ~ろりと白い人たちの様子を伺った。
白い人たちは別に僕のことなんか気にする素振りも見せず、いつものように僕らを作業舎に連れて行く。
絶対に黙ってないといけない。
絶対に、僕の身体がおかしいことを気づかれてはいけないんだ。
彼はチラチラと壁に掛けられた時計を気にしていた。
今日はなんとしてでも早く仕事を終わらせて、極めて自然に研究室を後にしなければならない。
利賀は、久しぶりの河田からの呼出に、少し緊張気味だった。
三日前、河田が突然菅原の研究室を訪れた際、彼はさり気なく利賀の膝を叩いた。しかも二回。
それは「三日後に例の場所で落ち合う」という暗号だった。
── 一体、今度は何の用だろう。
利賀が河田と協力関係を持ち始めてしばらく経つが、河田が必要としてきた利賀の役目はもう随分前に終わったはずだし、それについての報酬もすでに受け取っている。
ことは、済んだはずだった。
しかし、利賀は河田の呼出を断る訳にはいかなかった。
今だに利賀が個人的に用事でカンボジアに飛ぶ時の交通費は河田の会社が秘密裏に援助くれているし、利賀にとって一番大切な『家族』の面倒も、利賀が向こうにいない間、河田の会社はみてくれていた。
利賀の脳裏に『家族』のことが頭に浮かんで、嫌な緊張感が少し収まった。
カンボジアにいる愛すべきメイと娘のリーのことを考えると、利賀の心は幸せで満たされる。
メイは、利賀がカンボジアで出会った女性だった。
籍は入れていなかったが、いわゆる現地妻というやつだ。
利賀は非常に奥手な人間だったが、カンボジアにいる時は日本と違って少し開放的な気分になるのが常だった。
三十代の始め、勉強漬けだった利賀はまだ性体験がなかった。
純粋に忙しかったし、どことなく女性が怖かった。
だが、男で三十過ぎまで童貞ともなると、さすがにマズイと利賀は思い始めたのだった。
しかし日本では、三十過ぎの童貞男なんて相手になんかされない。
逆に気味悪がられるのがオチだ。
一度そういうお店の前まで行ったが、やはり勇気がなくて入れなかった。
日本の女は、やはり怖い。
皆、白々しい目で自分を見てくる。
それと違って、カンボジアの女は利賀に優しかった。
利賀がお金を持っている日本人だからなのかもしれないが、行く先々で優しくされた。尊敬さえしてくれた。
だから利賀は、三十三歳の時、カンボジアの娼館で初めて女を抱くことができた。
その相手がメイだった。
メイは、器量としてはごく普通の女性だったが、指がとてもきれいだった。それに、その娼館では最も気の優しい娘だと評判だった。
最初は、菅原教授についてカンボジアを訪れた時のみメイの元へ通っていたが、次第にメイに会うことが目的で個人的に赴くようになった。
対外的には、自分の研究のためという名目でカンボジア行きを研究室に申請した。菅原教授も一時期は殆ど向こうで過ごす時間が多かったこともあり、利賀の申し出をすんなり許してくれた。
事実、メイと会うことにより研究意欲にも張り合いが出て、ここのところ利賀の研究成果はよくなってきていた。
これまで後輩にどんどん出世の順番を追い越され、周囲から「ダメ人間」のレッテルまで貼られていた人間が、メイのお陰で息を吹き返したかのようだった。
自分の存在価値を見出すことができて、仕事にも張り合いがでてき、次第に芽生えてきた利賀の積極性を菅原教授もよろこんでくれた。
当然利賀は、メイをお客として抱くことはなかった。本当に恋人に触れるようにしてメイを扱ったし、実際気分は恋人同士であった。
むろん、メイが他の男性ともそういうことをしていることは重々承知していた。それがメイの生業だった。
でも、努めてそれを考えないようにした。
メイにも利賀と会っている時だけは、そのことを忘れてもらえるようにと利賀は努めた。
そのお陰か、やがてメイも利賀を同じように愛してくれるようになった。
大概、商売女として酷い扱いを受けることが多い中で、利賀だけは彼女にとっても特別だった。
利賀は恋人へ向ける本物の愛情をメイに注いでくれた。
身体を売って外国人から金を儲けるやり方は、メイの国でも人々から忌み嫌われた。町の人々はおろか、メイを買った客でさえもメイを白い目で見ることが多かったが、利賀だけは違っていた。
いつもメイをお姫様のように扱い、メイの身体を気遣い、メイの生活が潤うようなプレゼントをいつも持ってきた。メイが体調を崩している時はセックスすらせず、一晩添い寝をするだけの時すらあった。
こうして二人の愛情は、次第に本物になっていった。
二人が顔を合わせる度、メイを雇っている女将の対面もあって依然と金のやりとりはあったが、二人の間でそれはもはや形式的なことだった。
利賀とメイは、二人の立場を忘れて、未来への夢を次第に語り始めるようになった。そしてその思いは、真剣にメイを『身請け』する方法の模索へと発展した。
メイは貧しい田舎の出の女性で、田舎で暮らしている大家族を養うために娼館に身を売っていた。なので、彼女は簡単に仕事を辞めることはできなかった。
彼女からの送金が途絶えると、確実に田舎の家族は生活が立ち行かなくなることは分かり切っていた。
店側も、彼女を店に迎える時に多額の金を家族に渡しており、その借金もまだ残っていた。
いくら円が強いとはいえ、利賀の安月給では到底まかなえない。
オゾッカ製薬の河田は、そこに付け込んできた。
彼は、カンボジアでの利賀の動きをすべて把握していた。
オゾッカ製薬は、東南アジアに生産拠点を構えてから後、随分深くまで地域に食い込んでいた。
地元の人間を多く雇い入れ、他より少しいい給料を工場で働く人々に与えることで、カンボジア全体をほぼ掌握しているようなものだった。
工場で働く人達は、カンボジア全土のあらゆるところから集まって来ていたし、その為カンボジアの国内で起こっている事細かな情報がアジアを統括する河田の耳に入ってきていた。だから、カンボジアと縁深い日本の研究者の助手がカンボジアでしていることなど、手に取るように分かっていた。オゾック製薬のカンボジア工場は、どこの国の諜報機関より優秀な情報収集能力があった。
河田は、さりげなくそして抜け目なく利賀に近寄ってきた。彼が、メイを娼館から抜け出す手だてを全て整えることは雑作もないことだった。
河田は、メイの数多くいる兄弟や親戚をいい条件で工場に雇い入れることを約束し、メイの抱える借金も清算してくれた。
河田はメイの肩代わりした借金は無利息無担保にしてくれた。彼は、ゆっくりと返してくれればいいと二人に言ってもくれた。
こうして利賀とメイは、プノンペンの町の片隅で小さな新居を構えることもできるようになったし、新しい命も得ることができた。
当然、利賀も馬鹿ではない。
これだけのことを河田がタダでしてくれたとは思っていなかった。
利賀がそのことを指摘すると、河田はさも嬉しそうに笑顔を浮かべた。
「利賀くんは頭がいいから話が早くて助かるよ」
彼はそう言った。
河田の要求は、菅原教授の植物エキス抽出方法を秘密裏にオゾッカ製薬に教えてくれることであった。
河田が強調したのは、『秘密裏に』といったところで、当然利賀はそこに怪しい臭いを嗅ぎつけたのだった。だが、既に後戻りはできないところまできていた。利賀に断る術はなかった。
しかも河田は、カバーラと地元で呼ばれている植物のエキスを抽出する方法を知りたがっていた。
植物の有用成分を抽出するには、その植物ごとに違う方法を考えねばならない。
その方法を菅原教授に確立して欲しいと河田達は切望していた。
しかしカバーラという植物の特性からして、菅原教授が首を縦に振るとは思えなかった。
それは利賀ですら、すぐに分かった。
カバーラとは、阿片によく似た幻覚作用を引き起こす植物として、密林地帯で知られている植物だった。
近代的な医療の手が届かない山深い地域には、いまだにシャーマン ── 祈祷師的な役割を果たす人物が村々にいて、彼らが治療を施す際、それを使っていたのだった。
カバーラをすりつぶした汁を患部に擦り付けたり、また服用させたりして、彼らは患者の痛みを和らげた。
それまでどんな痛みで暴れていたとしても、カバーラを与えられると患者は途端に大人しくなった。皆、幸福感を感じ、穏やかになった。
なのでカバーラは、時として村で厄介者とされる暴力的な若者にも処方されることがあった。
そのような若者は、定期的にカバーラを与えることによって皆従順になり、村の長老の言うことをよく聞くようになった。
カバーラは、天からのさずかりもの・・・村人は例外なくそう言った。
そのカバーラのエキスを抽出するというのだ。その使用目的は安易に想像できる。
だからこそ菅原が、それに同意するとは思えなかった。
菅原は、決して汚い金では動かない性格をしていたので、河田の望みが叶えられる可能性はないに等しかった。
そこで利賀の出番だ。
利賀は長年菅原の側で彼の研究を手伝ってきた。
教授が考案した、いくつもの抽出方法のことも知っている。
だから菅原の代わりに利賀にカバーラの抽出方法を突き止めてもらおうと河田は考えたのだった。
利賀は内心、良心が痛むのを感じながらもそれに目を瞑った。
全ては、メイとかわいい娘の為だと言い聞かせた。
利賀が要求を呑まねば河田が次に何をするのか、想像するのは難しくなかった。そうなれば、メイとの幸せな生活は泡と消えていくだろう。
抽出方法を突き止めるには少々時間がかかるかも知れないと利賀は一応断りを入れたが、河田はそれでも構わないと言った。
こうして利賀は、カバーラに最も似ている植物の品種を調べ上げ、折を見て秘密裏に菅原教授のライブラリーから精製機の配置図を盗み出した。そしてそれを元に、カバーラのエキスを抽出する精製機を創り出した。
それが丁度四年前のことである。
河田は利賀の仕事に大変満足し、どういう訳かいまだに利賀とメイの生活のサポートを続けてくれているが、あれ以来河田が利賀に何か別の要求を突きつけてくることはなくなった。
だからこそ利賀も河田との約束を忘れかけていたところだった。
それが三日前、膝を二回ポンポンと叩かれ、一気に四年前に記憶を引き戻された。
河田は四年前の取引があった後も、きっと利賀を再利用する時がくることを見越して、利賀とメイの生活を援助することを止めずにいたに違いなかった。
利賀はそのことを思い、また再び背中に嫌な汗が滲むのを感じた。
先程までメイを心に浮かべ、幸せに浸っていたことが嘘のようだった。
利賀は再び壁掛け時計に目をやる。
するとふいに声をかけられた。
「何かお約束でもあるんですか?」
「え?!」
利賀が少し驚いて横を見ると、隣で東條が植物分類の資料を手書きで纏めながら、声を掛けてきたことが分かった。
東條は約一年前に研究室に入ってきた男で、抜け目のない仕事をすることで既に菅原から頼りにされている助手だった。助手としては一番の下っ端だったが、年齢が割と高いこともあってか妙に肝が据わっていて、全然下っ端という感じはしない。むしろもう何年もこの研究室にいたかのような錯覚すら覚えさせる男だった。
利賀は、普段から他の助手達と交わることが少ないので、当然東條ともそのような関係だったが、東條は度々利賀に話しかけてくることがあった。
東條は、尚もペンを走らせる自分の手元を見つつ、「利賀さん、さっきから時計気にしてるから」と言ってくる。「彼女とデートですか?」と言う時に初めて顔を上げた。彼にしては珍しく、暖かみのある笑みを浮かべながら利賀を見ていた。
「── そ、そんな・・・。彼女なんて、いないよ」
利賀が頭を掻きながらどもると、東條は「なんだ」と呟きながら肩を竦めた。
「さっき何だか幸せそうな顔をしてたから。てっきり僕は、利賀さんが久しぶりに恋人にでも会われるのかと思いました」
容姿が整い過ぎていて少し冷たく見える彼が、思惑柔らかな表情を見せたので、利賀は内心ちょっとホッとした。
利賀から見れば、東條はちょっと取っつきにくい男だなと感じていたのだ。東條が仕事ができるだけに余計そう感じていた。
東條は、再び自分の作業に戻りつつ、ぼそぼそっと呟く。
「実は僕も先日しばらくぶりに恋人に会えましてね。だから利賀さんも同じなんだって勝手に思って・・・。すみません、変な勘違いをしてしまって」
「え? 東條君、恋人いるの?」
利賀はそう言って、自分が変なことを口にしていると気が付いた。
東條なら、利賀と違っていくら勉強馬鹿だとしても恋人なんて余裕でいるだろう。自分とは違うのだ。
利賀は何だか無性に恥ずかしくなって、慌てて言い直した。
「いや、東條君なら、いて当然だよね。遠距離なの?」
東條は、それまで気のない風な感じで作業片手間に会話していたが、そこで初めて作業の手を止めた。利賀の方に顔を向けてくる。
「ええ、そうなんですよ。互いに忙しくてね。この前会えたのが三週間ぶり。その前なんて一年とか会ってなかったですからね」
「一年!」
利賀は思わず大きな声を上げてしまった。
自分がメイと会う頻度より少ないじゃないか。
「まさか彼女、海外に住んでるってこと?」
利賀は思わずそう口にした。
東條は少し考えるような顔つきをしていたが、「多分海外に行ってたような話は聞かなかったけれど」と肩を竦めた。
「でも似たようなものですよ。国内にいたって、側にいないんじゃね」
東條にそう言われ、利賀はなんだか親近感が湧いた。
自分が望んでも手にはいることがなさそうな魅力をたくさん持っている東條が、自分と同じ様な境遇なのが意外だったし、ちょっと嬉しくも感じた。
「それじゃ、寂しいよね。いつも会えないんじゃね」
利賀がそう言うと、東條はテレ臭そうに笑った。
「まぁ、そうですね。でも事情があるから仕方がない。そんなことで、駄々を捏ねるわけにもいきませんからね」
内心、利賀も同感だと思った。
本当なら、利賀だってメイを日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい。
でもそれはできなかった。
メイとの関係を公にするには、リスクが大きすぎる。
大学というところは・・・いや、大学でなく日本の一般企業でも元・売春婦・・・しかも外国の人間を妻に迎えるだなんていうのは敬遠されるはずだ。それにスキャンダルとして大学中に知れたら、新設校でイメージ第一主義ある大学側が利賀を雇い続けてくれるか怪しくなってくる。
養うべき家族がいる以上、職を失うわけにはいかない。
そんな自分の苦労が、東條の話とシンクロした。
「でも、意外だったな。東條君が恋愛で苦労してるなんてね」
深い同情心を込めて利賀がそう言うと、東條もにっこり笑って、「僕も意外でしたよ」と返してきた。
「え? 何がだい?」
「だって利賀さん、僕が知る範囲、こんなたわいのない話、今まで誰ともしてきたことないから。私語するのって、嫌いなのかと思ってました」
「そんな、嫌いという訳じゃ・・・・」
利賀は口ごもる。
本当は、どうやって他の助手達と会話していいか分からなかったからだ。
こんな風に気さくに利賀に話しかけてくれた人は、東條以外には今までいなかった。
「ただ、ちょっと苦手だっただけだよ」
利賀がか細い声で答えると、東條は「そんなに怖がらないでくださいよ」と笑った。
東條は、そう言いながら手元の資料を作り終わると、席を立った。
「いずれにしても、利賀さん今日早く上がりたいのなら、仕事手伝いましょうか? 僕の今日の分の仕事はもう済みましたから」
東條はそう言いながら、手元の資料を真新しいファイルに綴じて、菅原教授行きのボックスにそれを投げ込む。
利賀はチラリと時計を見た。
確かに、一人でやるより東條に手伝って貰えれば、明日にこの作業を残さずに済むだろう。
東條は、さっきの会話のせいで利賀のこの後の予定を訊くことにも興味が失せたようだし、彼が意外に親しみやすい人物だということも分かった。
「じゃ、ちょっとだけ手伝ってもらおうかな・・・」
利賀がそう言うと、東條は「お安い御用ですよ」と親しみやすい笑顔を浮かべ、腕まくりをしたのだった。
接続 act.10 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
ひっさびさのお休みです。今月二回目のお休み。
や~・・・長かった。
それはさておき、読者の方々からいくつかご質問を受けたので、それにお答えしようと思います。
まず一つめ。
「イデねぇさんって、井手ですか、井手ですか?」
・・・。やぁ~・・・月日を感じますねぇ・・・。
って、すっとぼけている場合ではなく(汗)。
正解は・・・井手さんです。
すみません。作者本人がすっかり忘れちゃってます(汗)。
いくら国沢が誤字脱字王国の王様だったとて、準主役級のねぇさんの名前を忘れていようとは・・・。申し訳ないです(脂汗)。現在多忙につく多忙により、訂正するに至ってませんが、近々直すようにしたいと思います。
次二つめ。
うちの長老犬ちゃんと我が母上の具合についてのご質問をいただいたので、それについて。
ブログなんかでちらりと書いていた話題ですが、うちには齢21歳になる長老犬レンちゃんがおりまして、一年ほど「介護いる犬」としてオムツ生活をしていたのですが、昨年7月末に大往生いたしました。21歳五ヶ月。本当に大往生です。最後は静かに息を引き取りました。国沢としても家族としても、自分たちなりに精一杯お世話をしてきたという思いもあり、愛犬の死に寂しくもありましたが、やりきった感もあって、そんなに哀しみに満ちた最期ではありませんでした。なんというか・・・国沢も愛犬レンも互いに健闘をたたえ合う感じ。最期は、ご飯を口に運んで入れてもがんとして食べなかったレンちゃん。気が優しいけど変なところ頑固な彼らしい最期でした。
自分も、この世にさよならをする時は、彼のように死にたい。そう思いました。
現にレンが本当はどう思っていたか、国沢は犬語が分からないので何とも言えませんが、やはり納得できる死は美しいものだと感じました。
そして一方、うちのオカン。
去年の年末にむりやり退院してきたうちの母は、もうすっかりよくなりました。
ムリをするとさすがに膝に響くようですが、日常生活を行う上では大丈夫なようです。
ということで、国沢も主婦業から晴れて解放。現在仕事一本槍の日々をすごしております。主婦業にかまけてさぼっていた仕事が怒濤のようにたまってたというのが主な原因ですが(汗)。
おかげで、まだ確定申告のしの字もできてません(涙)。
やばい・・・。ホント、どうしよ・・・。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
