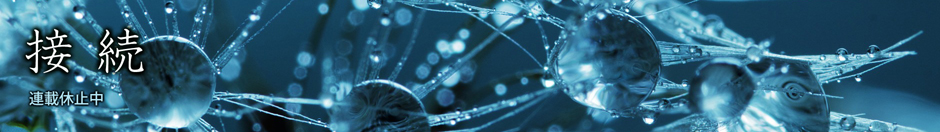
act.01
<はじめに>
外の空気はねっとりしていて、ちょっと気持ち悪い。
きっと毎日夕方になると凄い音を立てて降る雨のせいだ。
僕らは寝起きしている場所から作業するため所へ移る時に、その空気に引っ付かれる。そいつはいつでも濃い緑の臭いがした。
建物の向こうには、たくさんの葉っぱをつけた木がいっぱい生えている。
でも僕は、その木の名前を知らない。
僕がここに連れられてこられるまで、誰もその木の名前は教えてくれなかったし、ここに来てからもそんなことを教えてくれる人はいないからだ。
でも、この広場のいろんな所に建っている建物の中に入ると、そんな空気はどっかに行ってしまうんだ。
建物の中は外と違ってさらりとしていて、蒸し暑くもない。気持ちよくて過ごしやすい。いつでも同じだ。困ることは何もない。
湿気の多い生暖かい空気は人を病気になりやすくさせるらしいから、あの人達はそれを嫌っているみたいだ。
いつも僕らの身近にいる『白い人達』は、いつも凄く気を付けていた。
僕らが病気や怪我をすることに。
でも僕らの中で、そんなことを気にしてる人はひとりもいない。
せいぜい考えていることといえば、「一体自分が誰なのか」という酷くぼんやりとした『僅かばかり』のナゾだけだ。
[接 続]
<第一章>
「お疲れさまでした」
彼女がそう言うと、患者は大きな溜息をつきながら診療用のソファーから身体を起こした。彼は、自分が酷く汗を掻いていることに驚いたようだった。
「先生、それで・・・。その夢の意味は分かりましたか」
彼はそう言いながら上等なスーツの胸ポケットを探ったが、お目当てのハンカチは見つからなかったらしい。
精神科医の井手靜は、デスクの上に置いてあった自分のハンカチを差し出した。患者はテレ臭そうにそれを受け取ると、禿げ上がった額に浮かぶ汗を拭った。
「── 加藤さん・・・、まだ初診なので何とも言えませんが・・・。何かの記憶に関連したものかもしれません。ご自分が覚えておられない頃の記憶とか」
井手がそう言うと、患者は徐に頭を振った。
「いや、そうとは思えませんな。確かに私は大陸生まれだが、あんなジャングルのような景色は見たことがないし、それに何というか・・・」
「あなたのいた建物は、非常に近代的だった」
「そうです。その通り」
患者は、満足したように頷いた。
「別に取り立てて困っておる訳ではないのです。だが・・・これが毎夜毎夜ではどうにも気になってね」
井手も同じように頷いた。
「お気持ちはよく分かりますわ。夢をご覧になられるようになったのは・・・およそ一ヶ月前とのことですね」
井手は、同僚が井手に回してきたカルテと壁に貼られたカレンダーを見比べながら訊いた。
今日は、2001年6月23日。カルテには、『2001年5月20日より連続して見始めた』と記載されている。
「そうです」
「一ヶ月前に、何か変わったことはありませんか?」
「それについては、前のお医者さんにもないとお伝えしましたが・・・」
「ええ、そうですね。カルテにも書いてあります。でももう一度考えてほしいんです。これは非常に重要なことですから、加藤さん。原因の究明の糸口になるはずです。どんな些細なことでも構いません。そうですね・・・例えば、引っ越しされたとか、旅行に行ったとか。通勤する方法を変えたとか・・・。失礼、あなたの場合は迎えの車があるでしょうから、この線はないですね」
井手が苦笑いすると、患者も合わせて苦笑いした。
「先生、心当たりがないのですよ。残念ながらね」
井手は、真っ直ぐ患者を見つめた。
「── 本当に?」
しばらくの間があって、患者は答えた。
「・・・本当です」
早朝の光が射し込む誰もいないロッカールームの片隅で、青年はその素肌についた水滴をタオルで黙々と拭っていた。
くっきりと筋肉の筋が浮かび上がった逞しい胸板、そして腕。
ピンと張りつめた肌に覆われた背中にもびっしりと筋肉の筋が這っており、腰まで繋がっている。
小柄だがしっかりとした、完璧なトルソ。
そして、小気味よく締まった臀部から太股、足先に至るまで隙なくスレンダーな筋肉がうねっていた。
青白い光に照らし出されたその裸体にはいやらしさなど微塵もなく、寧ろ厳しく鍛え上げられた末の厳粛さすら感じさせる。
その静かな面差し。
一流の武道家を思わせる穏やかさと、触れたら切れてしまいそうな鋭さが同居している。
切れ長の目を彩るのは、右目の目尻にある泣き黒子。
その黒子を、すっと伸びた睫が二、三回叩く。
青年は、『高橋』と書かれたネームプレートが差し込まれたロッカーのドアを開ける。ガランとしたただっぴろいロッカールームに金属の擦れ合う音が大きく響く。
白いTシャツ、下着、警視庁のワッペンが肩口に縫いつけられた紺色の作業服、漆黒色の膝当て、様々な金具がついたベルト、ウエストバック、ガンホルスター、つま先に金属板が仕込まれた編み上げブーツ。そして・・・分厚い防弾ベスト。
もし現代に戦国武将が蘇るとしたら、鎧の替わりにつけるであろうその装備を、青年は手慣れた手つきで黙々と付けていく。
今やロッカールームには、衣擦れの音やマジックテープが剥がされる音が響き渡り、分厚い胸板や堅く引き締まった美しい腹筋もあっという間に無骨な被い覆われていった。
青年は防弾ベストの上を一回強く叩くと背後を振り返り、ベンチの上に置かれた書類に目をやる。
『通達書』と書かれたそれには、今日の試験がこれまで長い間行ってきた訓練の最終試験であることが記されてあった。
「お前に対するヒントはない。ゼロ。ナッシングだ」
青年・・・櫻井正道の目の前で、警視庁公安部のトップ・榊警視正は嬉しそうにそう言った。
「お前が持っていい装備はこれだけ」
目の前のテーブルに、ゴトリと黒光りするハンドガンの部品が並べられる。
櫻井は黙ったまま、手慣れた動きでそれを組み立て始めた。
榊の背後で、教官の腕章をつけた男がさり気なくストップウォッチを眺めている。
櫻井の手が止まると、そこには45口径のオートマチックタイプ、コルト社製のハンドガンが現れていた。銃口の下にはオプションのライトがついている。
教官がストップウォッチの数字を榊に見せると、榊は眉をくいっと引き上げた。
「だが、合格ラインだけは教えておいてやろう。九人。九人だ。三十分以内に九人の猛者を制圧しろ。弾はペイント弾だ。確実に急所を狙え」
榊がそう言いながら、弾倉を櫻井に向かって放り投げる。
「楽勝だろ?」
櫻井はそれを受け取りながら、そう言う榊をちらりと見た。榊はニヤニヤと嫌な笑みを浮かべている。その笑みが何を指し示しているのか、櫻井は直ぐに分かった。
ハンドガンの装弾数は、弾倉の七発に装填した一発を加えても全部で八発。相手は九人だから、一人一発ずつで仕留めたとしても一発どうしても不足する。最後の一人は自分の力で何とかしろ、ということか。
「お前は『お芝居』の教科が苦手だからな。せいぜい『体育』で点数を稼ぐことだ」
モニターで見てるからな、と言われ教官室を追い出される。
教官の後について案内された建物は、機動隊の訓練所敷地内にある鉄筋二階建ての小さな建造物だ。この日機動隊の演習訓練は完全にオフで、ごく限られた人間しか敷地内にいない。都心から大分離れた、富士山麓にほど近い広陵としたこの訓練所は、周りに『何も』なかった。つまり森や人口の建造物などのような隠れるところが全くないので、外部の人間が内部を探ろうとしても不可能な作りになっている。おまけに監視カメラや侵入者防止システムもしつこいほど設置されているので、外部の人間が入ってくることもまずありえない。機動隊の数ある訓練所の中でもこれほど警戒が厳重なところはまずなかった。
ここでは、機動隊の特殊訓練や新規導入機器の性能検査・訓練等が行われると同時に、機密性の高い公安特務員訓練にもしばしば使用される。
警視庁公安部に配備される特務員は、普段、一般精密機器製造企業の姿を隠れ蓑にした工場地区の地下訓練所で、様々な訓練や試験を行っているが、大規模なものになるとこの訓練所で行われることになっていた。
最も難しく厳しいとされる特務員最終試験についても、ここで行われることが多い。これが終われば、『仮免許』が貰え、短い休みが終わった後、実際に街に出て簡単な任務をこなす『本採用試験』が待っている。
そして今日、櫻井は訓練所での最後の試験を迎えていた。
同期の仲間は、昨日この試験でこてんぱんにやられ、病院送りになっていた。
試験と言いながらも、襲ってくる相手は限りなく本気なのだ。
櫻井が一歩建物の中にはいると、物々しい鋼鉄の扉が背後で閉ざされた。
ゴオォンという音が辺りに響き渡ると同時に櫻井の視界は真っ暗闇になる。
『時間は三十分しかないぞ』
建物内部に仕掛けているらしいスピーカーから、榊の声が聞こえてくる。
櫻井はその声にも焦らず、じっとその場を動かないで、目を闇に慣らした。
次第にうっすらとだが、建物内部の様子が見えてくる。
数歩足を進めると、ぽっかりとした闇がまた現れた。空気の流れに意識を集中すると、遠くの空間から、空気がそよいでくるのが感じられる。どうやら長い廊下らしい。
視野が見える範囲の壁に、ドアが見えた。規則正しく、ドアが両側の壁に向かい合っている。
想像するに、長い廊下の両側にそれぞれ個室が並んでいるのだろう。
そこに九人の敵が潜んでいるという訳だ。
櫻井はハンドガンを構えた。
ゆっくりと足を踏み出す。
暗視カメラで映し出されたモニター映像を見て、榊の後ろに立つ教官の一人が、ううんと唸った。
「オプションのライトを使いませんね」
大抵の訓練生が銃口の下に付いているライトを使ったのに対し、櫻井はまったくライトを点ける気配を見せなかった。
「よっぽど夜目がきくんでしょうかね」
もう一人の教官が呑気な声を上げる。
榊は一瞬、「馬鹿か。あれは耳と感覚で周囲を見てるんだ」と言いかけたが、それを言うこと自体バカらしく思えて、敢えて口に出さなかった。
明かりを使うと現状をよりよく把握できるが、同時に相手にもヒントを与えることになる。相手も暗闇の中に同じ条件でいるのならば、いっそライトを使わない方が相手に対するプレッシャーをかけられることとなるのだ。ただし、自分がその不利的条件を克服できる自信があればの話だが。
── それに・・・。
榊はニヤリと嫌な笑いを浮かべた。
櫻井を襲う九人の刺客には、全員暗視ゴーグルを装着させている。米国の夜間行軍に使用されるそれと同じものだ。
だからこの点で、刺客と櫻井の条件は同じでなかった。圧倒的に櫻井の方が不利であった。
── さて坊や、どうする・・・?
櫻井の動きは隙がなかった。
それはもちろん訓練で培われたものだったが、その隙のなさは天賦の才能からくるところもあった。
彼は順調に手前二つの部屋の安全を確保し、奥へと進んでいく。
「十分経過」
榊の隣に座っている主任教官がマイクで知らせた。
あと二枚目のドアで、最初の二人と出くわす手はずになっている。
その時が来た。
バタン!という音の後で、連続した銃声音が続いた。
スイッチングされたモニタに、櫻井の走る姿が一瞬過ぎる。
すぐに複数の呻き声が聞こえ、ペイント弾が発射される独特の音が二発続いた。
「どこだ? どこに行った?!」
榊達は、櫻井の姿を見失った。
一階にはあと二人いるはずだ。
榊が別のモニタに過ぎった影を追うと、グロテスクなゴーグルをかけた隊員を踏み台にして、まるで幅跳びの選手のように長い廊下を飛ぶ櫻井の姿が映った。
櫻井は、踏み台にした隊員の背後に控えていた二人目の首根っこを背後から捕まえ、ゴーグルをはぎ取ると、隊員を楯にした。前の隊員が焦って振り返える。ゴーグルがないことで目標を勘違いした隊員は、同僚にむけてマシンガンを撃った。マガジンの中には、実弾とは違うがペイント弾より威力の強い偽弾が装填されており、それを至近距離でまともに食らうと、防弾チョッキを着ていても衝撃の酷さに気を失う。
櫻井はガックリ項垂れる隊員の身体の後ろから、動揺する隊員の額をペイント弾で撃った。
先程のマシンガンの発射で起こった散発的光が、隊員の位置をシルエットながらはっきりと浮かび上がらせていたお陰で、ペイント弾は額のど真ん中に命中した。
教官の一人が口笛を吹く。
「これで四人仕留めましたな。それにまだ弾は三つしか使っていない」
榊はチラリとタイマーを見る。
櫻井は奪った暗視ゴーグルを被ると、足を進めた。
視界がクリアになった分、今までと違って動きがスムーズになる。
二階に続く螺旋階段では、マシンガンを撃ちながら下りてくる隊員の気配を素早く感じ、機敏に身を翻させ、手すりにぶら下がった。
櫻井の素早い動きにターゲットの姿を見失った隊員二人は、マシンガンを撃つのを止め、階段の中腹でキョロキョロと辺りを見回した。その間に櫻井は、するすると手すりを外側を伝っていく。
隊員達が気づいた時には、目の前に櫻井が突然立っていて、次の瞬間には喉元と胸部にペイント弾を打ち込まれていた。
グエッという呻き声が響く。
「── 六人目。あと三人」
二階では、新たな攻防が既に繰り広げられていた。
マシンガンを構えた隊員の股下を潜り、相手のベルトを後ろから掴むと、その手を引き上げて相手をひっくり返した。櫻井はその相手を足で踏みつけ自由を奪い、その胸にペイント弾を撃つ。次の瞬間には、新たに部屋に飛び込んでくるもう一人の隊員の気配を感じて、身をかがめた。マシンガンの弾が頭上を掠めて行く。
櫻井は、自分の暗視ゴーグルをひっつかんで相手に投げた。
相手がそれに気を取られている間に、櫻井は引き金を引く。ペイント弾は顔のど真ん中に命中した。鼻先でペイント弾が炸裂して、隊員が悲鳴を上げる。
櫻井が安堵したのもつかの間、暗闇から突然飛び出してきた最後の刺客が、櫻井を後ろから羽交い締めにした。
マシンガンを構える気配がしなかったので、気づくのに遅れた。
最後の隊員は、なかなかの切れ者らしい。
櫻井が、気づくのに遅れることを核心しての、あえての肉弾戦だった。
背後を取られてはペイント弾の銃口も、相手の急所は捉えられない。
例え相手の足や手を撃ったところで、試験にはパスしない。
確実に首根っこを捉えられており、意識が混濁していく。
首から上の皮膚が充血して、みるみるむくんでいく。
まるで本気で絞め殺される勢いだ。
櫻井は足をバタつかせたが、一向に相手の腕が緩む気配はない。
櫻井の手から、ハンドガンが滑り落ちる。
その様子をモニターで見ていた教官の一人が呟いた。
「さすがのゴールデンルーキーも、これで終わりですね」
榊は何も答えず、腕を胸の前で組んだ。
中央のモニターでは、ズルズルと身体が下がっていく櫻井の姿が映し出されている。
榊は溜息をついて、席を立った。
その時。
── ガシャン!!
大きな音が聞こえた。
ハッとして榊が振り返る。
なぜか中央のモニターだけが、真っ白くなっていた。
「何事だ、一体」
教官達も動揺する中、スピーカーの向こうから、『18分35秒、高橋、制圧』と櫻井の声がした。
状況は、以下のものだった。
背後を取られ首根っこを捕まえられた櫻井は、結局ハンドガンを捨て、意識を失いかけていると『演技』して、足下に転がる既に倒した隊員のマシンガンを手に取ると、それを建物の外側に向かって乱発射したのである。
その際、部屋の上部にあった暗幕で覆われているガラス窓に数発の弾が命中し、外の光が一気に中に射し込んだ。
闇に目が慣れていた櫻井もそのまぶしさに一瞬目が眩んだが、暗視ゴーグルをつけていた隊員は、完全に目がつぶれた状態に陥った。櫻井を掴んでいた両手で思わず自分の両目を覆ってしまった隊員は、次の瞬間最後のペイント弾でその両手の間を打ち抜かれていた。
結局櫻井は、二人の隊員を病院送りにし、その制圧時間は歴代最高タイムをマークしたのだった。
接続 act.01 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
皆様、お久しぶりです(汗)。
いや、シムズ日記を読んでいただいている方はとりわけお久しぶりではございませんが、小説の更新再開は本当に久しぶりで、国沢もかなり緊張の面持ちです。
これまで、やれ「検察官の話書いてる」だぁ、「リーマン・コメディ系にしようかなぁ」だぁ考えておった国沢ですが・・・。
おいおい、蓋開けてみると、『触覚』の続編じゃねぇか。
すみません・・・(汗)。ホント、移り気で・・・。
突如降りてきたものですから・・・。ネタが。
本気でもう随分小説をきちんと書いてないので、かなりリハビリ要素たっぷりなんですが、ぜひとも皆さんにお楽しみいただければなぁと思います。(大丈夫かなぁ???)
できる限り、頑張って定期更新に努めたいと思いますが、何分またもや見切り発車なので、定期更新ができるかどうかホント定かでないです!(←ふんぞり返って言うことか)
しかも、冒頭からお断りしておきますが、
ラブ度はまたもや
かなり薄い。
甘いお話には到底なり得ません。
すみません。
この二人なんで、もう仕方ないんです(汗)。
でも、たまに会う時はかなり砂糖ザリザリなほど甘くなると思うんで、許してください・・・。
で、お話は、『触覚』後、約一年という設定になっています。『触覚』自体が2000年の日本を部隊にしたお話でしたので、この『接続』も2001年のお話というちょっと浦島太郎チックな様相を呈しております。ま、だからといってさほど影響はないんですけどね(汗)。他の話との兼ね合いでそうなってます(うちのサイトはお話同士のリンクがよくあるんで・・・)。ということは、このお話もどこかの話とつながってるわけで(笑)。これだけ書いちゃうと、もうバレバレのような気もしますが(汗)、それはそれで楽しみにしていてください!
[国沢]
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
