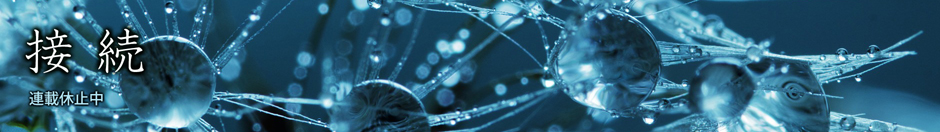
act.03
今日はお薬の日だった。
お薬のある日は、朝起きたら着替え服と一緒にお薬が入ってる注射器が置いてあって、皆自分でお腹に注射する。
お薬は、綺麗な透明の透き通った液体の注射だ。
多分、栄養剤なんだと僕らは思っている。
なぜかというと、そのお薬が切れかかってくると、段々身体がだるくなってきて、気持ちが重くなってくる。お薬を打つと、身体がしゃっきりして気分もすっきりするし、余計なことを考えなくてすむから。
皆、そのお薬の時間を待ちわびていた。
年を取っている人ほど、それを楽しみにしていた。
お薬は、僕らを幸せにしてくれる。
何も不安はないと安心させてくれる。
だから僕らが、一体どんな人間であるか悩む必要もない。
皆幸せで平等だから、名前すら知らなくてもいい。
お金を稼ぐ必要はないし、昼間する作業だって身体が鈍らないようにする簡単な運動なだけで、大変なことは何もないし、食べ物にも困らない。
ああ、僕らはこんなにも幸せだ。
他の世界の人達も、僕らみたいだといい。
左耳に填められたイヤホンに、『河田氏は五分後に出発する』と連絡が入った。
櫻井は袖口に仕掛けられたマイクに向かって「了解」と返事する。
視線を自分の横に立つ『同僚』に向けると、同僚の山田もまた同じ内容の通信を確認したのか、彼は軽く頷いた。それを合図に櫻井は非常階段に向かった。
民間警備サービス会社『セイフティ・ユニゾン』で最も新入りのボディガード要員である『高橋秀尋』は、新人であるが故に下っ端仕事をしなければならなかった。
素早い動きで五階から一階まで一気に駆け下り、クライアントが乗る車を表に回して安全を確保せねばならない。
黒塗りの車をビルの表玄関に止め車を降りると、櫻井は素早く周囲の様子をチェックした。
「── 異常なし」
櫻井がマイクに向かって報告すると、それを合図にふたりのボディーガード(SP ── セキュリティポリスは警察官にのみ使用される用語で、民間のそれとは区別される)に前後を守られた河田が自動ドアを潜って出てきた。櫻井が後部座席のドアを開けるとまず河田が乗り込み、続いて最も身近で河田を守っている沖というベテランのボディーガードが乗り込んだ。それに続き山田が助手席に座り、最後に櫻井が運転席に収まる。
「厚生省まで頼む・・・ああっと、厚生労働省になったんだけっけ? 今年の1月に」
何度も日本を離れてると、日本の世相に疎くなる・・・と苦笑混じりに河田はそう言ったが、既に行き先は櫻井の頭の中に入っていた。今日一日のスケジュールは前もって計画されていて、夕べの内に櫻井が道筋の安全を確認していた。
櫻井はスーツの胸ポケットに引っかけてあったサングラスをかけ、車を出した。
クライアントである河田昭治は、近年成長目覚ましい外資系の製薬会社『オゾッカ製薬』の日本支社長だった。
日本支社長と言っても彼は年の大半を海外で過ごし、特にここ一年間は東南アジアと日本の往復という生活を送っていた。
そんな彼が民間の警備会社に身辺警護を頼むようになったのも、ここ一年のことだ。
きっかけは、出張先のカンボジアで危うく誘拐されかかったためで、それ以来海外でも日本でもボディガードを従えるようになった。米国の本社としてみれば、幹部社員に誘拐保険をかけるよりボディガード代に予算を割いた方が遙かに安上がりだという計算だ。
河田の身辺警護は、公安特務員としての櫻井の初仕事だった。もっとも、初仕事といっても現在『仮免許』なので、お試し期間中であるのだが。
もちろん、セイフティ・ユニゾンには櫻井の本当の身分は知らされていない。
高橋秀尋という名の至極ありがちな偽の履歴書が、人事課のファイルに綴じられているはずだ。
そして今回与えられた任務は、ただの身辺警護ではなかった。
一刻も早く河田の側に近づき、河田が持っている違法な活動に関する情報を掴むことが求められていた。
もっとも、河田が本当に違法的活動を行っているのか、行っているとしてどんなことをしているのか、公安はまだまったく掴んでいなかった。
オゾッカ製薬は、CIAのブラックリストに載せられている企業だった。
この企業の近年の目覚ましい発展の裏には、新たな生物化学兵器の開発が関わっているのではないかという疑いがかけられていた。その兵器の開発に複数の日本人が関わっており、河田もその一人ではないかと目されているのである。
公安はこの一件に、公安部の中でも特に優秀な特務員の一人を当たらせているが、櫻井はそのサポートとなる仕事を与えられた格好になる。
課せられた任務は非常に重いものだったが、仮免期間中にこの任務を与えられたところを見ると、榊も櫻井にそこまでの成果を求めていないのだろう。
せいぜいルーキーにできることといえば、対象者の監視ぐらいのものだ。これで有効な情報がもし幸運にも得られれば、棚から何とやらということなんだろう。まずはルーキーのお手並み拝見ということか。
もちろん河田に対する貼り付け(張り込み)やプロフィール調査は、別の部員が三年前から当たっているが、これまで河田の側まで近づけなかったのが現状だった。
だから一年前に河田がボディガードを雇うことになったことが最大のチャンスを生んだのだが、公安はそこで一歩出遅れてしまった。榊は幾人かの特務員をセイフティ・ユニゾンに送り込んだのだが、既に河田はセイフティ・ユニゾン一優秀な沖というボディガードを専任として指名していた。それ以来、河田の側には沖しか近づけない状態が続いている。
この沖というボディガードはなかなか優秀な男で、シークレットサービスの本場アメリカでずっと働いていた経歴を持っていた。したがって公安にとっては不運なことに、沖には日本の警察組織との柵がまったくなかった。なので迂闊に捜査協力も申し入れられない訳で、結局、公安の特務員らは沖より『お気に入り』になることができず、有効な情報が得られぬまま今日まできてしまったというのが現状だ。
厚生労働省に到着しても、櫻井が同行できるのは打ち合わせのある部屋の入口までだった。
その日河田は、厚労省の事務方に挨拶しにきたらしい。
日本では製薬会社に睨みを効かせる役目を果たすのが厚労省なので、どんな小さな製薬会社でも厚労省への挨拶回りは怠らない。先日海外から戻った河田も、土産話を携えて挨拶に訪れたのだった。
櫻井が山田と共に木製の分厚いドアの前に立っていると、廊下の向こうから一塊りの人垣がまとまって移動してくるのが分かった。
今年1月の中央省庁再編に伴い、厚生省から厚生労働省に統合されて初めての大臣が、マスコミに囲まれながら登場したのだった。
すれ違い様、大臣についている警視庁警護部のSPが櫻井と山田を白けた目つきで眺めてきた。
櫻井自身、表向き警察組織を離れてみて思うことだが、警察組織に囲われている多くの人間が警察の仕事に酷似した職種に従事する民間人に出くわした時、些か格下に見る傾向が強いことが分かった。現に今もそうだ。
正確に言えば、櫻井は警察庁公安部外事第二課に所属する警察官であるのだが、彼らが櫻井の本当の正体を知るはずもない。
元々櫻井は、交番勤務から私服警察官になった時もずっと所轄の警察署に勤めてきており、本庁に直接の知り合いはいなかった。もしいたとしても櫻井は既に一年前『殉職』しているのだから、せいぜいよく似た男がいた・・・ぐらいにしか思われないであろう。
山田も、警視庁のSP連中の不快な視線に気が付いたらしい。大臣を中心とした喧噪が遠ざかるのを見ながら、面白くなさそうにチッと舌打ちをした。しかし、隣の新人がまるでそんな視線など気にならないといった風情で表情を崩さず立っているのを見ると、バツが悪そうに顔を顰めた。
「お前、気にならないのか」
「何がです?」
互いに前の壁を見たまま、会話した。
「── あいつらの目だよ。方々で会う度、こっちを馬鹿にしたような目で見やがって。クソが」
山田は相当腹に据えかねているらしい。山田は、沖と違って元機動隊所属の警察官だったそうだから、昔仲間だったはずの連中からそういう目で見られるのは、プライドが傷つけられるのだろう。
「相手にするだけ無駄です。仕事には何ら関係のないことですから」
櫻井がそう言うと、山田は「お前、新顔のくせに食えねぇやつだな」と捨てぜりふを吐いた。
山田にしてみれば、新人のくせして妙な度量の深さを感じさせる櫻井の存在が少し疎ましいのだろう。年齢は山田の方が三歳年上だったが、身体から滲み出てくる雰囲気は櫻井の方が遙かに落ちついていた。
もっとも、それも当然のことだ。
山田は知る由もないが、櫻井はこの一年間、米軍海兵隊員の訓練より苛酷と言われている公安特務員訓練を一年間みっちり続けてきたのであり、それ以前の一般警察官時代にも数々の際どい犯罪現場に遭遇してきた。修羅場の経験で言えば、山田のそれを軽く凌駕しているかもしれない。
『── 次の予定を急遽変更する』
ふいに左耳のイヤホンが鳴った。沖の声だ。
「変更? どういうことですか?」
山田がマイクに向かって声を荒げた。
『山田、声が大きい。文字通りの意味だ。次の予定をキャンセルして、城新大学に向かう』
城新大学と聞いて、櫻井の心はピクリと反応した。
── 香倉さんのいる大学だ・・・
三週間前、最終試験にパスして褒美にもらった休日に櫻井自身が訪れたことのある場所だった。
櫻井は、一旦外していたサングラスを再び掛ける。
二週間前にこの任務についた時点で髪を短く切っていたので、櫻井と香倉が知り合いであることを見抜く学生や助手が現れる可能性は少なかったが、万が一ということがある。
結局渋顔の山田を助手席に乗せて、予定変更のルートを走ることになった。
バックミラーに映る沖の顔も、機嫌が悪そうに見えた。
予定変更というのは守る側にとってしてみれば非常にやりずらく、神経を使わなければならなくなる。事前の安全確認ができていないし、万が一こういう時に襲われたりすると安全に退路を確保するのが困難になるからだ。
河田のこの動きは、長い間専属でついている沖にしてみても、初めて経験する動きらしい。
沖は努めて顔に出さないようにしていたが、沖の額に浮かんだ汗の粒が彼の戸惑いを表しているかのように見えた。
「── 君、城新大学までの道、知ってるんだな」
ふいに背後から、河田にそう声をかけられた。
河田に直接声を掛けられたのは初めてで、「は?」と櫻井は思わず聞き返してしまった。
山田と沖がちらりと櫻井を見たのが分かった。
「城新大学は郊外の新設校だから、一番の近道であるこの道を知っている人間は少ないと思ってね。君、新人なんだろう?」
「── はい、そうです」
「私について初めて行く場所だろうに、よく道を知ってるなぁ」
内心、櫻井はしまったと冷や汗を掻いた。
以前香倉を訪ねて行ったことがあるので、つい自然に車を走らせていた。
河田の口調は、特に櫻井を疑ってる節は見受けられなかったが、抜け目のない河田のことだ、心の中で何を思っているかは分からない。
櫻井は、自分が犯した初歩的ミスを呪いながらも、それを顔には全く出さす、こう答えた。
「自分は任務に就く前に、これまで沖が書いてきた日報を頭にたたき込んでおります」
沖が、再び櫻井をちらりと見た。
河田が、ほうと声を上げる。
「じゃ何か? 君は、日報に出てきた私が訪れたことのある場所への道全てを暗記しているということか?」
「この任務につく段階で車両の運転を任されることは分かっておりましたから、当然の下準備です」
実際のところ櫻井の頭の中には、沖の報告書以上の、三年間公安がため込んだ河田の行動データがインプットされていた。
今ここで仮に、河田が行きたいといった場所に地図なしで行ける自信はある。
河田の沈黙が怖かったが、河田が「前任の運転手さんはこうじゃなかったから、ちょっと驚いたよ」と言ったことで櫻井は胸を撫で下ろした。
どうやら前任の運転手とは、助手席の山田らしい。一瞬だが山田に物凄い目つきで睨まれた。
「── 君、名前はなんて言うの」
「高橋秀尋です」
櫻井は榊から貰った新たな名前を淀みなく口にしたが、まだ感覚的にその名前が身体に馴染んでいない感じがした。この名前を使い始めて一年になるが、まだ慣れない。名前を口にする度に少し胸がドキリと疼くのだ。それは、『秀尋』が愛する人の名だからなのだろうか・・・。
「年はいくつなの?」
「今年の末で30になります」
「なるほど、若く見えるな、君。だから余計に意外に感じるのかもしれないね。沖クン、なかなかいいの、入れたじゃないの」
河田は戯けた声で沖の肩を叩いた。
沖は、「ありがとうございます」と誇らしげな表情を浮かべ、それに答えた。沖も山田には物足りなさを感じていたのかもしれない。
河田からの初歩的な信頼を得たのと同時に山田からの憎悪も獲得したが、櫻井は努めてそれを考えないようにすることにした。
河田が突然予定を変えて向かった行き先は、城新大学の菅原教授の研究室だった。
現在香倉が内偵を進めている例の研究室である。
菅原教授は、植物学・・・主に分類学の権威で、特に新たに発見された植物をあまたある植物分類票に照らし合わせて、その植物にどんな由来があり、関連があるのか正確に突き止めることができた。
現在の植物学会で最も未知の領域にある場所は南米のアマゾン地区で、ついでアフリカ中部の密林地帯、最後にベトナム・カンボジア・ミャンマーの国境地帯に跨るジャングルと続いた。
上記二つの場所に関しては、純粋に研究が進んでいないための結果であったが、三番目の場所については政治的問題や『黄金の三角地帯』と呼ばれる闇の利害関係が絡んだ事情において一般人が容易に踏み込めない地域であり、そういう意味で『未知』にならざるを得ない地域であった。
菅原教授は、長年根気よくその地域への働きかけを続けている唯一の植物学者といってよかった。
彼の情熱は純粋に学問に対しての欲求からくるものであり、その他の利益に関して彼は、まったくもって無頓着だった。従って余計な賄賂などで汚れない彼は、次第に現地の人間にも受け入れられるようになった。そのお陰で近年、様々な柵を持つ人間がその事情を度外視して、教授の研究を手助けしてくれるようになった。それから以後、教授の手によっていくつか新種の植物が発見され、今まさに教授の苦労は報われつつあった。
また教授は植物の分類だけでなく、植物の有効利用に関する研究も同時に行っていた。
植物の有益な成分を、その植物に適した方法で抽出するやり方を思案することが、教授の何よりの楽しみだった。
教授が抽出した有効成分が新薬の開発に大いに貢献することも数多く、国内はおろか世界の製薬会社が教授の研究に興味を持っていた。
中には多額の研究費を寄付しようと持ちかける輩も多かったが、そういう下世話な話を嫌う彼は常に中立の立場にいることを望み、多少矛盾はするが、だからこそどの製薬会社も教授のことを信頼していた。
教授に新薬への協力を要請するには、常に教授の心を金以外の方法で揺り動かす必要があった。すべては教授の気分次第だった。けれど一度彼が協力をすると心に決めると、彼は心底熱心にそれに取り組んだ。
そのため、製薬会社は常に教授とのコネクションを密に取ろうと躍起になっており、教授が比較的捕まりやすい日本に帰国している場合は、皆挙って教授の元を訪れた。
河田もそんな中の一人だろうと、櫻井は単純に思った。
菅原教授の基礎情報は、この任務に就く時に一通り頭に入れていた。
その情報は、主に香倉によってもたらされたことを櫻井は考えたし、事実それは正しかった。
東條千尋と名を変えて、香倉が菅原教授の研究室にうまいこと潜り込んでまだ幾ばくも経っていなかったが、香倉は定期的に新しい情報を榊の元に寄越した。
河田が菅原教授の研究室を訪ねると、幸いなことに教授は在室していた。
どうやら厚労省を出る直前に、電話でアポイントをとっていたようだった。
まだ新設校らしい匂いがする廊下を進み、意外に質素な作りのクリーム色のドアを開けるなり、河田は親しげな声で「いやぁ、教授。お久しぶりでございます。見るからにお元気そうで何より・・・」と声をかけた。
そこでドアは閉められ、厚労省を訪れた時と同じように沖だけが付き添って中に入っていった。当然、山田と櫻井はドアの前で立ちんぼである。
時折、学生が二人の前を通り過ぎ、皆、興味津々な目を二人に向けた。
特に櫻井はサングラスをしたままだったので、さもボディーガードらしい雰囲気を醸し出していたためか、皆一様に山田をちらりと見た後はずっと櫻井の全身をくまなく観察していった。通り過ぎていく女子学生らの中には、あからさまに黄色い声を上げていく者も少なくなかった。
彼女達にしてみれば、軟弱気味な同級生より櫻井のようなタイプの男は数段男らしく見えるのだろう。しかも櫻井が、彼女達の熱い視線を受けても微動だにしない様が益々彼女達を沸き立たせていた。どこかフェミニンなタイプの男性が市民権を得てきた時代といっても、硬派な男は若い女の子達にもまだまだ根強い人気があるらしい。
山田は、明らかに自分の話題でないところで彼女達が盛り上がっているのを悟ると、面白くなさそうに小さく溜息をついたのだった。
櫻井のことを益々憎らしく思っているのかもしれなかった。
河田が菅原の部屋に入って十分ほど経過した時、廊下の端から性急な足跡が複数聞こえてきた。
櫻井がそちらに目をやると、その人物の顔に内心ドキリとした。
前を歩く男は、櫻井が見た資料によると利賀茂樹という助手で、菅原研究室の中で一番の年長者だった。だが、櫻井の心を揺らしたのは彼ではない。彼の後に続いてくる男・・・他でもない香倉裕人、その人だった。── いや、ここでは東條と名乗っている筈である。
些か慌て気味の利賀と違い、香倉はゆったりとした足取りで利賀の後をついてきていた。しかしそれでも香倉の歩幅は利賀よりずっと大きかったので、彼が利賀より遅れることはなかった。
香倉は、三週間前と同様に淡い色のポロシャツにチノパンという至極一般人的姿で、その上から白衣を羽織っている。銀縁眼鏡をかけたその学者的風情は、これまで櫻井が見てきた夜の世界に生きていた頃とは180度違う雰囲気で、容姿の端麗さは際だっているものの、それでも彼は一般人としてよく馴染んでいた。ここにいる学生達は、よもや彼の身体に立派な朱雀の刺青が入ってるなんて、露と思わないだろう。
櫻井は思わず香倉の姿に見入りそうになったが、慌てて自分を戒め、また前方の壁に目をやった。
利賀がどこか不安げな目つきで、ドアの両脇に立つ山田と櫻井をジロジロと見つめつつ、ノックする。
「お待たせいたしました、教授。利賀です。東條も連れてきました」
利賀がそう声を掛けると、「ああ、入りなさい」と中から菅原の大きな声が返ってきた。
利賀がドアを開ける。と同時に、中から声が漏れてきた。
「── 河田さんに紹介しておきたい男がいるんだ。去年うちに来た新しい助手の子でね・・・」
利賀が「失礼します」と中に入る。香倉もその後に続いた。
香倉が中に入り際、櫻井はちらりと香倉を見た。
一瞬だが、ふたりの視線が重なる。
ほんの一瞬だが、三週間ぶりの接触。
三週間前訪れた香倉のベッドで香っていたシャンプーの匂いが残り香となって、櫻井の鼻孔を擽った。
「── さっきの助手・・・」
山田がポツリと口にする。
今度こそ、櫻井の心臓が跳ね上がった。
「なんです?」
思わず櫻井は聞き返す。
── よもや、香倉が何者であるか感づいたのでは・・・? それとも、さっきの視線のやりとりを見抜かれたとでも?
櫻井は口の中が乾いていくのを感じたが、山田はこう言った。
「助手にしてはえらく姿形が整ったヤツだな。あんなのが大学にいたら、どんな女子大生だって選り取りみどりだぜ。皆、腰振ってついていくだろうさ。まったく、神様たぁ不公平に作ってやがる・・・」
山田はどちらかといえばこれと言った特徴のない容姿をしていた。
取り分け醜いわけでもなく、かといって優れているわけでもない。
名前は記憶に残ったとしても、顔が記憶に残らないタイプだ。
空気のように黒子に徹することが必要となる仕事なら、彼ほどの適任者はいない気がした。だが、相手を威圧する必要があるような仕事になると、彼は役不足だろう。
公安の特務員も、主にこの二つのパターンで与えられる職種が変わってくる。
相手に印象を残さないようなタイプの人間は、長期の潜入任務につくことが多く、一方香倉の様な容姿に特徴があるタイプの隊員の場合は、その容姿を利用する必要がある時に徴用されることが多かった。今回の場合、通常の採用シーズンと外れた時期に大学に潜り込む必要に迫られたので、菅原の妻を経由して潜入する作戦がとられた。その為、菅原の妻から好印象を得られやすいタイプの人間・・・しかも優れた情報収集能力と押し際と引き際の判断力に長けている香倉に白羽の矢が立ったという訳だ。
── 自分の場合、榊警視正から一体どんなタイプに振り分けられているのだろう・・・
櫻井は朧気にそう思った。
接続 act.03 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
視線だけで交わす愛。
いや~、エロいわ(笑)。
そういうのがエロいと思うの、国沢だけですか?
やはりそういうのに萌えるのって、妄想魔神のなせる技なのかもしれませんが(汗)。
先週、櫻井君とアニキの接触ありと書いたものの、会話すら交わさない接触となり、
「申し訳ございません」(ほんのり高島弟風味)←まだこれやってる。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
