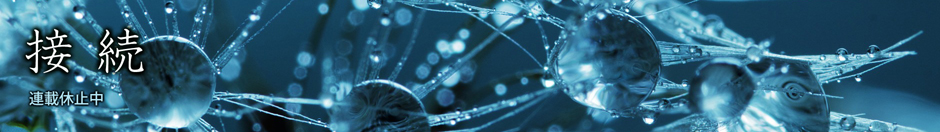
act.02
僕にはたくさんの仲間がいる。
小さな子どももいればおじさんみたいな人もいるけれど、ひとつの建物の中には大体同い年の仲間が集められている。
僕が寝起きしている場所には男しかいないけど、ふたつ向こうの建物には女の子だけのグループが同じように寝起きしているらしい。でも、作業をする時も寝る時も女のグループと顔を併せることはないので、本当に女のグループがあるかどうか、僕には分からない。
僕らは、淡いグリーンの長袖シャツに長ズボンを着ている。
その洋服はとてもきれいで汚れてなくて、朝起きた時にはもうみんなのベッドの横に新しいものが用意されていて、僕らは朝起きると真っ先にそれに着替える。
新しい服を着ると必ず鼻の奥がツンとする冷たい臭いがするけど、全部着替える頃には気にならなくなる。
僕らは同じ時間に起きて、服を着替えて、ご飯を食べて、作業をする。
その間中、白い人達がずっと僕たちを手助けしてくれる。
怪我や病気になったりしないよう、注意をはらってくれるのだ。
だから全く心配はない。
僕らが心配することは、何もないのだ。
井手がその男を馴染みのバーに呼び出したのは、久方ぶりのことだった。
男は先に店についていて、あの日と同じようにズブロッカを啜りながらカウンター席の片隅で井手が来るのを待っていた。
あの時と変わっているのは、男の髪が肩下まで伸びて無造作にゴムで縛られていることだ。
黒い上下のカジュアルなスーツに白いシャツ。ジャケットの胸ポケットには細い銀縁の眼鏡がぶら下がっている。取り分けアクセサリーもつけていない質素な格好の香倉だったが、それだけに彼の姿の良さが際だって見えるのだろう。ボックス席の数カ所に座っている女性同士の客らがチラチラと香倉の様子を伺っていたが、井手が香倉に近づくとあからさまに落胆した溜息をついた。
「久しぶり」
井手が声を掛けると、男 ── 香倉裕人はちらりと横目で井手を見た。
井手はバーテンにスロウジンを頼むと、香倉の隣に腰掛ける。
「一年振りね、この店で会うのは。・・・もう一年も経つのね、あれから」
香倉は再度チラリと井手を横目で見たが、特に何も答えず肩を竦めただけだった。
井手にしても香倉にしても『あのこと』に触れるのはこの日が初めてだったが、香倉が何も答えようとしないということは、香倉の中の傷はまだ癒えてないのかもしれないと井手は思った。
「元気? 新しい仕事の方は、順調?」
井手は、『あのこと』があった直後、組織が手配した精神科の病院に入院している香倉に秘密裏に面会しに行ったが、その時はまだまともな話ができなかった。心神喪失状態だった彼には物静かな時間と休息が必要だった。
そしてその後、個人的な知り合いでもある大石要から香倉が公安の特務員として再び現場に復帰したことを知った。現在の香倉の連絡先を教えてくれたのも大石だった。
大石は、例の事件で上層部に逆らう働きを犯して以来現在まで警察大学校教官という職でお茶を濁す状態らしいが、公安部の榊とは近しい関係らしい。どうやら例の一件における大石の行いを榊がいたく気に入ったらしいというまことしやかな噂もある。
「今度は、学者さんなんだって?」
井手が他の席に聞こえないほどの小さな声でそう言うと、香倉は怪訝そうに顔を顰めた。「なぜお前がそれを知ってるんだ」という顔つきだった。
今度は井手が肩を竦めると、「この情報はジジィから聞いたのよ。だからいいでしょ」と言った。
井手の言うジジィとは榊のことで、警察組織の連中が一睨みされただけで怖くて震え上がる榊を捕まえてジジィ呼ばわりするのは、井手ぐらいである。井手は極めて警察組織・・・しかも公安とも近しい関係にあるので、ある程度の情報を流して貰えるのだった。むろんその為、井手は警察から直接表立って頼み難い案件を頼まれることもある。確かに井手は民間人だったが、限りなく身内に近い民間人だった。
「── まったく、あのオヤジ・・・。公務員の機密情報をペラペラとしゃべりやがって・・・」
香倉はそう毒づいた。
井手も、香倉の口から「公務員の機密情報」なんて単語が出てきたので、思わず吹き出してしまった。
公安の特務員である香倉の場合、機密も機密、一般の国家公務員が責任を帯びている守秘義務を遙かに超える秘密を抱えている。世間では一般的に『スパイ』だなんて華々しい言葉で捉えられがちだが、その仕事の内容たるや非常に地味で地道な作業の連続である。しかもそのどれもが秘密裏に行わなければならないことなので、ストレスも多い。それでも努力して守っている『機密』が、上司の軽口でやすやすと漏れたのだから、内心面白くなくて当然だろう。しかし香倉も、榊がそんな香倉の心労を思って井手に香倉の今の状況を意図的に漏らしたことを薄々は感じているようだ。微かに口を尖らせたその表情が、テレ臭さを象徴しているように井手には見えた。榊は、香倉に『多少の秘密を共有しあえる友達』が必要であると踏んだのだ。さすが、痩せても枯れても香倉は公安のサラブレットである。榊は、大層香倉のことが可愛いらしい。
「で、なんて呼べばいいの?」
名前、また変わったんでしょ?という言う意味を込めて、井手は香倉を見つめた。
香倉はさりげなく周囲に視線をやって、特に誰も自分達に注目してないことを探った後、小さな声で「東條千博」と耳打ちした。
香倉が名前を変えるのはこれで三度目だった。
一度目は警察学校時代まで使っていた本名の小日向秀尋から結城和重へ。その名前で一年ぐらい海外での・・・特にアジアでの諜報活動に従事していたが、香港マフィアとの抗争事件に関わり、麻薬シンジケートを壊滅に追いやったきっかけとなる事件に荷担したせいでその名が使えなくなり、次に香倉裕人と名前を変えた。そして随分長い間その名前で東京の夜の世界に深く潜入し、大人しくほとぼりを醒ましていたのだが、一年前に発生した奇怪な連続猟奇殺人事件と偶然にも関わることとなって、また名前を変えざるを得ない状況に陥ったのだ。
香倉のことを中学時代から知っている井手にとってしてみれば、やはり本名である小日向秀尋が一番しっくり来るのだが、最近では香倉裕人を随分長い間使っていたので、そちらの方が違和感なく感じる。
だが新たな名前になれば、それで呼ばなければならない。
目の前の男は、そういう世界に生きている男だった。
「東條。・・・ふ~ん・・・なんだかピンとこないわね」
井手がそう呟くと、香倉の足に脹ら脛を軽く蹴られた。
「そんなくだらん話をしに、ここへ呼んだのか?」
どうやらぬるい会話に痺れが切れてきたらしい。
「はいはい。今日の本題は、それじゃありません」
井手はスロウジンをチビリと舐めると、一冊のノートをカバンから出してカウンターの上に置いた。
香倉が初めてまともに井手を見る。
井手は顎で、香倉に見るように促した。
そのノートは井手の診察ノートで、患者の個人情報はもちろん記載していないが、井手の受け持つ診察ケースの要点や問題点を箇条書きにしているメモである。通常カルテは家に持ち帰る事ができないので、外部に持ち出せる範囲内の情報をノートに書いて、家に持ち帰るのだ。
香倉が、ペラペラとページを捲る。そして最新の情報が書かれているページを探し当てた。
香倉の顔に、またも怪訝そうな色が浮かんだ。
メモにはこう書かれてある。
『密林の中の広場。
無数の仲間。
平屋建ての白い建物。
規則正しい配置。
白衣を着た人々。
無気力感。
漠然とした謎。
自分は、誰なのか。』
箇条書きにされた単語の下に、『忘れている過去の記憶?』と書かれ、その上に×印がされている。その下には更に『連帯記憶?』と書かれ、その隣に『今月までで8人目。皆、同じ症状』と書いてあった。
「どういうことだ?」
香倉がノートを閉じながら訊いてくる。
「私もさっぱりよ。だから意見を聞こうと思ってね」
井手はスロウジンをグイッと飲み干すと、バーテンにお代わりを頼んだ。
「始まりは三ヶ月前よ。他の精神科クリニックから、手に負えない患者がきたから、そちらで何とか面倒を見て欲しいとカルテが回ってきたの」
井手が務める坂出メンタルクリニックは業界内でも非常に有名で、時折同業者からのそういった相談を受けることは多々あることだった。
井手の元に回ってきたそのカルテには、毎夜同じ夢を見続ける患者について書かれてあった。
一見するとなんて事はない症例だったが、それが普通でなくなったのは、同じような夢を見続けている患者が他に八人も出てきたのだ。
先程香倉が見た箇条書きの言葉は、患者達の夢に共通する夢の情景だった。
「まったく同じ夢なのか?」
井手は頷いた。
「若干個人差はあるけれど。それは単なる視点の違いで、夢に出てくる建物や風景は同じよ。催眠療法で得た情報だから嘘はないと思うし、この八人が事前に示し合わせているとも思えない。第一、そんなことしたって何の得にもならないからね。別に保険金が出るという話でもないし、それに皆、不眠に悩まされているという訳でもない。ただ単に同じ夢を見続けているというだけだもの。何だか気になる・・・という程度よ。八人とも」
「薬物による幻覚ということはないのか?」
「そう。私もそう思ったの。だから今日、東條先生を呼んだんじゃないの」
香倉が顔を顰める。井手は、その疑問を表す香倉に畳みかけるように言葉を繋いだ。
「あんたんとこの教授様は、植物学の権威でしょ? 日本はおろか特に東南アジアの植物生態を専門としている。現在、精製されている麻薬の一大マーケットがあるのが北朝鮮と東南アジアよ。新種の植物から新たなタイプの薬が生み出されているケースも最も多い。教授は、世界的にもそのことに詳しい人だわ。だから何か知ってることはないかって思って」
「新種の薬?」
「そう。尿検査や血液検査でもまったく引っかからない、同じ幻覚を見るような新しいタイプの薬のね」
井手が一気にそう言うと、香倉は大きな溜息をついて席を立った。
「場所を変えよう」
井手が香倉に連れられてやってきた場所は、井手達が先程いた店とそう離れていない場所にあった。
徒歩で移動した二人は、コンクリート打ちっ放しの建物の真っ赤に塗られた鉄製のドアを徐に潜った。
ドアを開けると、大音量のトランスミュージックと中央フロアで若い男女が踊り狂う熱気が井手の身体を包んだ。
大声で話しかけない限り、とてもじゃないが香倉の耳には届きそうにない。
店内には激しく瞬くミラーボールと色とりどりのライトがくるくると高い天井を照らし出している。際どい格好をした若者達が、至る所で身体を密着させていた。おまけに、天井からは二つの大きなゲージがぶら下がっている。明らかに人が入れるサイズだが、今はそこに人の姿は見えなかった。
流石の井手も、この喧噪には目を白黒させた。
仕方なく井手は香倉の後を大人しく追う。
香倉はカウンターの中の若いバーテンに軽く会釈した。
小鼻の脇や唇の端に数々のピアスをぶら下げているその若いバーテンは、カウンターテーブルの下から彼を照らすライトグリーンの明かりの中で、興味深そうな妖しげな視線で井手を見つめてきた。井手が見つめ返すと彼はニヤッと笑い、店の奥の扉を丁寧に指し示した。
カウンターテーブルが壁に行き着くそのすぐ側に設けられた扉もまた鋼鉄製の赤いドアで、『プライベート オンリー』の札が貼られてある。しかもご丁寧にそこはナンバーキーとなっていて、番号を知る者しか出入りできない仕組みとなっているようだ。
井手がその鍵を見て、警視庁に取り付けられているナンバーキーと似てると思った矢先、香倉が慣れた手つきでキーを押した。
ガシャンと物々しい音がして、ドアが開く。
香倉と井手が連れ立って中にはいると、井手の背後で再び自動でドアの鍵が閉まる音がした。
ドア完全閉まると、割れんばかりの大音量は半減した。
井手の目の前には、地下に続く階段が伸びている。
「何よ、ここ」
井手が香倉の背中にそう訪ねると、香倉は少しだけ振り返り、ニヤッと笑って「秘密の隠れ家」と戯けて見せた。
今度は、井手が顔を顰める番である。
「そのいやらしい顔。さっきのバーテンにもそんな顔して見られたわ」
香倉は、階段を降りながらその謎に答えてくる。
「あいつも公安野郎さ。ここは俺らみたいな連中が憂さを晴らしたり、身を隠したりするのに使ってる場所のひとつだ。大方あいつも、俺が女を買って憂さ晴らしにきたとでも思ったんだろう」
井手が階段を降りる足を止める。
「ちょっと。それじゃさっきのアイツ、アタシを商売女だと思ったってこと?」
香倉はくるりと振り返り、ニッコリと微笑んだ。
「よかったな。若く見られて」
「── アイツ、後でぼっこぼこにしてやるわ」
長い地下への階段を降りきると、外の喧噪が全く聞こえなくなった。
階段の突き当たりにはまたひとつドアがあり、今度は赤では塗られておらず、鉛色のやたらと重いドアだった。
香倉がドアを開け電気をつけると、まるでワンルームマンションのような空間が広がっていた。
意外に広い。
まるでモデルルームのように、リビングとキッチン、何かの作業をするための書斎のようなゾーンと効率的に収納家具等で区切られており、一番奥のパーテーションに遮られた向こうにはきっとベッドがあるものと安易に想像させた。リビング部分には飴色の革張りのソファーやテレビもあるし、書斎のデスクには電話機もある。キッチンには二人がけの小さなダイニングテーブルと大きな冷蔵庫、コンロの上には煙を吸い込むフードも完備されていた。さすがに地下なので窓は一切ないが、潜伏生活をするにはそちらの方がおあつらえ向きである。窓がないから覗かれる心配もない。
井手がバックにぶら下げている携帯を見ると、アンテナが圏外となっていた。
この分だと、外からの盗聴電波も届かないだろう。
なるほど、内緒話には適しているといった具合だ。
井手は室内をぐるりと見回して、あることに気が付いた。
「ここの家具、見覚えがあるものがあるわ」
空間を仕切っている本棚やソファー、テレビもどこかで見たことがあるものだった。
「これってひょっとして・・・・」
井手がそう呟くと、香倉が「やっぱり気づいたか。流石だな」と井手をちゃかした。
「一年前まで使っていたものをそう易々と忘れる筈がないでしょう? まだそこまで耄碌してないわよ」
確かにその場にある殆どの家具は、かつて井手が居候していた香倉のマンションにあった備品ばかりだった。特に、リビングにある飴色のソファーは間違えようがない。井手が零したコーヒーのシミもそのままだ。
「特務員が任務で使っていた備品は全て倉庫に保管されてある。任務にあわせて身分相応のものをレンタルしていくって訳だ。どこのお役所も、経費節減の波を食らってるからな」
香倉は冷蔵庫から小さな瓶入りのスタウトビールを取り出すと蓋を開けて、一本を井手に差し出した。井手は面白くないと行った様子でぐびりとビールを飲む。
「まさか、こんなところで使われてるとはね。よかった、ベッドは自分で買っといて。さもないと、私が使ってたベッド、どっかの公務員の憂さ晴らしに危うく再利用されるところだった」
幸い、井手が使っていたベッドは元々井手が個人で購入していたベッドなので、公安の連中があの部屋を引き払う前に井手の新居に移されていて、今も彼女はそのベッドを使っている。
二人は懐かしい座り心地のソファーに腰掛けると、早速本題に入った。
「実のところ、厚労省のお役人にも訊いてみたのよ。最近、新手の薬は出回ってないかってね」
「へぇ。誰に訊いた?」
「葛谷」
「── あいつか」
葛谷一臣は麻薬捜査官だった。香倉も仕事上の付き合いがあって、知っている。
麻薬捜査官は、厚生労働省の管轄で正確には警察官とは違う。だが彼らは警察官と同じ権限を有しており、さらに表だって警察では許されていない『おとり捜査』も行える権限を持っていた。
葛谷一臣は、いわゆるそのおとり捜査のベテランであり、ゆえに公安の特務員とは方々で顔を併せていた。むろん、協力関係の時もあれば非協力関係の時もある。よって、現場レベルはおろか、幹部レベルでも公安と麻薬捜査部はよく衝突している。
「確かに数日前、葛谷から俺の元に探りが入ったな」
「本当?」
「ああ」
「どんな風に?」
「最近、新手の薬は出回ってないかってね」
香倉は、井手が言った台詞をそのまま繰り返した。井手が「なによ、それ」と吹き出す。
「恐らく、麻薬捜査部も寝耳に水の話だったんだろう。新手のヤクの話なんかな。俺が今張り付いている先生は、お前が言った通り、そっちに関する植物学でも権威であらせられるから、新しいヤツが出たとなると一番にその情報を握っているとふんだんだろう。── だが、残念ながらそんな話はないね。現在問題になってるのは、教授が考えた植物エキスの高度な抽出技術がとある製薬会社に違法に流れたのではないかということで、麻薬のことに関してうちはノータッチだ」
井手は、ぎょっとして香倉を見た。
「植物エキスの抽出技術? そんなネタで公安が動いてるの? どうして?」
「米国に本社を置くその製薬会社が、生物化学兵器の開発の一端を担っていると疑われてるからヤバイんだ。奴らは近年東南アジアに生産拠点を着実に広げている。うちはこの情報を、CIAからもたらされた。やっこさん達は、自分のお膝元でそんな危なっかしいものが秘密裏に生産されようとしていることに大変な嫌悪感を感じている。うちはその製薬会社の真意を追究することでも、CIAから捜査協力を依頼されてる立場でね」
井手はそう聞かされて、ああと溜息をつき、ソファーに身を凭れさせた。
確かに、テロの拡散が叫ばれている昨今、そんな物騒なものに日本で生まれた技術が利用されているとあっては、国家的に『ヤバイ』ことになる。日本の警察もアメリカ政府からの圧力があるとなれば、のんびりはしておれない。だからこそ、菅原研究室への潜入が急務となった訳である。
「── 新手のヤクだとか言ってる場合じゃないわね」
井手が肩を竦めると、香倉はその肩を軽く叩いてビールを飲み干し、席を立った。
「でもまぁ、気にはかけておく。現に菅原教授の元には世界中から新しい薬物に使われた植物特定に関する捜査に協力してほしいと依頼が来る事もある。菅原教授は俺が見るところ、黒い人物ではない。新手の麻薬精製に役立つ植物の発見となれば、すぐに警察に働きかけをするだろう。お前にしろ、葛谷にしろ、着眼点は間違ってはいない」
香倉は、空瓶をキッチンのダストボックスに放り込むと新たな一本を取り出して、キッチンに凭れながらそれに口をつけた。
「それにしても、奇妙な話だな」
「何が?」
「お前の患者の話だよ。八人に共通点はないのか?」
井手は首に振った。
「特にないわね。性別も偏りがないし、生活習慣もバラバラ。強いて上げれば、皆ある程度裕福であることぐらいね」
「病歴は?」
「精神科については、皆今回の件で初めて利用してる。過去の精神疾患はないわ。その代わり、皆何かしらの病歴は持ってたわね。もちろん、体の部分でよ。でも、皆ある程度の年齢だから、病気のひとつやふたつはしててもおかしくはないでしょ?」
「同じ病気ということは?」
「それはない。私も身体的病名にあまり詳しくないから分からないけど、臓器の違いぐらい分かる」
「同じ病院とか?」
「それもないわ。皆、別々の病院に通っている」
香倉はふ~ん・・・と鼻を鳴らすと、「麻薬がらみじゃないんなら、人間の身体に幻覚を起こす要因があるとすれば医療関連だけだ。そこで何かしらの共通点がないのであれば、この一件、非科学的な話になりかねん。それはお前だって望んじゃいない結果だろ?」と続けた。
井手もそれを受けて肩を竦める。
「幽霊が関係してます、だなんて精神科医は言えないもの」
香倉は意地悪そうな笑みを浮かべた。
「幽霊の仕業にしたくないんなら、その病歴とやらをきちんと調べてみるんだな。一見共通点がなにもないように見えて、視点を変えてみたら途端にそれが現れてきた、だなんてよくある話だ」
そう言うと香倉はビールを一気に飲み干し、ダストボックスに瓶を上手に投げ入れた。
接続 act.02 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
久々のアニキ登場でした。
時間軸でいうと『触覚』の番外編『日々』の直後の頃なので、アニキ、ロン毛ですわ。
そしてメガネ持ち(笑)。
今回のアニキは、エグゼクティブではございませんが、インテリジェンスな感じでございます。つってもしがない助手だけど(笑)。
しっかしまー、この話ホントにモーホースキーな香りが全くないですな(青)。
これでいいのかと書いてる方も不安になってきました。
『触覚』好きの読者の方々は、少々ラブ度が少なくったってついてきてくださるのは分かっておりますが、へたすりゃ『触覚』よりラブ度が僅かな気がしてなりません(汗)。
なんか・・・国沢、萌えどころ、皆とずれてないか?
大丈夫だよね?
・・・。
不安はぬぐえませんが、はじめちまったものは仕方ない。
突き進むのみっす。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
