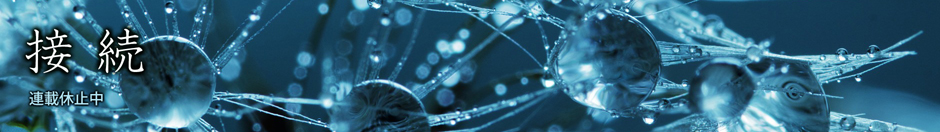
act.04
── 見るからに胡散臭い男だ。
オゾッカ製薬の河田という男に対する香倉の第一印象はそれだった。
自分を河田に紹介する時の菅原教授の様子を見ると、教授は助手が現れてくれたことにより、一人で河田を相手にする必要がなくなったことに安堵しているようだった。元来、菅原はあらゆるおべっかを使ってくるタイプの人間が苦手なようだった。
香倉はそんな思いをお首にも出さず、最高の笑顔で河田が差し出してきた手を握り返した。
「初めまして、東條と言います。年は食ってますが、一番の下っ端ですので、今後いろいろ勉強させてください」
「いやぁ、爽やかだなぁ。こんなハンサムな助手さんに初めて会いましたよ」
河田も白い歯を見せながらそう言う。
菅原は再びソファーに座り直しながらも、「いや、この子は姿だけじゃないよ。非常に優秀な男なんだ。初めは家内に雇ってやってくれと頼まれて渋々だったんだが、今となっては、こっちが彼に頼り切りなんだ」と言った。河田も同じようにまた腰を下ろしながら、「ほう」と相づちを打つ。
菅原は傍らに立つ利賀と香倉に、「君らも座りなさい」と促した。
利賀は空いていたシングルソファーに座り、香倉は部屋の片隅に立て掛けてあるパイプ椅子を広げて座った。
「実は、先月カナダに利賀君と行っている間に授業を持ってくれたのが彼なんだ。帰ってきてみたら、いつも以上にレポートの提出率が高くて、逆にこっちが閉口したほどだよ」
菅原はそう言って笑った。
「すると、助手になって一年足らずで早くも授業を受け持たれたんですか?」
河田も感心した表情で香倉を見つめてきた。香倉は肩を竦めると、「前もって教授が準備していた内容を黒板に書き付けていただけですよ。伝言係のようなものです」と答えた。
「だが、それにしても・・・。他の助手の人達から、嫉妬されて大変なんじゃないかな?」
河田が顔を顰めると、菅原は首を横に振った。
「助手の連中は、授業など面倒くさいものだと思っているものですよ。できれば自分の研究に没頭したい。むしろ、新人ながら十分に授業の代役をする人間が現れたので、彼らは喜んでいるんじゃないかな? どうだね、利賀君」
話題を振られた利賀は、大きく頷いた。
「そうですね。僕も彼のお陰で手が放れたことが沢山ありますから・・・。助かってます」
「そうか、それはよかったな、利賀君」
河田が、左斜めに座る利賀の膝をポンポンと二回叩く。
利賀は一瞬河田の手元をまじまじと見つめ、次にテレ隠しのような笑みを浮かべ、軽く後頭部を掻いた。
── おや? と、香倉は思う。
利賀は香倉より一つ年上だったが、大学で見る限り非常に内向的な人物で、他の助手からもちょっと変わり者であるとのレッテルを貼られていた。
取り分け後輩の面倒見が悪いということはなかったが、それ以上のことは全く付き合う素振りを見せなかったので研究室では孤立していた。大学の同僚のうち、彼が一体何を好んでいて、どういう趣味をし、どんな風に生活しているか知る者は皆無だった。
その利賀が一瞬浮かべた親しみのある表情は、香倉も初めて見るものだった。
どうやら利賀と河田は、意外とウマが合うらしい。
── それとも・・・別の繋がりでもあるのか?
それは、香倉の意識が利賀に移った瞬間だった。
これまで調べた所によると、オゾッカ製薬会社と菅原教授の繋がりは、意外にも気薄なものだった。
香倉が研究室に入ってから約一年、河田が菅原の元を訪れたのは今回で六度目であり、二ヶ月に一回の割合だ。一ヶ月単位や酷いのになると一週間ごとに・・・なんていう、もっとマメに教授の元を訪れる製薬会社は他にごまんといた。
CIAからの情報では、オゾッカ製薬会社が得たと見られる植物エキス抽出技術は、米国のいかなる大学でも確立されていない斬新な方法だったし、ヨーロッパにおいてもそれは同様だった。
となると、オゾッカが関連している残りの地域は東南アジアで、その地域一帯に関連している研究者は、地元の大学の人間か菅原教授のみだった。
CIAは、まだ確かな全体像を掴んでいないその高度な技術を開発するには、高価な研究費と設備を有する菅原研究室が最も可能であると判断したのである。
香倉が教授の性格を把握して、教授が完璧に『白』であると結論づけたのがつい三ヶ月前(それほど時間がかかったのは、教授の海外出張が余りにも頻繁だったためである)、それ以後は教授以外の他の要因で抽出技術がオゾックに漏れた可能性を模索していた。
歯がゆいほど手がかりは少なく、なるだけもっと深い情報に触れる地位につけるよう努力する必要があった。
その為に香倉は、他の助手達に負けない知識を身に付ける必要があったし、大学での下っ端仕事以外の時間は、努めて植物学とは何たるかということを注意深く学んでいった。それは溜息をしたりないほど根気のいる作業だったし、精神的にも肉体的にもキツイ仕事だった。
潜入捜査を生業としている特務員は、任務についてある一定の時期を過ぎても大きな成果を上げられない時、自分のしている行いが果たして本当に役に立つのだろうか・・・という漠然とした不安に襲われ始めるものである。
他でもないこの香倉も、表向きは榊に対しても落ちついた態度を示していたが、内心モチベーションに陰りが差し掛けている最中であった。
それだけに、今利賀が見せた一瞬の綻びは、香倉にとって新たな、そして大きな光明だった。
これまで当然、他の助手達のことも調べつくしていた。
菅原教授の研究室は、多くの助手や研究生を抱えていた。
植物の分類という作業は、標本の作製やこれまでの膨大な資料との比較作業などについやされることが大部分で、やることは単純であったがたくさんの手間と時間がかかる作業であった。しかしこの地道な作業が全ての基本にあたることなので、それなくしては全ては始まらないのだった。
そうなると当然、人手がいる。
大学側は教授の求めるままに、人員を受け入れた。
菅原教授は、新設校である城新大学の中でも『目玉商品』だった。
城新大学では、菅原教授以外にはまだ世間的に注目される研究成果を発表できる教授は育っていなかった。
新しい大学が生き残っていくためにはスター選手が必要であり、大学側は破格の条件で菅原教授を国立の最高学府と呼ばれる大学から引き抜いてきたのである。
袖の下に興味のない教授であったが、正規の形で支給される研究費については、多ければ多いほど良しとした。その点で菅原教授は貪欲だった。それに何より教授にとって魅力的だったのは、教授の所有する膨大な植物に関する資料を身近に置くことができる巨大な保管室を大学内に構えて貰えることだった。その保管庫は、完璧に湿度と温度を管理することができる部屋で、全国的に見ても最大級の規模だと言えた。
そういった事情で、教授の研究室はいつも盛況だった。
様々なタイプの助手や研究生が教授の庇護下で研究を進めており、中には一般企業からの出向組もいた。助手達はいつも熱心に教授の仕事を手伝い、教授が海外に出張しがちでも教授の求めている植物の分類作業が滞ることはなかった。
香倉が容易に研究室に潜り込めたのも、教授の研究室が簡単に人員を増やすことができたお陰でもある。
助手や研究生、ゼミ生の中で疑わしい人物は何人かいたが、残念ながらこれまで、どれも不発で終わっていた。
当初利賀も、一番教授に近しい人物だったため疑われたのだが、彼は余りにも内向的過ぎて、香倉が分かる範囲での彼の生活は質素極まりないものだった。
彼の両親は既に他界しており、親戚との付き合いもない。独身で、現在つきあっている異性の影もなく、友達らしき人間もいない。住んでいるのは築十五年の学生向け安アパートで、後輩の助手達の方がよっぽどいいところに住んでいた。酒も飲まず、博打もせず、自分の研究に関する機器やパソコン以外は散財している様子がまったくない。
あの抽出技術をオゾッカに売ったとなれば、それ相当の対価が得られたであろうし、技術を『盗み出す』ような人間であれば、特別で法外な報酬を得られたとすると、自然と生活も派手になっていくはずである。だからこそ利賀は、香倉の頭の中のブラックリストから当初外されていた人物だったのだが。
── どうやら俺のよみは甘かったらしい。
なおも河田と利賀が、とりとめがないとはいえ、意外なほどの和やかさで会話しているのを見て、香倉の腹は決まった。
香倉は会話に合わせ笑顔を浮かべながら、それでも極めて冷静な瞳で利賀の横顔を見つめた。
河田と菅原教授の面会は、約1時間程度のものだった。
沖に「車をまわしてきてくれ」と無線で指示され、櫻井は教授の部屋がある研究棟を出た。
一般来客用の駐車場に向かいながら、櫻井は車のキーを取り出す為にジャケットのポケットに手を突っ込んだ。
一瞬鍵を引き出そうとした手が止まる。
指先に、鍵の感触と違う別のものが触れたのだった。
「?」
── 朝、このポケットには鍵しか入れてなかったはずだが・・・。
櫻井がそれを取り出すと、それは二つ折りにされた小さなメモ用紙だった。
櫻井は何気に周囲を見回しながら、そのメモを広げる。
『クラブ・マシャド』
初めて見る店の名前と、その店の住所らしき番地が書かれてある。
櫻井はその筆跡が誰か一瞬で思い当たり、パッとメモを閉じた。そしてもう一度念入りに周囲を見渡す。特に誰に見られている訳でもなかったが、櫻井は慌ててメモをポケットに突っ込んで、車まで走った。
少々慌て気味に車を研究棟まで回し、沖にその報告をした。
櫻井は努めて平静を装ったが、ドクドクと胸は高鳴っていた。
メモが突っ込まれたポケット辺りが、なぜかじんわりと温かく感じるのは気のせいだろうか。
河田が下りてくる間、櫻井はついさっきのメモに書き付けられていた文字を頭の中で反復した。
あれは間違いなく香倉の字だった。
おそらく、香倉が菅原教授の部屋に入るあの一瞬にメモを櫻井のポケットに差し込んだのだろう。
あれほど訓練を積んだ櫻井でさえも、香倉の動きには気が付かなかった。
何故か訳も分からず頬に朱がさすのを感じて、櫻井は焦った。
だが丁度その時沖が建物の出入り口から出てきたので、櫻井はパンパンと顔を叩いて車を出、後部座席のドアを開けたのだった。
小高い丘の上に建つ大学を背に、緩やかな坂になった道路を車はスムーズに下っていった。
急な予定変更だったが、何事もなく済んでよかった・・・とボディーガードの三人が内心そう思っていた時である。
対向車線を走っていた大型のRV車が突如櫻井達の車の前で方向転換した。
ギュイギュイとタイヤが擦れる派手な音がして、RV車が行く手を塞ぐ。
沖が後部座席を振り返ると同時に櫻井もミラーで後方を確認すると、同型のRV車に櫻井達の車は挟み撃ちにされていた。
この道は大学へ繋がる一本道で、午後の中途半端なこの時間帯は交通量が極端に少なかった。
アクセルをふかして強行突破するには相手の車は大きく、無事に通過できるとは思えなかった。
櫻井は、反射的にブレーキを踏む。
「高橋、止まるな!!」
山田が怒鳴る。
「いや、突破は無理だ!」
沖がそう叫び、無線で本社に応援を要請する。
バックミラーの中で河田の怯えきった顔が見えた。
前の車から目だし帽を被った男が二人出てきた。一人はサブマシンガンを片手に持っており、もう一人は軍仕様の棍棒を握った大男だった。
後ろの車からは誰も出てこない。
相手は少人数だ。
「自分が出たら鍵を掛けてください。この車は防弾車です。車の中にいる限り安全です」
櫻井はそう言い残すと、運転席と助手席の間に挟んである薄手のアタッシュケースを手に取って車外に出た。
その耳に、河田の「銃相手にどうするつもりだ!!」という悲鳴じみた声が聞こえた。しかし山田は櫻井の言った通り、すぐさま内側から鍵をかける。
相手がサブマシンガンを構え切る前に、櫻井は男達と車の間に出た。
相手が撃つタイミングに合わせて、アタッシュケースを身体の前に掲げ、楯にする。
アタッシュケースには鋼鉄の板が入っており、暴漢の攻撃を阻むための小道具だった。
タタタタタと小刻みな音がして、数発の弾丸がアタッシュケースに当たる衝撃が櫻井を襲う。
アスファルトに当たって弾けた跳弾が、櫻井の頬をかすった。
相手が櫻井の行動に怯んだ隙に、櫻井は猛ダッシュする。
背後でドアが素早く開閉する音がした。おそらく、沖も車外に出てきたのだろう。
櫻井はダッシュした勢いをアタッシュケースに込め、そのまま振りかぶって五キロもあるそれをマシンガンを持つ男に向かって思い切り投げつけた。まるで陸上の円盤投げをする選手のように。
ギュンギュンと唸りを立てて水平に飛んでいったアタッシュケースは、暴漢が行く手を阻もうとマシンガンで攻撃したにも関わらず一向に進路を変えることもなく、そのままマシンガンの男を銃ごと後ろへ吹き飛ばした。
男は、カハッと声にならない声を上げたまま、動かなくなった。
しかし櫻井に気を許せる暇はなかった。
次の瞬間には、櫻井の頭上から太い棍棒がヒュンという音を立てて振り下ろされるところだった。
櫻井は、持ち前の反射神経で身体を反り返らせる。
鼻先数センチのところを棍棒の切っ先が掠め通った。
棍棒が巻き起こす風圧が、櫻井の頬を擽る。
「高橋! 警棒!!」
背後から沖の怒鳴り声が聞こえた。
櫻井は咄嗟にそのままバック転すると、沖が放り投げてきた伸縮式の特殊警棒を空中でキャッチした。
櫻井は、膝をついて何とかバランスを崩さず着地し、ひと振りで警棒を伸ばした。
と同時に大男が再び棍棒を振り下ろしてくる。
ギンッと耳障りな音がして、金属が当たりあう音がした。
すんでの所で、櫻井は男の攻撃を警棒で食い止めていた。
男は物凄い力で櫻井を上から押し込んでくる。流石の櫻井も、完全に力負けしていた。
「高橋、堪えろ!」
沖が新たな警棒を手に、走ってくる足音がする。
その時、大男と目だし帽越し視線があった。
その余りにも冷静な大男の両目に、櫻井はふと違和感を感じる。
── なんだ・・・? こいつ・・・。
櫻井が怪訝そうに眉間を顰めた瞬間、男は突然身を引いた。
沖が二人のいる場所まで到達する前に、男は意外なほどの身軽さで車まで引き下がると、道路で大の字になっている仲間とその仲間をノックアウトしたアタッシュケース、サブマシンガンなどを纏めて抱えて、車に乗り込んだ。それにあわせて、運転席から出てきていた第三の男も、何やら細々したモノを拾い集めて、大男と同時に車に乗り込んだ。
そしてあっという間にRV車はその場から走り去っていった。気づけば、背後の車も同様に別の方向に走り去っていったのだった。
櫻井は大きく息を吐き出すと、その場に跪いた。
余りにも突然の実戦だったので、少々身体が驚いていた。
自分はまだまだ未熟だな・・・と櫻井は思いながら、僅かに震える太股の筋肉を服の上から手で押さえ込んだ。
「おい、大丈夫か?!」
沖が櫻井を覗き込んでくる。
「── ええ、大丈夫です」
櫻井がそう答えると、沖は懐からハンカチを取り出した。
「頬、血が出てるぞ」
「すみません」
櫻井は遠慮なくハンカチを受け取って、今更ながらジンジンと熱く疼きだした右頬にそれを押しつけた。
「相手、どんなヤツか見えたか」
「いいえ・・・。目だし帽でまるっきり・・・」
櫻井はそう言いながら立ち上がり、車の方を返り見た。
櫻井は、先程の襲撃に漠然とした疑問を感じていた。
── やっぱり、窓に銃痕がない。
車は、フロントガラスどころか、車体のどこにも銃創を受けていなかった。
相手はまるで、櫻井の構えたアタッシュケースのみを狙って撃ったかのようだ。
櫻井は益々眉間に皺を寄せた。
── なんだこれは・・・。こんなのおかしい。これじゃまるで・・・
「おい! 君! 大丈夫か!!」
車中からの河田の声のせいで、櫻井の思考は止まった。
「河田さん! 安全が完全に確保されるまで窓から顔を出さないでください!」
沖が怒鳴る。
遠くで、数台のパトカーのサイレンがまるでコーラスしているように鳴り響くのが聞こえた。
接続 act.04 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
今年、母に代わりおさんどんをしている国沢です(汗)
。なので、激しく正月気分のない国沢です(涙)。いきなりおせち料理はできません。すみません。
しかしあれですね。
国沢、今回の母の怪我・入院で、意外な自分の新たな一面を知りました。
どうやら国沢、家事と仕事の両立ができないタイプらしい・・・(力汗)。
年末から実務の仕事も幾ばくか残してしまっていた国沢なんですが、家事をやってるとまったくもって仕事のスイッチが入らず、もうすぐ仕事始めだというのに仕事をする気分になりません・・・(脂汗)。
完全に仕事の両腕がもがれた状態・・・。
まさか自分が、一つのことしかできない不器用さんだったなんて。
もし、万が一、まかりなりにも国沢、結婚することがあれば、間違いなく専業主婦になります!ワタシ!!
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
