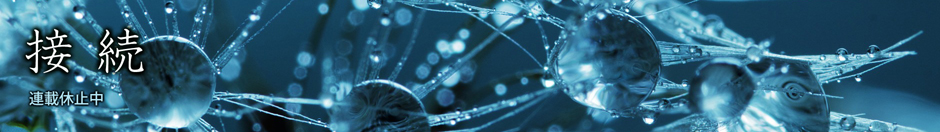
act.12
櫻井は、何気なく辺りをうろつくような仕草をしながら、気配を感じる方向へ足を進めた。
そしてすぐに違和感を感じた。
気配の相手は、櫻井が近づいてくるのを見ていながら、相手は全く動こうとしない。
櫻井は、思わず眉間にしわを寄せる。
相手だって、櫻井が自分の方に近づいてくることを明らかに分かっているはずだ。
いや、それとも櫻井の思いし越しで、本当にズブの素人なのか・・・?
櫻井は、一気に間合いを詰めて、建物の陰に佇んでいた気配の主をつかもうとした。
しかし相手もやはり素人ではなかった。
櫻井の腕をはねつけたばかりか、逆に櫻井の腕が取られた。
相手の穏やかな、でも抗いようのない動きで、櫻井の身体をひっくり返そうとする。
この動きは、明らかに有段者だ。
柔道というよりは、合気道の動き。
櫻井はとっさに宙で身体を反転させ身体を跳ねさせると、意表をつかれた相手の手から逃れて、地面に片膝をついた。
それは一瞬の出来事だったが、その驚きと突発的な衝撃が櫻井の体力と精神力をあっという間に消耗させていた。
櫻井が肩で息をしながら顔を上げると、闇の中に紛れる相手の気配の雰囲気がまるで変わっていることに気がついた。
まるで殺気がなくなっていた。
櫻井は、怪訝そうに顔をしかめながら立ち上がる。同時に闇の中から「クックック」と押し殺した笑い声が聞こえてきた。
「お前さん、相変わらずだな」
その声に聞き覚えがあった。櫻井も、ようやく身体から力を抜く。
「── 阿部さん」
櫻井は顔をほころばせた。闇の中から、相変わらずくたびれた背広とコートを羽織った無精髭の男が出てきた。
「俺の予言は見事的中したって訳だな」
阿部はそう言いながら、ニヤニヤと笑った。
阿部は、一年前の事件で櫻井と姉が対峙したその場に居合わせていた公安の特務員だった。
彼は姉からの銃弾を受けたが、幸い防弾チョッキの上からであったので大事には至らなかった。
そういえばあの時、櫻井の運動能力に目を見張った阿部が「公安に再就職したらどうだ」と言っていたことが現実になっていることに、櫻井は初めて気がついたのだった。
櫻井は、テレくさそうに少し笑う。
「お久しぶりです」
「ま、俺の気配を察しただけでも新人としては合格だな」
阿部はそう言いながら櫻井の肩をポンと叩く。
櫻井は内心、阿部がわざと『適度な気配』を漂わせていたことを思いながらも、あえてそれを口にせず素直に「ありがとうございます」と答えた。阿部が櫻井に対して『適度な気配』を放ちながら接してくるのもこれで二度目のことだ。あの時の夜もそうだった。
けれど、こうして櫻井自身、阿部と同じ公安の特務員となった今、阿部ほどのベテランになれば尾行対象に一切気取られることなくできることは、訓練中に思い知らされている。
「今日はどうされたんですか?」
櫻井は改めて周囲に誰もいないことを確認しつつ、阿部に効いた。阿部は肩を竦めると、「サラブレットからのリクエストでな」と答える。
── サラブレット・・・。
阿部がそう呼ぶ人間は、むろん香倉のことだ。
「そうなんですか?」
櫻井が驚いて返すと、阿部は新しいタバコに火をつけながら、
「奴の同僚の動きが怪しいとの報告を受けてな。アイツが尾行するのは面が割れていて目立ち過ぎるから、丁度暇こいてた俺に白羽の矢が立ったって訳だ。確かにサラブレットが言うように、十二分に怪しい奴だよ。安月給のはずなのに高級料亭に入っていくなんてな。しかも裏口から」
とボゾボゾ呟く。
櫻井はそれを聞いてハッとする。
「自分は今、オ・・・」
そこまで言いかけて、阿部に口を押さえられた。
「ああ、みなまで言わなくったって分かってる。俺たちのような奴が外で会話を交わす時は、完全に安全が確保されてない限り、易々と対象のことを口に出すべきではない」
「すみません」
櫻井は即座に頭を下げる。阿部はまた肩を竦めた。
「ま、あんたは元々表の業界にいたし、慣れないのは分かるがな」
櫻井が悔しそうに唇を噛みしめると、阿部はニヤニヤ笑いながら肩をぽんと叩いてきた。
阿部が耳打ちをする。
「お前の言いたいことはよく分かる。俺も、その可能性は高いと思うね。この目で見た訳じゃないから確定とは言えないが、ほぼつながったな。サラブレットとお前さんのお手柄だ」
「今後、自分はどうすれば・・・」
間近の阿倍の顔を見つめて櫻井が効くと、「今まで通り、ただのボディーガードとして振る舞うことだ。そのうち部長から次の指示がくるだろう」と返事が返ってくる。
阿部は再度櫻井の肩を叩いて、闇の中に消えていった。
そしてあっという間に気配がなくなった。
「おはようございます」
香倉が挨拶をしながら研究室に入ると、「おはよう」とその場にいた数人の助手から返事が返ってきた。
だがその中に利賀の声はなく、香倉は自分のデスクにカバンを置きながら、さりげなく利賀の姿を探した。しかし、利賀の姿は見えない。
利賀が、夕べ不穏な動きをしたことは、既に香倉の耳に入っていた。
阿部からの報告によると、確証は得られていないが利賀とオゾッカの河田が高級料亭で密会していたことはほぼ間違いない。
今回のこの動きは、榊がしくんだあの襲撃が引き金になっているのだろうか・・・。
香倉は考えを巡らせたが、その辺のつながりについては、いい筋書が思い浮かばなかった。
だが、どんなきっかけにせよ、新たな動きが始まったことには違いない。
今まで根気よくやってきた香倉の仕事の成果がようやく実になり始めた証拠だった。
周囲の助手達は、皆せわしなく自分の研究ファイルを取り出してまとめる作業に熱心で、利賀がいないことにも気づいていない様子だった。もうじき・・・あと三十分後に週一回行われる菅原研究室の定例会が始まるからだ。
定例会では、菅原教授の今後のスケジュールと助手それぞれの研究の成果及び進展の報告、各企業への助成金申請の割り振り等、非常に重要なことが話し合われる。
特に、助手達は自分の研究が菅原教授の興味を引けば、今後の出世に直結するので、誰もが必死だった。
一方香倉は、元々研究要員というより本当の意味での助手として雇われている手前、そこまで必死になる必要もなかったが、怪しまれない程度に香倉も会議で報告できる程度の研究テーマを準備していた。
しかし、そんな大事な会議があるというのに利賀がいないのは不自然だった。
利賀はいつでも誰よりも早く研究室に来ていたし、会議の前となるとそれこそ熱心に自分の研究のレポートを再チェックしていた。
── よもや、昨日の密会を受けて、行方をくらませた・・・なんてことはないよな・・・
香倉の脳裏に、ふとそんな不安がよぎる。しかし、阿部からはそんな連絡は一切受けていなかった。
阿部は今でも、利賀に張り付いているはずだ。
今回の一件で、利賀の学外の動きをしばらく経過観察することになっていた。だから、利賀が行方をくらませれば、阿部から報告があって当然だった。
香倉は、腰のポケットに差し込んである携帯電話に手をやったが、彼はそれを取ることなく、資料を抱え会議室に向かった。
会議の冒頭は、菅原教授の北米大陸出張の成果の報告から入った。
新しい植生分布研究チームとの研究発表会の様子や米国の製薬会社とのミーティングの様子、新たに持ち帰った植物資料についての説明等が、プロジェクターを使って行われた。
特に米国大手の製薬会社でのミーティングの下りでは、助手が皆色めき立った。
日本の製薬会社と比べ、外資系・・・特に米国の製薬会社は、特に有効な研究と判断されたことに対する資金援助は下品なほどあからさまに巨額の資金を投入してくれる。研究室が潤えば、個別に進めている研究にもおこぼれが回ってくることは間違いないし、新たな研究機材をいれることも可能だ。
今日、地方大学の研究室が研究資金の捻出に必死になってるというのに、菅原教授の研究室にはそんな苦労は無縁だった。助手の皆は気づいていないが、それはひとえに菅原教授が経済的手腕に長けているおかげだった。
研究畑にいる大学教授というものは、大抵経済観念が欠如していたり、世間知らずな者も多いが、菅原は違っていた。菅原教授は教授としては珍しく、その点のバランス感覚が優れていた。
「── ということで、私の営業活動も無事すんだことだし・・・」
菅原がそう冗談を飛ばすと、助手の皆が一斉に笑った。香倉も同じように笑いながら・・・とはいっても目は冷静なままで・・・時計を見る。既に会議が始まって40分経っている。利賀はまだ姿を見せない。
「私はしばらく日本でゆっくりとこれまで溜まった資料を纏める作業に専念したい。では、君たちの研究報告を聞こうかな」
菅原がそう言った時、丁度いいタイミングで利賀が会議室に入ってきた。
酷く慌てた様子で、額には汗が浮かんでいる。
「── すみません、遅れました・・・」
利賀がそう言いながら、末席に座る。菅原が「カナダから帰国した時の時差ボケがまだ治らないのかな」と単純な冗談でそう言ったが、それに対して上がった笑い声は些か利賀を小馬鹿にしたようなものだった。利賀の研究室内での扱いを象徴するような笑い声。しかし、だからこそ利賀も慣れたものなのだろうか。あえてそれには反論せず、ただ「すみません」と頭を下げた。
むろん香倉も顔には出さなかったが、こういう空気は好きではなかった。
どこの世界に行こうが、こういう扱いを受ける人間はどこにでもいる。
夜の世界は、そういうのが極めてシンプルに分かりやすく図式化できるのだが、こういう個人の利害が複雑に絡み合うような場所では、かえって陰湿だ。そのためか、菅原はこの微妙な空気に気がついていないようである。
「あー、利賀君。カナダ出張の報告書、ありがとう。よくできていたよ」
「あ、ありがとうございます」
「さっき君がいない間に、皆に言ったのだがね。しばらく私は自分の研究ラボに籠もるから、君も自分の研究を進めてもらっていいからね」
菅原がそう言うと、利賀の表情が途端に明るくなった。
その表情から察すると、自分の研究に再び戻れることによる喜び以上の何かが働いているようだった。
「あ、あの・・・実は教授・・・」
「ん、なんだね」
「よければ少しの間、東南アジアの方に行ってきたいのですが・・・」
── きた。
香倉にはピンときた。
阿部からの夕べの報告を受けての利賀の申し出だ。
何もない訳がない。
「少しの間? となると、二、三日という口ぶりではないね」
菅原が怪訝そうに利賀を見る。利賀は汗を拭きながら、「研究対象の標本が足らなくて、統計がとれないんです。今回は、奥地の方まで足を伸ばしてみようと思っています」と彼にしてみれば早口でそうまくし立てた。
だが、香倉以外の誰もそんな利賀の変化に気がつかない。というより彼らには興味がないのだ。
香倉は、すっと手を挙げた。
菅原が香倉の方に目をやる。
「なんだい、東城君」
「教授、差し出がましいことは十分に分かっておりますが、僕の研究対象地域は利賀さんと重複しているところが多いので、できれば僕も同行させてもらいたいのですが」
ザワッと会議室内が揺れた。
他の研究員にとっては、利賀なんかより香倉── 彼らにとっては、何でもこなしてしまういけ好かない新人研究員・東城であるが── の動向の方がよっぽど気になるらしい。
だが、この中で一番動揺しているのは利賀だった。「え!」と絶句したまま、口をパクパクさせている。
菅原は呑気なもので、ふ~むと下あごを撫でながら、「それもそうだねぇ。東城君には私がいない間、随分頑張ってくれたし、確かに一人で行くよりアジアに慣れてる利賀君が一緒だと、私も安心だし」と呟く。
「きょ、教授!」
利賀が声を挙げる。
「それは、東城君と行動を共にしろということですか?」
利賀の反論に珍しく他の人間が同調した。
「そうですよ、東城はまだ入って間もない。海外は早いです」
「何いってるの」
菅原が眉間にしわを寄せる。
「君だって、入って半年で私についてマレーシアに行っただろうが」
「それは教授の助手としてです。自分の研究のために行った訳では・・・」
その反論は、教授の表情が益々まずくなっていくにしたがって、尻すぼみになって行った。
ここではやはり菅原が王様だ。菅原の機嫌を損ねたら、その後はない。
「君ね、そういう風なへりくつを言うもんじゃないよ。私だって、未熟な者をおいそれと単独で海外にやることはしない。東城君には海外にやっても大丈夫だろうし、それにベテランの利賀君がついているんだから、何を心配する必要があるのかね」
「教授・・・あの・・・」
「なんだね、利賀君」
「今回は、調査の困難な奥地まで足を伸ばそうと思っていたんです。海外研究に慣れていない東城君を同行させるには・・・」
「それなら大丈夫です」
反論を許さない声色で香倉は言った。
「体力には自信があるし、自分の限界点もよく理解しています。もし利賀さんのお手を煩わせるようなことになるくらいだったら、自分から身を引きますよ。ただ、僕だって研究員の端くれです。自分の研究に役立つことであれば、どんな苦労も厭いません」
他の研究員は、顔を顰めて小言か何か言いたげな様子だったが、菅原が満足げに頷いたのを見て、皆口をつぐんだ。
「利賀君も、意地悪なんか言ってないで東城君を連れて行ってあげなさい。それに、かえって君の方が助かるかもしれないんだよ。東城君の情報処理能力が優れていることは、利賀君だって知ってるだろう。いいね」
「・・・はい」
利賀は渋々だが頷かざるを得なかった。
ミーティングが終わると、トボトボと出ていく利賀の後を香倉は追った。
「利賀さん」
香倉が声をかけると、昨日の友好的な彼はどこへやら、煙たそうな顔つきでこちらを振り返ってきた。
利賀は周囲を見回し、目線で香倉に廊下の隅に来るように促した。
「ちょっと、どういうつもりなんだよ」
日頃おとなしい利賀が、今日はいやにあからさまだった。
香倉は内心、ほくそ笑む。
これは案外デカイ魚を引っかけている状態なのかもしれない。
「どういうつもりって?」
「とぼけるなよ。邪魔するつもりか」
「邪魔なんてそんな」
香倉はわざとらしく周囲を念入りに見回すと、利賀に耳打ちをした。
「向こうに行ったら、別行動にしましょう」
利賀が驚いた顔つきで香倉を見上げてくる。
「東城君・・・」
「確かに研究地域はかぶってますけど、やりたいことが同じという訳ではないですからね。お互い別々の方がフットワークが軽くてすむ」
「でも・・・」
途端に利賀が不安げな表情を浮かべる。
「教授にバレないか心配ですか?」
香倉が訊くと、利賀は頷く。香倉は利賀を安心させるように肩に手を置いた。
「そこら辺は任せておいてください。なに、初日と最終日に一緒に移ってる写真を撮ればいいんです。あとは互いに互いの分の植物標本を適当に分け合って、合同の報告書を作成すればすむ話ですよ。僕が教授にうまく報告します」
利賀の表情がみるみる緩んでくる。
「でも・・・本当にいいの? 君、向こうにツテはないだろうに」
「まぁ、研究関連では確かにないですけど・・・。利賀さんの紹介でということであれば、出入りも簡単にさせてくれるでしょう。それに、海外経験がまったくないわけではないんです。南の方ではないですが、一応アジア圏でしばらく住んでいたこともあるし、その間東南アジアにはよく旅行していましたから」
「そうなの? そういうことならまぁ安心だ。向こうの関連大学のことなら、よろこんで紹介させてもらうよ。電話で済む話ならね」
「そうしてもらえると助かります。もし利賀さんに僕が協力できることがあればおっしゃってください。互いに、持ちつ持たれつで」
香倉がウインクすると、利賀は不器用な笑顔を浮かべながら「まぁ、商談成立ということだね。大まかなスケジュールが組めたら、東城君に電話するよ」と言った。ポケットから携帯を取り出す。
「念のため、東城君の携帯番号教えてもらえるかい?」
「ああ、いいですよ」
香倉は、東城として契約している携帯電話を取り出した。
香倉が番号を教えると、利賀は登録するのに四苦八苦している。
「── しばらく登録作業なんてしてないから・・・。どうだっけ・・・」
「やりましょうか?」
「ああ、お願いするよ」
香倉は、利賀から携帯を受け取って登録する素振りを見せながら、素早く利賀の着信・発信履歴や登録メンバーをチェックできる範囲でした。
予想通り、恐ろしく登録件数は少ない。それどころか登録者がフォルダー分けもされておらず、香倉はほぼ全員の名前を記憶した。
「できましたよ。どうぞ」
香倉が、登録したばかりの電話番号を見せて説明すると、利賀は心底香倉を信頼した顔つきで「ありがとう」と言ったのだった。
接続 act.12 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
ややや・・・やっと書いた・・・・。
今週もめちゃめちゃ仕事が忙しくて、ほぼ毎日10時ぐらいまで働いていたんで、とんでもなくハードな一週間でした・・・。って、今日も夜に打ち合わせに行かなきゃならないんだけど(涙)。
そんな中書いただけあって、少々盛り上がりに欠けますが、どうぞご容赦ください(脂汗)。
当然のことながら、次週のストックは
ありません。
力こめていうようなことじゃないっすね・・・。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
