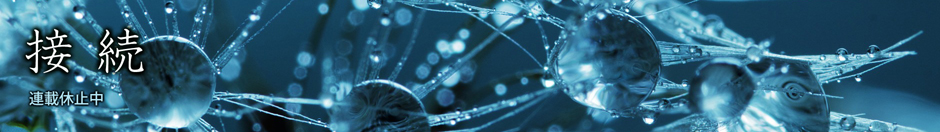
act.25
突然バシャリと頭の上から水を浴びせかけられた。
香倉ははっと気がつき、ブルリと頭を振った。
どうやら僅かの間だが、気を失っていたらしい。
例の部屋から軍人もどきの男共に連行された香倉は、古びた木製の椅子に座らされた恰好で両手両足を拘束されていた。
案の定、相手は香倉を丁重にもてなしてくれるわけはなく、さんざん殴られたあげく、しまいには壁から剥いだ電線の端っこを押しつけられる始末だった。
おかげで軽く気を失ってしまったのだが、幸い香倉は、過去このような拷問を受けたことが数回あった。中には更に手酷くされたこともあったので、香倉にはいくらか余裕があった。
鼻や口からは血が流れ出ていて散々な有様だったが、香倉はまだ言葉らしい言葉は一言も発していなかった。
こんなに手荒な連中がこの物騒な工場を取り仕切っているとすれば、利賀はおろか利賀の内縁の妻や子どももどのような扱いを受けているか分かったものではない。
一方、香倉を直接痛めつけている若い男二人は、香倉が一体どこの国の人間で何者なのかを計りかね、苛ついているようである。彼らのボスらしき初老の男は、香倉の所持していた物を熱心に物色している。
香倉はその様子を見ながら、内心胸をなで下ろしていた。
── 急場のことだったとはいえ、現地で全ての物を調達してよかった・・・。
一部日本製のものが混じっているとはいえ ── デジタルカメラは日本製である ── 多くは闇で出回っている米軍やロシア軍の横流し品であったり、出所が定かでないようなものばかりだったからだ。
そのお陰か、連中は香倉が極東アジアのどこの国の人間なのか絞りきれずにいた。しかし中国人と朝鮮人は候補からはずされたようである。
目が覚め際、再び香倉は顔を殴られた。嫌な音がして香倉は思わずうなり声を上げた。
口の中がゴリッとした。
下を向いて口の中の血の塊を吐き出すと、白い小さな欠片が混じっているのを見て、香倉はげんなりとなった。
これだけ素手で殴れば、相手の手も相当のものだろうに・・・と男を見上げると、案の定男の拳も赤く腫れていた。案外拷問には慣れていないのかもしれない。
「・・・チッ・・・しぶといな」
「これほどまでやって何も吐かないとは、どんな神経をしてやがるんだ・・・」
部下達はそう口々にそう口走りながら、上司である初老の男に目をやった。
初老の男は始めて香倉自身に興味を持ったかのように少し目を見開いて香倉を見やると、やっと香倉に近づいてきたのだった。
初老の男は香倉の目の前に立っていた若い男を押しのけると、腰元から小型の特殊警棒を取り出した。
棒の切っ先で自分を見上げる香倉の顎を右側に押しやると、そのまま棒の先で濡れた黒い長袖Tシャツの襟元を肩口の方向へ押しやった。
散々捕まれて伸びた襟元から覗いていた刺青の一部が男の目に止まったらしい。
「なんだ、これは」
部下達は自分たちが見逃していたポイントを指摘され、バツが悪そうに互いの目を見合わせる。
「おい」
初老の男が目配せする。
それを合図に、乱暴にTシャツを剥がれた。
手を後ろ手に拘束されていたので、破れた布きれが、湿り気を帯びたまま胴や腕にまとわりつき、気持ち悪かった。
「ホンモノですね」
男が露わにさせられた赤い朱雀の文様に手を這わせ、言う。
初老の男は、興味深く長い時間それを眺めた後、急に興味をなくしたかのように顎でドアの方向を指し示した。
それを合図に椅子からの拘束を解かれ、後ろ手に縛られたロープはそのままで無理矢理立たされた。
どうやら今日はこれで終わりらしい。いや、それとも香倉の命そのものを終わらせるつもりなのか・・・?
香港の町並みは、明らかに日本のものと違っていた。
タクシーの車窓から見える風景は、雑踏という言葉がよく似合いの、実にエネルギッシュで混沌とした町並みが広がってた。
近代的なデザインで彩られた高層ビルがあったかと思いきや、一本道の奥に目をやると薄汚れた古い住宅がひしめき合うように建っている。
道行く人は極めて日本人によく似た人々が歩いていたが、不思議と日本より活気があるように見えた。それに、東京よりで見かけるよりも多く白人の姿を見る。1997年7月に中国に返還されたとはいえ、元はイギリス領だったために未だに数多くの外資系企業がオフィスをおいていると聞く。
時刻は丁度午後六時頃で、美しい夕焼けが空を焦がしていた。
退社時間に重なったのか、道は渋滞していて、窓の外では様々な方向からクラクションが鳴らされていた。
櫻井は、空港でタクシーを拾うなり例のマッチを運転手に見せ、「そこにやってほしい」と英語で指示をした。
タクシーの運転手は黄色く濁った目で、胡散臭そうにマッチと櫻井の顔を交互に見やった。
「お客さん、その店、本気で行くのか」
多少訛りはあるが、流ちょうな英語が返ってきた。
運転手の怪訝そうな顔が、櫻井を少し不安にさせた。
「ああ。行くつもりだ」
それでも櫻井が毅然と答えると、ふうんと運転手は鼻を鳴らした。
「お客さん、知ってるかどうか分からないけど、その店、とてもお金かかるよ。とてもね」
運転手はそう言う。
どうやら櫻井の身なりを見てそう言っているらしい。
「それなりの恰好をしていかないと、相手にしてもらえない。少なくとも、そんな恰好じゃ入れてもらえないね」
「それでもいい。とにかく、その店の場所まで行ってください」
櫻井は更に強い口調で言った。運転手は渋々車をスタートさせて、今に至る。
運転手が言うに、櫻井の指し示した『華見歌壇』は、香港島でも屈指の高級クラブで、地元の有力企業の接待の場となっていることはおろか、中国本土の共産党員まで頻繁に訪れているという店らしい。
それだけに、そこで支払われる金額はそれ相当の者で、香港の人間でもごく限られた人間しか入れない店となっているらしい。
つまり、有名な店ではあるが、今の櫻井のようにタクシーを拾うようなごく普通の観光客には到底手の届かない店であるという訳だ。この店目的で来るラグジュアリーな観光客は、タクシーなど拾わずリムジンをチャーターして乗り込むのが常套という訳だ。
しかし櫻井としては、店の場所をまず確認する必要があった。
例え門前払いを食らおうとも、なんとしても櫻井は『リンファ』という女性と接触する必要があった。
手がかりは、『華見歌壇』しかない。
櫻井は、車窓を流れる刺激的な風景を見つめつつ、カチリと親指の爪先をかんだ。
接続 act.25 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
600,000ヒッツのプレゼントCDの方もアイデアがただいま停滞中・・・・。
ジャケット、どんなデザインにしよ・・・とかってグニャグニャしてます。
ぐにゃぐにゃ・・・ぐにゃぐにゃ・・・。
せっかく誕生日を迎えたというのに、なんだか煮え切らない国沢なのです。
や、誕生日を迎えたからこそか・・・。
人間、だんだん誕生日が楽しくなくなるっていうのは、本当ですね(笑)。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
