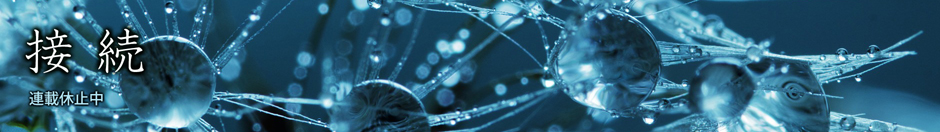
act.27
結局櫻井は、一旦出直すことに決めた。
シャンハイ・ストリートの傍にあるホテルに部屋を取り、翌日身なりを整えてハイヤーを雇い、再度出向くことにした。
幸い、仕立てのいいスーツは持ってきていた。
香倉が買ってくれたスーツだ。
何かと思い入れのあるものである。
香倉が見立ててくれたブラックスーツは、実際櫻井によく似合っていた。
少なくとも、つるしのスーツを着ているような安月給でこき使われているサラリーマンには見えない。
あいにくネクタイは、仕事の時に使うような地味な色のものしか持っていないから、華やかなパーティー用・・・とはいかないが、それでも見劣りはしないだろうと高をくくって、櫻井はハイヤーに乗り込んだ。
運転手に行き先を告げると、運転手は「かしこまりました」と返事をした。
バックミラーから見える彼の顔は、いたって普通のなごやかな顔つきだったが、内心彼が不機嫌になっているのが何となく『肌で分かった』。
目的地の華見歌壇は、目と鼻の先で歩いて行ける距離だから、迷惑な客だと思われたのだろう。
一年前の事件があって以来、妙に人が表に出さない内部の感情が分かる時がある。
空気というか雰囲気というか。
全身の五感から、脳みそまで直接相手の気持ちが伝わってくる感覚。
気のせいだと言ってしまえばそれまでだが、そういう場面に出くわす度、櫻井は姉のことを思い出すのだ。
やはり血は争えないということか。
しかし、運転手が例え嫌がろうとも、ここはわざわざハイヤーを使う必要がある。
やはり「どんな客でも身なりさえ整えていれば大丈夫」と言われても、徒歩で来る客なんか相手にされそうになかったからだ。
資金は潤沢にあるかどうかは分からなかったが、金の支払いについては高橋秀尋名義のクレジットカードを使えと公安総務課から言われている。
よもやカードが使えない訳ではあるまい・・・。
内心ドキドキしながらも、櫻井は例の店の前に降り立った。
まるでステージに登るかのような数十段の階段を登り、ドアマンに近づいた。
「いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました」
ドアマンが笑顔で軽く頭を下げる。「初めての方ですね」といきなり言われた。どうやら客の顔を覚えているらしい。櫻井が「はい」と素直に答えると、「では、誰かのご紹介でしょうか?」と訊かれる。
櫻井は正直心臓がキュッと縮まった。
まさか昨日の運転手の言っていたこととは違って、一見の客は誰かの紹介がなければ入れないのだろうか・・・?
「えっ、いや・・・、その、そういうことはありません。誰の紹介でもありません。紹介がないと駄目ですか?」
おかげでしどろもどろになって、英語の文法を間違ってしまった。
辛うじて我慢はしたが、自分の不甲斐なさにため息をつきそうになる。
── こんな時、香倉さんならもっと上手くやれるだろうに・・・
これはきっと相手に呆れられるに違いない・・・と思った櫻井だったが、櫻井の返答を聞いてもドアマンからは櫻井を値踏みするような雰囲気は一切感じられなかった。
「いえ、紹介がなくとも構いませんよ。初めての方は誰かの紹介なしに最初から特別なお部屋に入れないことになっておりまして、それを確認させていただいたのです」
そういう彼の笑顔と櫻井が『肌で感じる感覚』に違和感はない。
櫻井がこのようなところに慣れない人間だと分かってからも、相手が櫻井を見下している様子はなかった。
一流の店の人間というものは、こういうものなのだろうか。
相手に嫌な思いをさせないよう、よく教育されているということか。
「ではこちらへどうぞ」
もう一人のドアマンが重厚な造りの両開きドアを開いた。
その途端、ふわりと花の香りが櫻井の顔を包んだ。
通路の両側に見事な生花が壺生けされていた。
その圧倒的な花の量に圧倒される。
生まれてこの方、こんなにたくさんの花に囲まれたことがない。
ドアマンに案内されながらも思わずキョロキョロと見てしまった。
── いけない。雰囲気に飲まれたら駄目だ。
櫻井は鼻の下を指でこすると、気を引き締めた。
二箇所目の両開きドアが現れる。
こちらは入口ドアとは違って、華奢なステンドグラスがはめ込まれた華やかなものだ。
そのドアが、唐突に、まるで自動ドアのように開いた。
薄暗く狭まかった視界が急に開ける。
櫻井は思わず息を呑んだ。
これは高級クラブというより、オペラ座のような美しい劇場のようだ。
ただ通常の劇場と違うのは、正面のステージを見下ろすように大小様々な大きさのボックス席が階段状に配置されている。
「こちらへどうぞ」
ドアマンから案内を引き継がれた女性の案内係が行き先を指し示した。
案内係は黒いチャイナドレスを着ている。
ほっそりとした後ろ姿に導かれながら、櫻井はぐるりと中を見渡した。
丁度混み始める前の時間帯なのか、空席の方が多かった。
ステージの緞帳はまだ下りていて、お客の話し声がさわさわと聞こえてくる。
「ご希望のお席はございますか?」
階段の降り口でそう訊かれた。
「いや、特には・・・」
そう答えると、「かしこまりました、こちらのお席にどうぞ」
数段階段を下りた右側の席に案内された。
「すぐに係の者が参りますので」
そう言われ、「誰かくるんですか?」と思わず聞き返してしまった。
立ち去りかけていた案内係はひたと足を止めると、「はい。このお店では、サービスで各テーブルにスタッフがつくことになっております。男性のお客様が多い場合は女性が、女性のお客様の場合は男性がつきますが、ご希望があればおっしゃってくださって結構ですよ」と案内してくれた。
なるほど、ここら辺が『高級クラブ』なわけだ。
正直苦手な状況だなぁ・・・と思った櫻井だったが、あっと気がついた。
「リンファさん、いますか? できればリンファさんをつけてください」
案内係は一瞬きょとんとした表情をした。
あれ、まずかったかなぁ・・・と思った瞬間、女は笑顔を浮かべた。
「ええ、リンファはいます」
ちょっと仇っぽい笑みだった。だがそれは一瞬のことだった。
「でも残念ながらリンファはテーブルにつかないんです。申し訳ありませんが、彼女が席までくるのはごく限られたお客様のみなのです」
「あ、そうなんですか・・・」
女は一礼すると、席を離れていった。
少しの間があって、お盆を持った女性がやってきた。こちらは目の覚めるような深紅のチャイナドレスを着ている。
「ようこそお越しくださいました。わたくし、スーと申します」
予想に反して三十代後半ぐらいの女性だった。
こういう店は、若い女の子がつくとばかり思っていた。
だが櫻井にとっては、かえってこういう落ち着いた女性の方が安心できる。
若い女の子に色目を使われながら迫られると、きっと気分が悪くなって潜入捜査どころでなくなりそうだ。
温かいおしぼりを手渡された。
ここは日本のクラブと似ている。
おしぼりを広げると、また花の香りがした。
「お客様は、日本の方ですか?」
と訊かれた。「はい」と答えると、スーは「やっぱり。これ、日本のお店のやり方を取り入れておこなっているサービスなんですよ」と流ちょうな日本語で返してきた。櫻井が驚いた表情を浮かべると、「このお店は、日本からのお客様も多いのです」と笑顔を浮かべた。
「何を飲まれますか?」
「ええと・・・、ウイスキーを・・・」
「かしこまりました」
スーが軽く手を挙げると、黒服のフロア係がオーダーを取りにやってきた。
「何か一緒にお食べになりますか?」
「えっと・・・、特には・・・」
「まぁ、お酒、お強いんですね。では後で何かほしくなったら、仰ってください。このお店は料理もなかなかおいしいんですよ」
スーはそう言って黒服の手からメニューを受け取って、テーブルの片隅に置いた。
「ウイスキーはそのままお飲みになります?」
「あっと・・・、水割りで・・・」
「かしこまりました」
スーは手際よく水割りを作っていく。
それを見ながら、櫻井は日本語で訊いた。
「あのリンファさんにはお会いできないんでしょうか?」
スーはグラスについた水滴をおしぼりで拭きながら、ちらりと櫻井を見た。
「心配しなくても会えますよ。もうすぐ」
スーはそう言いながら腕時計を見た。
「そうですね、本当にもう間もなくですわ」
「間もなく? それって・・・」
櫻井が聞き返そうとした時、櫻井は周囲の様子が変わっていることに気がついた。
ほんの先ほどまで空席が目立っていた店内が、いつの間にやら客で埋まっていた。空席を探す方がかえって困難なほどである。
さわさわとした話し声は櫻井が入店した時とさほど変わらなかったが、先ほどまで涼やかだった店内の空気は、今はどこか熱気を帯びているように櫻井は感じた。何かを期待するかのような高揚感とでもいうのだろうか。
どこ客もステージの方に身体を向け、仕切りと何かを話している。
「いよいよですわ。念願のリンファさんにお会いできますわね」
スーがそう言った瞬間、店内の照明が暗転してステージにスポットライトが当たった。それと同時に有名なオペラ、カルメンの曲が流れ始め、赤い緞帳がスルスルと上がっていったのだった。
香倉が放り込まれた部屋は、元々資材置き場だったのだろうか。
狭い室内はガランとしていたが、少し薬品臭い匂いがした。
片隅には鉄製のコンテナケースが置かれてあり、部屋の上部には鉄格子つきの空気窓が細長く開いていた。
どうやら本格的な軟禁部屋でなさそうなところを見ると、この工場には以前本当に侵入者たぐいの輩に狙われたことがなかったらしい。
その経験の浅さが、香倉に対する尋問の詰めの甘さに繋がっているのだろうか。
尋問を受け始めて二日目だったが、香倉がどこの国の人間なのか、彼らはまだ特定できずにいた。
夕べから続けられた徹夜での尋問も、香倉の方が随分タフで相手方の方が根を上げる始末だった。
どうも相手は慢性的な人員不足らしい。
香倉の尋問に当たっているのは、最初に香倉を拘束した若い男二人だけだった。
彼らの上司であるあの老兵は、どういう訳か姿を見せなかった。
しかしここにいると時間の感覚がなくなる。
いくら緩い拷問とはいえ、状況を冷静に考えれば、香倉にとってもこれは『ヤバイ』状況である。
公安の世界に長く身を置く香倉にとって、ここ数日の間本部に定期連絡を入れていないこの状況が何を意味するのか、十二分に理解していた。
どうにか打開策を考えなくてはならない。
何とかして、ここから逃れなくては・・・。
そう思っているうち、隣の部屋のドアが開いて、別の誰かが部屋の中に放り込まれたのが分かった。
よく耳を澄ませると、それは香倉が知っている男の声だった。
ドアが閉まる。
足音が遠ざかったのを確認して、香倉は鉄のコンテナの上に登った。空気窓から隣を覗く。
やはり思った通りだ。
隣の部屋でうずくまっていたのは、利賀だった。
「いいですねぇ、そちらにはベッドと簡易トイレつきですか」
香倉がそう声をかけると、利賀はビクリと身体を震わせて、怯えたように周囲を見回した。
「上ですよ、上。こっちです」
ようやく利賀が気づいた。
「君、東城君・・・かい?」
鏡なんか見てないから分からないが、おそらく殴られた右頬が熱を持っているので、腫れているのだろう。
人相が変わった後輩の姿に、利賀は驚いた。
「どうしたんだい、その顔。殴られたのか。それに・・・君がなんでここに? ひょっとして、まさか僕のせいか?」
利賀の顔色が益々青ざめていく。
どうやら自分のせいで香倉も巻き込まれたと思っているらしい。
── ここますっとぼけて、芝居を続けるべきかどうか・・・
正直判断がつかなかったので、取りあえず話を合わせることにした。とにかく、今のままでは余りにも分からないことが多すぎる。迂闊に正体をばらす訳にはいかない。
「利賀さん、一体ここで何をしているんですか? ここまでされたんだ。僕にだって知る権利はあるでしょう」
目に見えて、利賀の身体がビクリと震えた。
「何してるって・・・」
利賀は言いよどんでいるが、香倉は引くつもりはなかった。
「この部屋に連れてこられるまで、僕はもの凄い光景を目にしましたよ。人間が生きたまま解剖されて、何かの培養液につけ込まれてました。中には臓器がないヤツもいた。とても正気の沙汰とは思えない。明らかに残忍な犯罪行為です。利賀さんは、それに荷担してるんですね?」
香倉が冷たく言い放つと、利賀は座り込んでいたベッドから立ち上がった。
「と、とんでもない! 人を、か、解剖するなんて、そんなの、知らない!」
「じゃぁ、何だっていうんです? 僕らがこんなところに閉じこめられているだけの原因、利賀さんには心当たりあるんでしょう?」
「ぼ、僕はただ、カバーラのエキスを抽出するシステムの改良を命じられてるだけだ・・・。僕は誰も殺してない。人殺しなんかじゃない」
「カバーラ? カバーラとはなんです?」
「カンボジアの密林地帯に自生している野草だよ。アヘンに似た成分構造を持っている」
「麻薬ですか?」
「効果は似ている。だけど、自生している場所もごく限られていて、そこに生えているものはもう採り尽くしたみたいなんだ。しかも人工栽培に適してなくて、人の手で栽培したカバーラからは薄い濃度の抽出液しか採取できない。そのせいで、僕が呼ばれたんだ。もっと高濃度の抽出液が確保できるようにと奴らから命じられてる・・・」
香倉は、考えを巡らせた。
奴らはカバーラという麻薬性の高い植物を使って生物化学兵器を作り出そうとしているのだろうか。
だとすれば、あのケースに収められた人間達は、人体実験の材料なのか・・・。
「なぜカバーラという植物にこだわるんです? 生産性が悪いのなら、芥子を育てた方が効率的でしょう。こだわる理由は、人体に対して殺傷能力が高いせいですか」
ここでも利賀は大きく首を横に振った。
「と、とんでもない! カバーラに殺傷能力なんてないよ! そりゃぁ、ずっとずっと長い間摂取し続けたらどうなるか分からないけど、常習性はむしろアヘンより弱いんだ」
「じゃ、なんで」
しばらく沈黙が続いた。
利賀は香倉に全てを告げていいか迷っている様子だった。
香倉は、だめ押しのように言った。
「互いに協力しないと、ここからは出られませんよ、一生。連中は、人の死を何とも思わない輩です。僕はこの目で見たんだ。あの残忍な光景を。僕も、あなたも、あなたの家族も、ひょっとしたら同じようにあの培養液に漬け込まれることになるかもしれないんです」
利賀はハッとして顔を上げた。
その両目から、みるみる涙が溢れ出てきた。
利賀は意を決したように唇を噛みしめると、こう言った。
「カバーラには・・・、あれには、人を意のままにコントロールする力があるんだ」
接続 act.27 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
今週も妹夫婦の襲来を受けている国沢です(汗)。
うちのおネコ様たちも、戦々恐々として避難しております(笑)。
ネコってホント、子ども苦手ですよね。かわいがり方が乱暴だから(笑)。
でも不思議と子どもだって分かってるのか、うちのおネコ様の場合、よっぽどのことがない限り?まないし、爪も立てません。その代わり、後でその子どもの親(つまり妹)の足に何の前触れもなく噛みついてますけど(笑)。復讐でしょうかね。
最近見るテレビ番組のせいでというか何というか、はたまた年齢を重ねたせいかどうなのか、近頃とみに「いきどおる」ことが多くなってきました。
しかも類は友を呼ぶというのか、国沢の友人達もそんなのがいて、特に仲のいい人達は国沢と同じように社会に対して「いきどおって」ます(笑)。
このいきどおりっぷりはまた気が向いたら、ブログにでも書こうと思います。
そして万ヒッツCDは、米国のiTunes ギフトカードという強い味方を得て、どんどん選曲進行中。近いうちにジャケットデザインの準備もできるのでは、と思ってます。
誰かに待たれようが待たれまいが(待たれていない可能性の方が高いだろうが)、着々と進行中です!
内心、650,000ヒッツまでには完成したい・・・と思う今日この頃。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
