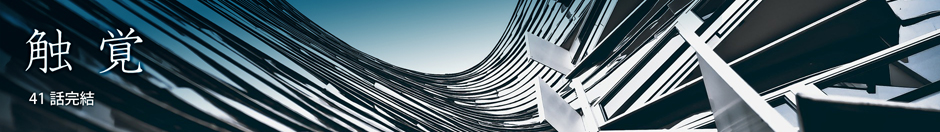
act.36
どれぐらい時間が経っているのか分からない・・・。
ぼんやりと目を覚ました香倉は、身体全体をいまだ覆っている痺れ感に顔を顰めた。
「早くもお目覚めか。タフだなぁ、お前」
すぐ側で、あのダミ声がした。
一気に意識が覚醒する。
身体を起こそうとして、香倉は自分が身体の自由を奪われていることに気がついた。
リストバンドを巻かれた両手首の上から手錠をかけられ、頭上にある黒いパイプベッドの支柱に引っ掛けられてある。
香倉は、固いベッドに突っ伏して濃い溜息をつく。
「ご大層なことで。態々リストバンドまでご用意してくださったんですか」
嫌味たっぷりに香倉が言うと、ベッドの脇にあるパイプ椅子に腰掛け、プカプカと煙草と煙を吐いていた榊が、二ヤリと笑った。
「男前に敬意を表したのさ」
「何をバカなことを」
香倉はそう返しながら、部屋の様子に目をやる。
およそ、特徴的なものは皆無に等しい。時計もない、テレビもない。極平凡なワンルームで、部屋の中央に香倉が拘束されているパイプベッド、その脇に小さなアルミ製のテーブルと榊の座るパイプ椅子、入口の脇に申し訳程度についている流し台が見える。その隣にあるドアは、上の隅に小さな四角いガラス窓がついているところを見ると、ユニットバスの入口といったところだろうか。
おそらくこの部屋は、公安員がよく使っている捜査潜伏用の部屋のひとつなのだろう。
部屋の隅、玄関ドアの近くに、香倉にスタンガンを押し付けた中年男が立っている。 年に一度、トップシークレット扱いで行われる公安部の辞令式があるが、その時にちらりと見た顔だった。
辞令式には特務員も含め、出席可能な限りの公安職員が一堂に会すが、警察組織の一員でありながら警視庁内部では行われず、僻地の工業地帯にあるビルの中で行われる。表向きは一般商社の持ち物であるビルだが、実のところ警察庁が裏で管理をしているところだ。捜査上、表に出しては問題になりそうな裏の捜査資金の流れ等をそのダミー会社内で管理しているという。
「とにかく、ほとぼりが冷めるまでここで大人しくしているんだな」
アルミのテーブルにある灰皿ばかりは、警察署内の備品である安っぽいスチール製の灰皿だった。そこに突っ込まれてある煙草の本数を見ても、確かに榊の言う通り、思ったほど時間は経っていないのかもしれない。
窓には遮光性の高いカーテンがきっちりと引かれてあるので、今が夜か昼かも分からない。
榊は「暴れたりするなよ」と釘を刺すが、少なくとも今のような状態では抵抗するのは不可能のように思われた。
さっき身体を起こした時に感じたことだが、恐ろしく身体が重い。よほど強烈な電流を身体に流されたに違いない。滅多に感じた事のない頭痛がした。だが、幸いなことに、多少呂律が不安ではあったが、口がきけないほどではなかった。
香倉は苛立ちを隠しもせず、チクチクと榊を刺激した。
「ほとぼりなんか、冷める訳がない。臭いものに蓋をしただけで、根本的なことは解決してないんですよ。カガミナオミを誰かが押えない限り、俺は永遠にあの女に狙われる訳です。本当に俺が死ぬまでここに閉じ込めるつもりですか」
いつもの榊なら、すぐにカッとした素振りを見せ、ベッドの端のひとつでも蹴り飛ばすところだが、今回の榊は違っていた。落ち着いた物腰で煙草を揉み消すと、カリカリと額を掻いて、腕組みをした。
「むろん、女は押える。だがそれをするのはお前じゃねぇ。既に鈴木と安部が動いている」
鈴木、安部の両名は公安特務員の精鋭として活躍した後、今は政治関係の犯罪やトラブルに対処する部隊に所属しているベテラン中のベテランだ。その人選から見ても、榊が本気であることは推し量れた。
だが、鈴木や安部、この榊など、カガミナオミの本当の怖さを肌で感じていない人間が、果たしてどこまで相手に近づけるというのだろう・・・。いくら百戦錬磨の凄腕を投入したからといって、簡単にことが済むとは到底思えなかった。
「今回のあんたの判断は間違っている」
香倉がそう言うと、榊はパイプ椅子から立ち上がり、椅子の背に引っ掛けてある薄手のコートを羽織った。
「どうとでも好きなように吼えろ。こっちとしちゃ、キャリア組出身の変り種であるお前を潰す訳にはいかねぇんだ。お前には随分と金をかけてきた。みぃんな国民の血税だよ。そうまでして育てたコマを、みすみすお釈迦にするつもりはねぇ。ここでは三食昼寝つきだ。風呂に入りたけりゃ入れるし、小便したかったら便所にも行かせてもらえる。女が欲しけりゃ上等なやつを俺のポケットマネーで手配してやるさ。ただし、全て見張りつきだ。いいな」
榊はそう言うと、部屋を出て行った。彼は一度も香倉の目を見ようとはしなかった。
再び高速にのって車を走らせた櫻井だったが、途中事故渋滞に遭遇してしまい、目的地に着いたのは、日没時間が過ぎてのことだった。
電話で応対してくれた富樫医師の息子・信弘も帰宅しており、櫻井を出迎えてくれた。
「刑事さんですか?」
相手は、櫻井が挨拶をしたなりにそう訊いてきた。厳密に言うと、辞表が受理されていれば警察官ではない訳で、櫻井としても「警察です」とは名乗らなかったが、なぜか相手の口からは、そんな台詞が転がり出てきたのだった。
「どうして・・・?」
思わずそう呟いた櫻井に、富樫信弘は「あれ? 違うんですか」と意外そうな顔をして見せた。
「うちの病院の患者さんに警察の方が多いもので、雰囲気がよく似てたから・・・。それに20年前のことを訊いてくるなんて、警察の方ぐらいのものでしょ。それこそ昔は随分熱心な刑事さんが何度も親父を訊ねて来られてました」
高橋のことだろう、と櫻井は想像した。事件発生当時、櫻井のために高橋刑事は精力的に動いてくれていたのだ。 櫻井は富樫信弘が案内するままに、奥の部屋まで歩いていった。
「父さん、起きてる?」
「ああ」
予想に反して、しっかりとした返事が障子越しに聞こえてきた。
富樫信弘が障子を開けると、丁度食事が終わったところらしく、信弘の妻がベッドの上に置かれた小さなテーブルから食器を下げるところだった。
「お客さん」
信弘がそう言うと、信弘の妻が富樫久信の耳元で「夕方、話したでしょ。電話の件」と補足した。やっと富樫久信の頭の中でスイッチが繋がったらしい。息子の妻の顔を見て、「ああ、そのことか」と言うと、櫻井の方を見て、「どうぞお座りください。こんな恰好で失礼しますが、足が悪いもので、ベッドから起き上がるのがなかなか大変で・・・」と言う。
寝乱れた髪を手で直している様子を見る限り、厳格で几帳面そうな老人だった。
今でも変らないその目尻の皺に、櫻井は胸元をグッと上から押さえつけられるような息苦しさを感じた。
目の前のこの老人は、自分が過去の犯した過ちの空気に触れたことのある人。今やバラバラに崩壊してなくなった家族の姿を知っている生き証人であるのだ。
「どうぞ、気になさらずに。突然押しかけたのは、自分の方ですから」
櫻井が畳にそのまま正座して言うと、富樫老人が「君江さん、早く座布団をお持ちせんか」と慌てた様子で言った。
君江と呼ばれた息子の妻は、「すぐに椅子をご用意しますね。そちらの方が、話しやすいでしょうから・・・」と部屋を小走りに出て行った。
「何が訊きたいとのことでしたかな?」
ふうと大きく息をついた後、富樫老人は言った。
「父さん、ほら、20年前のことだよ。昔、父さんが主治医をしていた北原さん一家の話」
「ほう・・・」
息子の言葉を聞いて、富樫老人はまじまじと櫻井を見つめた。
「そんなに若いあなたが、20年前の事件のことを訊きにいらしたんですか? 警察の方かね?」
そう訊かれ、再び櫻井が何と答えていいか迷っているところに、君江が籐製の椅子を持ってきた。
「これにお座りください」
ベッドの脇に椅子が置かれ、櫻井は頭を下げながら、その椅子に腰掛けた。富樫老人の息がかかる距離だ。
富樫老人は、目を細めながら再びマジマジと櫻井の顔を見つめる。その険しい表情を見て、息子・信弘は「まぁ、20年も前のことですから、父の記憶も曖昧になっているかもしれません・・・」と言葉を濁す。しかし次の瞬間、富樫老人がきっぱりとした口調で言った。
「信弘、君江さんも、ちょっと席を外しなさい」
父親の突然の発言に、息子夫婦が顔を見合わせる。
「だって、父さん・・・」
過去、刑事が訊きにきた時も、ここまでピリピリとした様子は見せなかった父なのに、どうして・・・という困惑が二人の表情から伺えた。だが富樫老人は、「いいから、早く。お茶も持ってこんでいい」と厳しい口調で言った。息子夫婦は、肩を竦めながら部屋を出て行く。櫻井は二人に頭を下げて、富樫老人と向き合った。その表情を見てピンとくる。
彼は、自分が何者であるか気がついたのだ、と。
「お久しぶりです」
櫻井がそれを見越してそう言うと、富樫老人は懐かしそうに少しだけ笑みを浮かべた。
「やはり、君だったか。随分立派になった」
櫻井は、気恥ずかしくなって俯く。
「その黒子で思い出した。北原さん家の末っ子くんだね」
「その節は、随分ご迷惑をかけたようで・・・。すみませんでした」
櫻井がそう呟くと、「何を言うのかね」と富樫老人は言った。
「実は私も、君の行く末が気になっていたのだよ。だが私は何もできなかった。心残りになっていたんだよ。今どうしているのだろうとね」
「警官をやっていました。あの時お世話になった刑事さんの計らいで・・・。ただ今は事情があって、身分保留というところです」
「それはまたどうして・・・」
櫻井は顔を上げ、富樫老人の目を真っ直ぐに見た。
「ひょっとしたら、テレビで見てご存知かも知れませんが、東京都内で発生している殺人事件に、自分の姉が関与している疑いがあります。自分にも、姉の行方や動機が分からずにいるのです。調べていくにつれ、姉の過去・・・いや、自分の家の過去に向き合わねばならないことに気がつきました。だから今日、ここにお邪魔したのです」
富樫老人は、すっと身体を引くと、腕組みをして長く息を吐き出した。
「あなたは、昔自分の家の中で隠されていた秘密を知っているのではないですか? 父や母が腫れ物のように扱っていた姉の秘密を。それを教えて欲しいのです」
櫻井が詰め寄っても、富樫老人は唸るだけで、渋い顔を見せた。
「しかし・・、そのことを君に今話しても、正実ちゃんの居場所が分かるとは到底思えないがね・・・」
医者としての守秘義務が引っかかっているのだろう。生真面目な富樫老人の血には、未だに優秀な医者としてのプライドが流れている。だが、それを押してまでも、今の櫻井には必要な情報であった。例えその秘密が空振りであったとしても、姉が今何を考え、何を思っているかを探るヒントになりえるかもしれないのだ。そして何より、自分の家族のこと、呪われた血筋のことを自分はきちんと知るべきだと櫻井は思っていた。
今まで、罪の意識の中、自分の過去を「背負う」ことはやってきた。だが、「向き合う」ことは決してなかった。無意識のうちに、そのことから逃げてきたように思う。だからこそ今、それに立ち向かわねばならない。そうでないと、自分は乗り越えられないと思った。
「お願いします。・・・これまでに、たくさんの人が傷ついてきました。事件の被害者を始め、加害者である犯人も姉か姉に関係している人間に操られ、彼らの人生を失いました。そればかりか、自分の同僚の精神や彼の妻のお腹にいた子供の命まで・・・。それもこれも、自分がきちんと自分の過去と家に向きあってこなかったせいだと思うのです。姉は自分にこんなメッセージを残しています。『私のことが分かる?』と。正直、自分には、姉という存在が分からない。そう訊かれても、分からないのです。思い出の中の姉はいつも優しくて、自分のことを気にかけてくれていた。そんな姉が、どうして今になってこのようなことをするのか、自分にはまったく分からない。その答えを得なければ、問題は解決しません。必死なんです」
櫻井は、切々と訴えた。正直な気持ちだった。
富樫老人は、しばらくの間櫻井をじっと見詰めると、再びうーんと唸り声を上げた。
だがやがて、ぽつりと口を開いた。
「・・・君のお姉さんを今のようにしてしまったのは、私や君の父、母であった北原ご夫妻のような大人達のせいなのかもしれない」
富樫老人は目の縁を擦り、呟く。
「君の純粋さが、心に痛みを与える。いつの時も犠牲になってきたのは、君のような人なのだね。すまない」
「そんな・・・。富樫先生のせいでは・・・」
櫻井がそう返すと、富樫老人は首を横に振った。
「臭いものに蓋をすると、よく言うでしょう。あれは、大人のための都合のいい言い訳なのだよ。私も昔、君のお父さんやお母さんと結託をして、蓋をしてきた。そのつけが、今になって噴き出しているに違いない」
臭いものに蓋をする・・・。今朝方、同じような台詞を香倉の口から出るのを聞いたばかりだった。
本来明かされるべき真実を、己の保身のために無理やり押し込めようとする大人。そこで歪んだ真実が、やがていびつな形の悲鳴を上げ始める・・・。
「ひょっとしたら、今起きていることは、私にも責任があるのやもしれん。だが今の私には、ただ語る力しか残されていない。それを思うといたたまれないが、今の私にできる精一杯の方法だ」
そういう富樫老人の震える手を櫻井はぐっと握った。富樫老人は、力のない笑みを浮かべ、掠れた声で語り始めた。
「君のお姉さんは・・・」
触覚 act.36 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
さっきまで背後のテレビで、「筋肉、筋肉」と連呼されてました(笑)。
なんてことなはい、テレフォン・ショッピングなのですが、寝不足の頭には、やたら「筋肉」という単語ばかりが耳について、なんだか笑えちゃいます。
なんせ「触覚」の裏テーマは「美しい筋肉」っすからねぇ~(笑)。
国沢、もっと書けよ、筋肉、とテレビに言われているような気分になってしまいました。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
