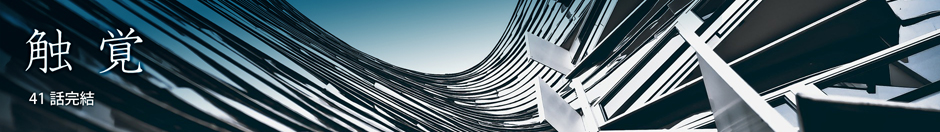
act.35
大石に啖呵を切って監察医務院を後にした香倉だったが、正直何の不安もないと言えば嘘になった。
自分が立ち向かおうとしている相手が、どれほど危険な人間であるかということは、大石に言われなくても十分に分かっている。
科学では解明できない人間の恐ろしい悪の力が、この事件を終わることなく支配し続けているのだから。
勿論、香倉だって過去そのような事件に出合った事はない。これまで数多くの様々な経験を積み重ねてきたが、今回のような「得体の知れない恐怖」を感じるのは初めてのことだった。
香倉とて、自分が完璧な人間でないことは知っている。相手に付け入る隙があることも確かだ。普通の人間ならば、心の何処かに何かしらの悲しみや罪を持っているはずである。
だが、それだからこそ尚更許せなかった。
負けるわけにはいかないと思った。
ひょっとすれば、自分の力なんて足元にも及ばないかもしれない。抵抗するよりもなによりも、端からそんな次元の話ではないのかもしれない。
だが、負けるわけにはいかないのだ。
警官としてのプライドと、そして何より深い傷を背負うことになった櫻井のために。
実際、兄の言うことは正しい。人に手を差し伸べるということは、その人の傷をも一緒に背負い込むこと。そしてその覚悟ができない限り、人を本当に救うことなんてできないこと。
そう言われ、香倉は迷った。珍しく自分に苛立ちを感じて、うろうろと病室前を歩き回った。自分を試されているような気がして、居心地が悪かった。
「お前の人生をかけてまで救わねばならない人なのかな? 人生のギリギリを何とか生きている彼に手を差し伸べることとは、つまりそういうことだ」
だが、兄のこの言葉を思い起こした時、香倉は決心をしたのだ。
櫻井は、自分の人生をかけてでも救うべき人間なのだと。
櫻井は昔の自分だった。その生い立ちが似ていたせいだけではない。暗闇を手探りで生きてきた苦しみ。そしてそんな生き方を選んできたお陰で、背負わなければならなくなった孤独。ただひたすら正しく生きようとしてきた人間が、どうしてこのような仕打ちを受けねばならないのか。
お前を支えてやる言ったのは、本心からだ。今までそんな言葉、誰にも言ったことはない。それまで支えてやりたいと思った人間はいた。だが、実際に言葉に出して、それに魂が篭ったのは、あの時が初めてだ。
不器用だが、必死にしがみ付いてきた櫻井。
そのぬくもりを救うことが、自分の孤独をも救うということを肌で知った瞬間だった。
自分は、逃げる訳にはいかない・・・。
香倉の足は、自然と例のマンションに向かっていた。
車は櫻井に貸していたので、監察医務院まではタクシーできた。
香倉は周囲を見回す。だが、平日の昼間、人通りの全くない裏道ではタクシーは通りかからない。とにかく大通りに出ることが先決だ。
香倉がそう思った矢先、携帯電話が鳴った。
立ち止まり、懐から電話を取り出す。着信の番号を見ると、榊からだった。
『おい、例のねぇちゃんのマンション。こっちで押えたからな』
電話に出るなり、あのだみ声がそう告げた。
「押えたって?」
榊の動きの素早さに正直驚いた香倉は、「どういう権限で押えたんです?」と厳しい口調で続けた。
『権限も何もあるか。大石の事件は表向きだけだったとしても無事解決。それならこっちは遠慮する必要がないだろう。こっちはこっちであの議員の件で無関係ではないんだ。お前が言ったことだぞ』
それは榊の本意ではないと思った。いくら公安でも、そんな無茶な押え方はしない。不自然すぎる。大石のケースを閉めたものの、不安に思った幹部連中が弱腰になって榊に取り付いたか。いや、そんな可能性は低い・・・。何より、榊の声に余裕が感じられないことが気に掛かった。それは香倉だからこそ感じえる程度のことだったが。
「何を企んでいるんです?」
と言いながら香倉は背後を振り返った。黒塗りの車が、香倉の側まですーと近づいてくると香倉の横でピタリと止る。
ドアが開いて出てきたのは、中年の表情のない二人の男。サラリーマン風の印象の薄い男達だった。
彼らの顔を見た瞬間、香倉は全てを悟った。
「大石ですか。大石が、あの写真のことを」
受話器の向こうから鼻で笑う音が聞こえてきた。
『残念。不正解。ブーだ。写真のところまではあっているがな』
ピンときた。
「河瀬さん」
香倉がそう口に出すと、榊がふふふと笑った。
『公安のサラブレッドをみすみす潰すつもりかと痛い言葉を言われたぞ。部隊の管理をお前はどうしているのかとな』
榊にそんな口を叩けるのは確かに河瀬しかいない。警視総監でさえ、榊には一目置いているのだ。
『もっとも、河瀬さんもお前のじゃじゃ馬振りはご存知だ。河瀬さんの優しさだと思え。本日よりお前の身柄を拘束する。写真のことを知っているお前だ。異存はないな』
「今更ケツまくれっていうんですか? あわよくば相手を確保できる可能性だってある。異存だらけですよ」
『可能性はこの際問題ではない。俺はリスクの高すぎる取引はしないし、お前が相手の手に落ちてみすみす殺されることを選ぶなら、この俺が殺してやる。いいか、その連中には殺してでも連れて来いと言ってある。観念しやがれ』
香倉が抗議する前に電話は切れた。
「チクショウ」
香倉がそう呟いた瞬間、青白い電流がバチバチと音を立てるスタンガンが香倉の背中に押し付けられたのだった。
櫻井は、廃墟となった実家を出て、近所の旧家を聞き込みしながら回った。
警察手帳を持っていない櫻井だったが、身体に染み付いた刑事以外の何者でもないその雰囲気のお陰で、手帳を見せずとも不審に思われなった。
聞き込みをした旧家の中には、櫻井が子供の頃に見知っていた家もあったが、どの家も櫻井が昔近所に住んでいた少年であるということは気づかない様子だった。なにせ20年も昔の話だったし、櫻井の質問内容が昔ここら辺一帯の家の主治医をしていた医者についての質問であったがために、櫻井の過去とは結びつかなかったようである。櫻井も敢えてそのことは言わず、ただ淡々と片足の悪い医者の行方を訊いて回った。
結局、数軒の家から聞いた情報で、片足の悪いその医者は、名を富樫といい、10数年前に隠居をして開業医である息子夫婦の家に越して行ったとのことだった。
息子が経営する病院は櫻井の家のある町にはなく、聞き込みをしたどの家もその病院のことまでを知っている者はいなかった。
櫻井はその町の中心街にある電話局に向かい、その町周辺の電話帳を調べることにした。通常の捜査活動でもよく行っている方法である。
だがあいにくと、町の周辺にも富樫と名のつく病院はなかった。櫻井は、他の数冊の電話帳を手に取ると、もう少し調べるエリアを広げてみることにした。
おぼろげに空腹感を覚えだした頃、電話帳のナンバーを辿る櫻井の指が止った。
「あった」
隣の県の電話帳に富樫内科クリニックという名前を見つけた。
早速櫻井は、その病院に電話を入れてみる。
電話を掛けた時間帯が丁度午後の忙しい診療時間帯であったがためにしばらく待たされたが、やがて富樫内科クリニックの院長・・・つまりあの足の悪い医者の息子が電話口に出た。
櫻井が20年前のことを訊くと、息子はその頃のことをよく覚えていた。幸運なことに彼の父親は現在ベッドの上の生活を強いられていながらも元気にしており、息子夫婦の家で暮らしているという。おそらくボケてもいないから、あなたの訊きたいことは教えてもらえるのではないだろうか、と好意的な答えが返ってきた。
息子に自宅の住所を教えてもらい、これから家を訪ねることに対して了解を取ると、息子は、家で父親の介護をしているという彼の妻に連絡をいれておくと言ってくれた。
20年前、大人達は姉に何をしていたのか。何を隠していたのか。
この人ならば、その秘密を知っているに違いない・・・。
櫻井は、手近にあった電話のパンフレットに書き付けた『富樫久信』の名前を見つめてそう思った。
触覚 act.35 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
ねむいです。流石に。ただいまちなみに、4時44分。笑えます。
まるで駄目押しをされているようです。深くは突っ込みたくないですが。
とか何とか言いながら、こんなにも仕事が恐ろしいことになっていうrのに、結構気分的にのほほんとしている国沢です。
年齢を重ねるということは、いい意味でも悪い意味でも、落ち着きという名の「ひらきなおり」精神を培ってくれることなんだなぁと実感してます。
しかしそれにしてもなんだろう。この気楽さは。 こんなに切羽詰ってるのにね。
仕事の状況よりも、この妙に落ち着いた気分の方が怖かったりする・・・。 や、やはり楽天的・・・?
そうか?そうなのか?!
と、とりあえず寝ます。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
