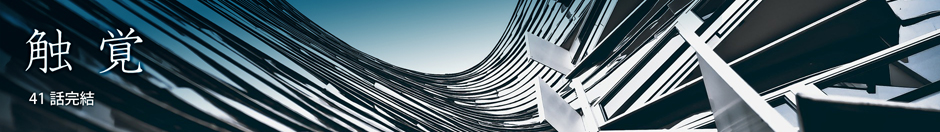
act.05
その日の仕事が終わり、櫻井は井手が在籍している坂出メンタルクリニックを訪れた。
井手は現在、東京拘置所にいる中谷の精神鑑定を引き続き行っているはずだった。
坂出メンタルクリニックは、会社帰りのサラリーマンでも通院できるようにと遅くまで開いている。
受付で「潮ヶ丘署の櫻井です」と名乗り、井手の所在を訊いた。
「井手先生は、ただいま外出中です」
こんな時間まで、仕事をしているらしい。中谷の件だろうか。
「連絡を取りたいのですが・・・」
こざっぱりとした顔つきの受付嬢は、冷静な瞳で櫻井を見上げてきた。果たして井手に連絡を取っていいかどうか値踏みしているのだろう。
じっと黙って佇んでいる櫻井を見て、受付嬢は無表情さをそのままに、電話の受話器を取った。
井手の携帯電話にでもかけているのだろうか。しばらくして、井手が電話に出たらしい。
「お忙しいところ、すみません。ええ、そうです。はい。櫻井様という方が来られています。先生とお会いしたいと。・・・そうです。警察の方です。・・・はい、はい。判りました」
受話器を置いて、受付嬢はメモ用紙にあるところの住所を書き込んだ。
「先生は、そこにおられます。直接来られてもいいと」
手渡されたメモを見て、櫻井は思わず受付嬢の顔を見た。
「・・・ボクシングジム・・・?」
「ええ。場所は、おわかり?」
櫻井は、もう一度メモを見る。判らないではない街の名前だった。
「ありがとうございます」
櫻井は礼を言って、クリニックを出た。
メモ書きで渡された住所にあるボクシングジムは、すぐに判った。
ボクシングにはあまり興味のない櫻井でも、少しは聞いたことのあるジムだった。
井手はここで何をしているのだろう。
今度世界チャンピオン戦に挑戦するというボクサーのメンタル面をサポートしているのか。
櫻井は半信半疑のまま、ジムの扉を開けた。
広いジムは、活気に満ち溢れていた。ジムの中央にはリングが構えられ、室内には、様々な音が響いていた。板張りの床に、縄跳びの縄が当る音。叩かれるサンドバックの重い音、きしむ柱の音。男たちの荒い息づかい。コーチ達の怒鳴り声。
櫻井が周囲を見渡して、入口の近くに立っていた、ジムの名前が印刷されたTシャツを着ている男に声をかけた。坂出メンタルクリニックの井手さんは、こちらにいらっしゃいますか、と。
男は、櫻井を興味本位の表情で見てから、ジムの奥の方に向かって大声を上げた。
「井手さん! お客さん!」
櫻井が、男の視線を追って奥に目をやる。
いくつものサンドバックが揺れる間から、白いTシャツに黒のスパッツを履いた井手の姿が見えた。櫻井は、ぎょっとする。判ったという合図がてらに振り上げられた井手の手には、赤いグローブが填められていたからだった。
「考えが纏まらない時には、ここにこうして来るのよ」
ジムの片隅にあるプラスチック製のベンチに腰掛けながら、井手は微笑んだ。
首にかけたスポーツタオルで顔の汗を拭う。
「座ったら」
下から見上げられて、櫻井は少し頷いた。少し距離をおいて井手の隣に腰掛ける。
井手は、ベンチの傍らに置いてあるミネラルウォーターのボトルを手に取ると、グラスに注がず、そのままラッパ飲みした。
櫻井はその横顔を見る。
井手は大きく息を吐き、横顔を向けたまま言った。
「意外? 女がサンドバック殴ってるの」
「いえ・・・、そんな・・・」
俯く櫻井に、井手がニヤリと癖のある笑みを浮かべる。
「精神科医に嘘は禁物。あなたは、解りやすいわ」
そんなこと、生まれて初めて言われた。櫻井が顔を上げる。
「最近では、流行ってるのよ。女の子がボクシングするの。健康的に痩せられるし、ストレス解消になるんだって。そんな映画も、公開されたしね。このジムは、プロを目指している人が中心だけど、中にはダイエット目的のサラリーマンや、鬱憤晴らしのOLも来るわ。私はもっぱら、考え事をする時にここに来る」
井手の言うことに耳を傾けながら、櫻井はジムを見回した。確かに、ちょっと太り気味の中年男性の姿も見える。
「でも、私もここに通い始めたのは最近のことよ。友達に勧められて」
「友達?」
井手が、顎でリングを指した。「赤い方」と呟く。
赤と青のヘッドギアをつけた大柄な二人の男が、激しく打ち合っている。
ジムのスタッフ数人が、リングに向かって掛け声をかけている。時折「チャンピオン」と聞こえ、どうやら打ち合っている男の一人は、今度世界に挑戦するミドル級の日本王者であるらしい。櫻井が見る限り、グレイのTシャツを身に付け、赤いギアをしている選手の方が優勢だ。どうやらそれがチャンピオンらしい。
背格好からして、リングの男が、いつか見た「井手の男」であるのは明白だった。
ヘッドギアのせいで顔はよく見えないが、そうに違いない。
自分の女に、ボクシングを勧めるなんて・・・。ボクサーとはそういうものか。
櫻井は変に納得した。チャンピオンであるからこそ、あんな高級そうなマンションに住めているのだろう。
しかし、井手の恋人がプロボクサーだったとは。
ふいに赤いギアの男が放ったアッパーに、青いギアをつけた男がもんどりうって倒れた。倒れた男は、起き上がる気配すら見せない。10カウントを数えなくても、赤いギアの男の勝利は明らかだった。
「あ~あ、バカじゃない、あいつ」
井手が横で呟いた。櫻井はその意味が分からず、井手を見る。
「珍しくムキになっちゃってさ。よほどあのチャンピオンのことが気に入らなかったのね」
え? と思い、櫻井は再度リングを見た。数名のスタッフが顔を青くしてリングに上がり、倒れた男のもとに駆け寄っている。一方、赤いギアをつけた男は、見るからにこのジムの最古参コーチと目される初老の男と話をしながら、肩を竦めていた。
「世界戦間近のチャンピオンをのしちゃうだなんて。いい大人が、大人気ないことをするわ」
井手はそう言いながらも、クスクスと笑っている。
赤いギアの男が、グローブを外して、ギアを取った。
汗が流れ落ちる横顔は、正しくあのマンションで見た男に違いなかった。
「香倉!」
井手が大きく声を上げた。
リングの男が、こちらの方を見る。
香倉と呼ばれた男は、微笑みを浮かべている初老のコーチに肩を叩かれながら、リングを降り、井手の隣に腰掛けた。
「あなた、何考えてるの?」
笑いが堪えられない井手が、男にミネラルウォーターのボトルを手渡した。
男は、ボトルに口をつけず、器用に水を喉に流し込んだ。
軽く息をつき、汗まみれの頭を振る。汗が床に滴り落ちた。
「あっちが誘ってきたんだ。俺は誘いにのってやっただけ」
「それはそうだけど。挑発にのることはないじゃない。大切な試合前に、しがないクラブのバーテンに負けたとなると、その精神的ダメージは相当なものよ」
「しがないクラブのバーテンに負ける方が悪い。所詮、それだけの実力ってことさ」
男はそう言ってクールな表情のままとぼけて見せたが、櫻井には、香倉という男の実力が只事ではないということに気がついていた。
櫻井とて、伊達に柔道三段ではない。畑が違うとはいえ、男の動きは隙がなく、完璧だったことは十二分に判った。本当に「しがないクラブのバーテン」なのか。
櫻井は、男を観察した。
以前は遠目だったので詳しくは見えなかったが、男はまさに「いい男」だった。
大柄だが、身体は引き締まっていて、動きにキレがある。汗に濡れた横顔は、鼻梁が高くて彫りが深い。涼しげな目元は鋭く、魅力的だ。Tシャツに丈の長いボクサーパンツというラフな出で立ちにも関わらず、大人の男の色香が溢れている。吉岡の言っていたことは、間違いない。女なら、「むしゃぶりつきたくなる」いい男だ。
「そっちの坊やは? お前の新しい男か」
櫻井に横顔を見せたまま、男が言った。
「違う。そんなんじゃないわ。・・・刑事さん」
男が、初めて櫻井を見た。目が細められる。
「ああ、あの刑事さんか」
どうやら男は、二週間ほど前のニュースを覚えていたらしい。
ふっと微笑を浮かべられ、櫻井はどきりとした。
この人は、本当にただのバーテンなのかと、櫻井の本能が警告を発していた。
「こちら、私の中学・高校時代の友人、香倉裕人。そしてこちらは、潮ヶ丘署の櫻井・・・」
井手が櫻井を見る。
「正道です。正しいに道と書きます」
櫻井は答えた。「正しい道か・・・」と香倉が小さく繰り返す。
「で、その正義感溢れる刑事さんが、何の用事で?」
ゴシゴシと頭をタオルで拭きながら、香倉が言う。
櫻井は、気まずそうな目線を井手に送った。香倉が、櫻井と井手を交互に見る。
「邪魔者は退散するとするか。そろそろ、店の時間だからな」
香倉が立ち上がる。ジム中の視線を浴びつつ、そんなことは少しも気にとめない風情の香倉は、ジムの奥にあるロッカールームに消えて行った。
「すみません、何だか・・・」
「いいのよ。あいつと私の間は、いつも無礼な感じなの。腐れ縁なのよ」
クスクスと井手が笑う。少なくとも、ここで見る井手は、警察署の中で見る井手とはまったくの別人だった。仕事中の井手は、まさに鉄の処女であるが、今櫻井の目の前にいる井手は、そのクールさは消えていないものの、人間味に溢れている。あの腐れ縁友達のせいか。
「で、本当に何の用事? ここまで一人で来るんだもの。何か訳ありなんでしょう?」
櫻井は頷いた。
「人に殺人を犯させるまで心神喪失状態に追い込むということは、可能だろうかと思って・・・」
「今度の連続殺人事件ね」
井手は、あえて「連続殺人事件」と言った。
厳密に言うと、犯人は全く別の人物だから連続ではないのだが、あの二つの殺人事件は、明らかに繋がっていた。
「厳密に言うと、不可能。小説でも、ある人間を洗脳して殺人兵器を作るというシュチュエーションがあるらしいけど、そこまでできるのは、精神世界によほど精通している人間でないと。心理学のトップ、山田建夫博士でさえ、かなりの条件が整わないと、そこまでの暗示にかけるのは難しいでしょう」
「じゃぁ・・・」
「でもね」
櫻井の台詞を切って、井手が言葉を続けた。
「人間の感情を高めることは可能よ。その人自身が持っている感情の暴力的な部分を高めて、自分の操りやすい方向に持っていく。人間さえ選べば、その方法で犯罪を犯させることも可能かもしれない。洗脳して、まったく関係のない人間を殺していくように仕向けるのは難しくても、元々あった感情を煽り立てて、その人間の価値観や道徳観を麻痺させることは、十分にできうる」
井手は、前かがみになって、膝の上で両手を組んだ。
「今回の黒幕は、そういう人物だと思うの。人間の一番弱い心を突いてきて、自分の手を汚さず殺人を楽しむ、卑怯な人間。あなた達が探し出すべき人間は、そんな奴よ」
人間の心理に深く入り込み、人間の欲望を操る人間・・・。
櫻井は、ふと自分の父親のこと思い出した。
思い起こした父親の顔は、まさしく人間の欲望に満ち溢れていた・・・。
賑やかな夜の繁華街の片隅。 ビルとビルの谷間の空間は、表通りの喧騒が別世界のように、暗く沈んでいる。
時折輝くネオンの光に照らされたその空間に浮かび上がる、二つの影。
縁なし眼鏡にグレイの三つ揃えといういでたちの男と、対照的に漆黒のタキシード風の身なりをした男。
タキシードの男が、細身の煙草をスーツの男に勧めたが、スーツの男は手でやんわりとそれを断った。タキシードの男が肩を竦める。
「キャリアのお偉方は、煙草を吸ってちゃ出世できなかったな」
「厭味を言うな」
スーツの男は少し笑った。ネオンの光に青く照らされた男の顔は、警視庁捜査一課の管理官・大石だった。
「よもや、公安のお前が俺に情報を流してくれるとはな。意外だったよ」
そう言われた男は、何も答えずゴロワーズを吹かした。
「早いものだな。お前が潜入捜査を始めて、どれくらいの月日が経つ」
「・・・さぁ・・・。8年か・・・いや9年・・・かな」
「9年か。お前が公安に配属されて以来、ろくにお前と酒も飲めん。おまけに偽名でお前を呼ばねばならん。それが公安の慣例とは言え、些か滑稽にも思える」
もっとも、それが公安らしさだが。と大石は言葉を切った。
警視庁公安部は、警察機構の中でも最も謎の多い部署として存在している。主に赤軍などのテロ集団の検挙や破壊活動を起こす可能性の高い集団を犯罪を犯す前に押えるという役割を果たしている。最近では、スパイ活動を行っていた外交官を、公安部が仕留めた話題が新聞にも掲載された。
警察関係者の中でも公安の詳しい活動内容について判っている人間は少なく、実際にどのような事件の捜査に関わっているかも詳しくは明らかにされていない。
政治犯が少なくなった現代、恐らく公安の果たす役割も様変わりしているだろう。大石の目前の、涼しい顔をした男も、その謎の一部なのだ。
「先日の、あの国家機密漏洩事件。あのヤマにも、お前が絡んでいたんだろう? あの産業スパイだった企業幹部は、聞けばお前の会員制クラブにもよく顔を出していたそうじゃないか」
男が、ちらりと大石を見た。ニヤリと笑う。
男は否定も肯定もしなかったが、男の表情を見るだけで十分だった。
「よもや、同じクラブに、今巷を騒がせている二人の殺人犯も、通っていたとはな」
大石の台詞を聞きながら、男は煙草を落とし、よく手入れされている革靴で踏み消した。
「しかし・・・なぜ。・・・なぜ情報を流したんだ。部長の許しがあってのことではないだろう。いいのか、そんなことをして」
男は、ビルの薄汚れた壁に、身体を預けた。スラックスの両ポケットに手を突っ込む。
「いずれ、判ることだと思ったからさ。捜査担当の責任者であるお前に、先に情報をリークしておけば、少しは俺の立場も考慮してもらえる」
大石が、眉を引き上げる。
「まさか・・・、会ったのか、あの刑事に」
察しのいい大石が口を開いた。
「確か、櫻井正道と言ったな。・・・正しい、道と書く」
男にしては珍しく、おどけた口調だった。
「・・・そうか・・・。取調室で何か思いついたような顔つきをしていたが、まさか、そんなに早くお前のところに辿り着くとは」
「いいや。偶然さ。あの若い刑事はそこまで気がついていないだろう。彼は井手に会いに来たんだ。俺に、じゃない」
「なら、なんで」
なんでかなぁ・・・と男は呟いて、空を見上げた。
しばらくの沈黙が、二人の間に流れた。
「なぁ・・・、お前、どう思う」
ふいに大石が口を開く。
男は、視線を上に上げたまま、「何が」と訊いた。
「櫻井のことだよ」
男が、大石を見た。
「奴は問題行動が多い。問題といっても、客観的に見れば、人を救うため。そんな純粋な動機によって、平気で危険行為を行う。命令もそっちのけだ。どんな奴かと調べてみたら、成績は優秀。非の打ち所がない。益々興味がそそられて、奴の査問員会に無理やり加えさせてもらった。本人に会ったら、驚くほど大人しくてな。物静かな男だった。ただ、怖いくらいに目が澄んでいて・・・。あれが、警察に何年間も勤めてきた男のする目つきかと思う。奴はよっぽど馬鹿なのか、それとも馬鹿を演じている賢者なのか・・・。正直、俺にも判らん。あの目で、何を考えているのか・・・」
男が、壁から身体を起こした。
「奴は、この世の誰よりも、人間、なのさ」
「え?・・・」
男が、大石に横顔を見せる。
「人間の良心だけを盾にして、驚くほど純粋に生きていやがる。だから、『痛く』見えるのさ。濁ってしまった俺達のような人間にはな」
この世には、まだまだ純粋な気持ちを貫いて生きようとする人間がいる。
そう言えば一年前、そんな奴らに出会ったな・・・。
男は、無性に口惜しくなった。
誤魔化すように、新しい煙草に火を点けたのだった。
触覚 act.05 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
ついに、ついに、アニキしゃべりました!!!
本当に、本当に長らくお待たせをいたしましちゃいましたね(汗)。なんか、もうひとつの方とボクシングネタかぶってますけど、許してください(大汗)。
そして、アニキの「飛び道具」、いかがだったでしょうか。
奴は、警察官だったんですねぇ! しかも、非合法活動もこなす、潜入捜査の達人。
すげぇ、おいしいよ。おいしすぎるよ、にいさん!
国沢もこの設定を思いついた時には、鳥肌が立ちました。なぜか(笑)。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
