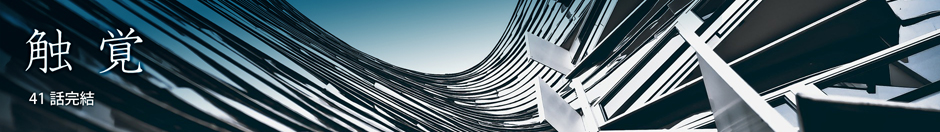
act.02
<第2章>
分かっている・・・分かっているんだ、いつだって。
男は、焦っていた。
早く実行に移さないと、自分の方が押しつぶされてしまうと。
腕時計のタイマーが鳴ったことが合図だった。
そう、自分が新しい自分に生まれ変われるチャンス。
曲々しい束縛から、解放される時。
男の身体中を、甘い衝動が駆け巡る。
この先の角を曲がれば、あの女がいつも利用している喫茶店がある。
この時間は、近所の暇と金だけ有り余っている中年女連中と、実のならない話に花を咲かせているはずだ。
急げ・・・急げ・・・。その時は近い。
脳髄の向こうで、あの声がする。
早くしないと、自分がダメになってしまうよ。あの女に、負けてしまうよ。
ねぇ、あの女は、本当にこの世に必要なの?
男は、小走りに喫茶店のドアまで近づいた。
ドアを開けると、目標はすぐ近くにいた。
「あら、由紀夫。どうしたの? こんな時間に。あなた、お仕事は?」
午前中の間に美容院できれいにセットしてもらった女の銀髪が、嫌にギラギラと輝いて見えた。
男は、女の言ったことに一言も答えなかった。
代わりに、果物ナイフを女の喉に突き立てたのだった。
誰もいない早朝の柔道場。
清らかな朝に光が差し込む畳張りの部屋に、青年の荒い呼吸音と、それに混じって数を数える声が響く。
壁際の横柱に黒帯を結わえ付け、櫻井正道は一心不乱に背負い稽古を行っていた。
櫻井が黒帯を肩越しに引く度に、柱が悲鳴を上げ、汗が飛び散る。
櫻井は、口で大きく息をしながらも、淡々とした表情で数を数え続けていた。顔の傷も目立たなくなり、身体の方も左上腕の包帯のみで後はかさぶたがこびりついている程度だ。
腕の傷は既に抜糸されていて、主治医の和泉から「あまり無理はしないように」と言われているが、毎日欠かさず行っている朝稽古をしないでいると、若い身体が鈍って仕方がなかった。謹慎処分を受け、何もせずに独身寮の部屋にいると、考えたくないようなことまで考えてしまって、どうしようもなくなる。
腕の傷は痛かったが、櫻井の持つ心の傷は、更に深かった。
常に櫻井には、自分の過去に犯した過ちに対する負い目があり、それがいつも彼を捉えて放さないでいた。だがしかし、その「負い目」が、今の彼を支えているのも事実である。
身体の中にたまった泥は、常に浄化させなければならない。人は様々な方法で、泥を吐く。酒に逃げる者。恋人に縋る者。家族に救われる者。櫻井の場合は、自分の身体を極限まで痛めつけることがそれに当った。一心不乱に稽古をし、びっしりと汗をかく。これ以上、呼吸ができないというところまで身体を酷使する。
家族とというものを失い、今まで独りで生きてきた櫻井にとっては、そうするしか方法がなかったのである。
「・・・99・・・、100!」
掴んでいた帯を放し、膝に両手をついて肩で大きく息をした。
はぁ、はぁと息を吐く度に、畳に大粒の汗が流れ落ちる。
櫻井は、深呼吸しながら右手を見た。
丁度、手のひらと手首の境目にあたる部分。手の部位で最も硬いその部分に、今もくっきりと残る痣。小型ナイフの柄の先が押し付けられたような形。
その痣を見る櫻井の瞳に、一瞬悲しみにも似た複雑な色が浮かんで消えた。
突然、道場の入口の扉が開く。
「おい、櫻井」
宿直明けの吉岡だった。櫻井が汗塗れの顔を上げる。
「正式に謹慎が解けたぞ。汗流して、早く着替えて来い」
最後に大あくびをしながら、吉岡はタオルを入口横のベンチに置いて行ったのだった。
謹慎は、結局8日間だった。
怪我もほぼ回復し、稽古に出ている櫻井の様子を聞いて、高橋が本庁に働きかけたらしい。強行犯も少人数であらゆる捜査に当っている。優秀な人手がほしいのは事実だろう。
久しぶりにネクタイを締め、スーツに袖を通す。
そして刑事課に入ると、まず「スター選手のご帰還か。いい気なものだな」という厭味の先行パンチを食らった。
櫻井と同じ強行犯係の戸塚だ。櫻井より2つ年上。吉岡の一年後輩に当るが、如何せん警察大学校出のキャリアで、しかもその中の落ち零れときている。階級で言えば、課長の高橋と同じ階級を持っていたが、大学時代から問題行動が多かったせいか、約束通りの出世コースには乗れず、今だ所轄の刑事課でくすぶっている。そのせいか、自分より後輩のしかもノンキャリである櫻井が、処分付きではあるが所謂「手柄」を立て、皆の脚光を浴びることが腹立たしくて仕方がないのだ。戸塚の場合、櫻井の真似をしようとしても、いつも裏目に出て、その失態をいつも吉岡にからかわれている。厭味のひとつやふたつぐらい言わないと、やっていられないのだろう。
「ご迷惑をお掛けしました」
櫻井が深々と頭を下げると、その先を続けられなくなったのか、戸塚は「まずは課長に謝れよ」と席を立って姿を消した。
櫻井は、自分のデスクで新聞を読みながら煙草を吹かしている高橋の前に立ち、再度頭を下げた。
「ありがとうございました」
高橋は、ちらりと櫻井の顔を見て、再び新聞に目を落とす。
「傷はもういいんだな」
「はい」
そうかと高橋は呟いて、新聞を捲る。
「通常業務に戻れ」
櫻井は頷いて、自分の机についた。上着を脱いで椅子にかけ腰を下ろすと、背中越し、吉岡がボールペンで櫻井の脇腹を突っついてきた。
「なぁ、櫻井。今晩、飲みに行かねぇか」
櫻井は、顔だけ吉岡の方に向けた。
「吉岡さん、宿直明けでしょう。・・・帰らないんですか」
「帰るよ。帰るけどよ・・・」
その様子を見て、櫻井は思い当たった。
「また喧嘩・・・」
櫻井が呟くと、吉岡は櫻井の視線を逃れるようにしながら、口を突き出した。ぼりぼりと無精ひげを掻く。
結婚4年目にしてようやく子宝に恵まれることになった吉岡だったが、最近妻の小夜子がマタニティーブルーに入っているとかで、よく喧嘩をしているらしい。
「いいんですか。小夜子さん、待ってるんじゃぁ・・・」
櫻井がそう言いかけた時。
課内入口ドアの上部に取り付けられたスピーカーから、けたたましいブザーの音が響いた。
『ただいま、井上町1丁目、カフェ・ド・セーヌより110番通報あり。60歳前後の女性が男に刺されたとのこと。現在被害者は病院に搬送中。被疑者は現在も逃走しており・・・』
櫻井と吉岡は互いに声を掛け合うこともせず、椅子の背の上着を掴むと、黙ったまま同時に刑事課を走り出た。背後では、関係各所に命令を下す高橋課長の重厚な声がだんだん小さくなっていく。
吉岡と櫻井は、既にお互い何も言わなくても勝手に身体が動くようになっていた。それは刑事課の他の面々も同じだった。
二人は受付で潮ヶ丘の腕章を受け取り、署内に入ってくる人込みを掻き分けながら外に飛び出して行った。
マスコミは、この一週間の間に、某有名企業の開発部において国家機密レベルの情報が国外に漏洩していた事件が発覚したせいで、こちらの熱はすっかり冷めてしまっていた。署外には、既に彼らの姿はなかった。
吉岡と櫻井はタクシーに乗り込むと、現場の住所をつげた。
まさかこれが、すべての奇怪な殺人事件の序章になることも気づかずに。
吉岡と櫻井が現場に到着すると、既に現場は黒山の人だかりで、二人は強引に野次馬を掻き分けて黄色いテープを潜った。
現場は、高級住宅地の外れにいかにもありそうな洒落た喫茶店だった。櫻井の生活とは縁がなさそうな、「カフェ」という代物だ。
昼食前のこんな穏やかな気候の日に、有閑マダムが集う気取った雰囲気の店内で、よもや殺人未遂事件が起こるなど誰も想像しなかっただろう。
店内には既に鑑識班が入っており、刑事達はそれが終わるまで中に入ることは出来ない。櫻井が喫茶店の入口から現場を覗き込むと、入口に比較的近い左側のテーブルに多量の血痕が血だまりを作っており、テーブルに置かれたクリーム色の食器類には、粘ついた血がまとわりついていた。そして溢れ出した血は、テーブルの脚を伝い床にまで滴っている。櫻井が目線を上げると、周囲の白い壁や観葉植物にもおびただしい筋状の血痕が飛び散っているのが見え、被害者の刺された箇所から、いきおいよく血液が吹き出たことを現していた。被害者は大動脈を切断されたに違いない。櫻井が想像するに、多分被害者は助からないだろう。
櫻井がそう思った矢先、パトカーの無線機から被害者の死亡が伝えられ、この事件は殺人未遂事件から殺人事件へとスライドされた。
「あれ?」
様子がおかしい事に気がついたのは吉岡の方だった。
「機捜の連中が少ない」
吉岡にそう言われて櫻井も「あ」と気がついた。
通常、パトカーで華々しく現場に最初に到着する私服警官は、特別機動捜査隊である。事件の初動捜査は彼らが担当し、現場の確保から通報者への事情聴取、目撃者の有無の確認等を行い、殺人事件等の重大事件はやがてその現場を管轄している所轄署に特別捜査本部がたてられる。所轄署の刑事は機捜の連中が許可を出すまで黙って見ているしかない。
だが、吉岡が言う通り、いつも現場で幅をきかせている機捜の連中の頭数が今日は少なかった。
第一通報者である店長や友人の血を正面からまともに浴びたらしいご婦人の事情聴取も、一人の刑事がまとめて行っている。
吉岡は、群集から少し離れたところに立つ馴染みの新聞記者の姿を見つけ、機捜の連中から背を向けて話し掛けた。櫻井も後に続く。
新聞記者は吉岡に頭を下げ、そして櫻井の顔を見て少し驚いた。
「あれ、櫻井さん、もう復帰してるの?」
頭の薄い体格のがっちりしたその新聞記者は、愛嬌のある表情を浮かべ大げさに驚いて見せた。
「そんなことはいいからさ、現場、どうなってんの? 最初から居たんだろ?」
吉岡が焦れると、新聞記者は真顔に戻った。
「犯人捕まえに行ったのよ」
「え?」
「犯人、ガイシャの息子だったのよ。母親の喉下刺して、皆が呆気に取られている間に店を出て姿を消したんだけど、それから後どうなったと思う?」
「だから、さっさと教えろよ」
「返り血浴びたまま自分の会社に戻って、仕事してたのよ。普通の顔して」
そこまで聞いて、吉岡と櫻井は顔を見合わせた。
「犯人を乗せたタクシーの運転手と会社の同僚から110番通報が丸の内署に入って、名前が一致したから犯人だろうと。ってことで、機捜の旦那達は連れ立ってオフィス街にひとっとびさ。今頃もう捕まえてんじゃないの? うちも若手がそっちに行ってるよ」
奇妙な事件だ。
櫻井はそう思った。いや櫻井だけではないだろう。吉岡や、この話を聞いた誰もがそう感じるはずだ。
犯人が犯行現場で取り押さえられて緊急逮捕というのは良くある話だ。だが、今回のように犯人が現場から逃走した場合、犯人は身を隠そうとするのが常で、事件発生直後に身柄を拘束することは難しい。幼稚な少年犯罪のようなケースは別として。
しかしそれにしても薄気味悪い話ではないか。
人・・・それも自分の母親を刺し殺した後、何食わぬ顔をしてタクシーに乗り込み会社に帰って、血まみれの顔のままキーボードを打っていたなんて、気味が悪い。
嫌な事件だ。
櫻井はそう思った。
「結局、特捜たつ暇もなかったな」
吉岡が新聞を畳みながらそう言った。その新聞のトップには、昨日スピード解決した殺人事件を「真昼の惨劇」と騒ぎ立てて取り上げている。もちろんテレビも昨夜からこの事件を取り上げていて、潮ヶ丘署ロビーはまたもや騒がしくなった。
この事件の異常性は、最早すでに証明されている。マスコミの注目度も高く、現に今犯人の取調べは通常の段取りとは違う方向で進み始めていて、それだけでも警察および検察関係機関の焦りが伺えた。
現在、犯人は潮ヶ丘署の取調室で本庁の刑事達が調書をとっていて、高橋課長とベテランの川口刑事が立会いをしているが、先ほどそこに検察庁のやり手検事まで呼び出された。おそらく、犯人の精神状態がネックになっているのだろう。
果物ナイフで、喉元を一突き。 櫻井は、吉岡の置いた新聞を横目に見ながら、なんとも言えない気分になった。
その瞬間、フラッシュバックする映像。 裂ける肉。激しく顔に打ち付ける血液。苦しそうにもがく口。床に転がった、血塗れのナイフ・・・。
「おい、櫻井」
吉岡に身体を揺さぶられた。はっとして櫻井は、吉岡に目線をやる。
「大丈夫か、お前。顔、真っ青だぞ」
櫻井は静かに、大丈夫ですと呟いた。
と、例の取調室のドアが開いて高橋課長が顔を出した。手で櫻井を呼ぶ。何か言おうとした吉岡をやり過ごして、櫻井は席を立った。
櫻井が取調室の前まで行くと、高橋は緊張した面持ちで言った。
「精神鑑定になる。もうすぐ鑑定官の先生が来るから、裏口で出迎えてやってくれ。名前は、井手靜だ」
「精神鑑定? ・・・ここで、ですか?」
「そうだ。頼んだぞ」
ドアが乱暴に閉められる。少し垣間見えた取調室は、重苦しい空気に包まれ、異常に汗を掻いた犯人の病的に見開かれた目が見えた。
よっぽどのことだ、と櫻井は思う。
大抵の場合、精神鑑定は、被疑者の身柄が検察庁の管轄である拘置所に移されてから行われる。検察庁から委嘱された鑑定官が数時間診断を行った後に出される簡易鑑定が最も多く、それでも診断が難しい場合は、診断期間の延長などの措置が取られる。その結果を踏まえて、起訴できるかどうかを検事が検討するのだ。・・・つまり、罪に問えるかどうかが判断される。
だから、今回のように被疑者の身柄がまだ警察にある状態にあって、検事立会いの元で精神鑑定が行われるというのは、異例といえるだろう。よっぽど焦っているのか、ただならぬ状態なのか。
この異常な事態に、櫻井は鳥肌が立つのを感じた。
櫻井が署の裏口に至る階段を下りると、狭いガラス戸越しに白いセダン車が車止めに入ってくるのが見えた。すぐさまドアが開いて、中からすらりとした姿の女性が現れた。
純白で細身のパンツスーツにスレンダーな身体を包み、癖のなく長い黒髪を後ろできつく縛っているその姿は、まさしく「颯爽」としている。女の顔は、色白ではっきりとした顔立ちの美人だったが、その鋭い光を宿した瞳が、彼女をただの女でないことを物語っていた。
裏口にも張り付いていた記者達は、彼女の登場が何を意味するのか、即座に理解したらしい。素早く女に近づいたが、櫻井が女の前に立つ方が早かった。
櫻井の厳しい一瞥で記者達が一瞬怯む。その間に櫻井は女をエスコートして署内に入った。
「・・・ツワモノの記者達を一瞥で怯ませる若い刑事なんて初めて」
署内に入った途端、女が口を開いた。
「犯人逮捕のためなら自分の身体を平気で犠牲にするだなんて若い刑事も初めて」
櫻井は振り返った。女の口調は冷たく醒めたものだったが、その目は笑みを浮かべていた。
「勝気な若い刑事なんて憎たらしいぐらいにたくさんいるけど、君の場合はただの勝気で済ませてしまっていいのかしら?」
櫻井がなんと答えていいか分からず戸惑っていると、女が手を差し出した。
「坂出メンタルクリニックの井手です。よろしく」
櫻井はなるだけ躊躇いを見せずに女の手を握った。女の手は細かったが、握り返してくる力は強かった。
「お待ちしておりました、井手さん。潮ヶ丘署刑事課の櫻井です。本庁の捜査員が先生をお待ちしています。こちらへどうぞ」
櫻井は井手の少し前を歩きながら、刑事課へと急いだ。
ふと背後の靴音が気になって少しだけ振り返る。
女はハイヒールを履いていなかった。まるで男が履くような色気のないローファーを履いている。よく見れば、アクセサリーと言った類のものも一切つけていないし、化粧もしていないようだ。
井手が櫻井の視線に気がついたらしい。先ほどと同じ薄い笑いを再び浮かべた。
「仕事に女は持ち込まないようにしてる。特に刑事事件が絡んでいる仕事は。私の性が、接見者の気を惑わすといけないので」
しかし井手はそれでも十分洗練されていて美しかった。女性的な美しさというより、透き通った氷のような美しさがあった。
櫻井と井手が刑事課に入ると、取調室から出てきた担当検事と本庁の刑事が二人井手を出迎えた。
「お待ちしておりました、先生」
「被疑者に接見する前に、彼に関する客観的なデータをください。それから、犯行時と逮捕された時の状況報告も合わせて。被害者のデータもいただけるとありがたいわ」
的確な要求と隙のない口調。こういう話し方をする女性を嫌う男達も多いだろう。現に頭を下げている本庁の刑事達の表情には苦々しいものが含まれている。人間の反応に敏感な櫻井には、それがすぐに分かった。
事件に関する書類を受けとって、井手は刑事課に隣接する応接室に案内されて行った。
櫻井が自分の机に戻ると、机の上に足を投げ出して座っていた吉岡が口笛を吹いた。
「まさかあの井手靜が出てくるとはな」
「吉岡さん、知ってるんですか?」
「知らないお前の方が潜りだっつーの」
ま、お前はいつも被害者のことしか見てないからなと吉岡が呟いて、机から足を下ろした。
「井手靜、33歳。独身。検察庁の連中が絶対的な信頼を置く坂出メンタルクリニックの稼ぎ頭。隙のない的確な観察眼と綿密な分析力。精神医学界でも期待のホープで学会の信頼も厚い。大学に付属していない医療機関に所属していながら、学会での彼女の評価は特別だ。加えてあの美貌。様々な業界の実力者が誘いをかけているようだが誰にも靡くことがない。噂によると、男嫌いだって話になってる。あだ名は"鉄の処女"」
吉岡の話を聞きながら、櫻井は刑事課から見える応接室のガラス窓を見やった。
ブラインドの隙間越し、熱心に資料を読む井手の白い横顔が見える。
吉岡がボリボリと頬を掻いた。
「一年前の板橋での立てこもり事件覚えてるだろ。18歳のガキの事件」
「ええ。確か、刑事責任を追及できると有罪になった・・・」
櫻井が吉岡に向き直る。その間吉岡は、応接室に目をやっていた。
「あの事件の精神鑑定を行ったのが井手靜だ。弁護人側が立てた著名な精神科医の判定結果を真っ向からひっくり返しやがった。検察にしてみれば、涙がちょちょ切れたろう。彼女の仕事には、それだけの説得力がある」
その井手が、今回の犯人のあの目を見て一体どう思うのだろう・・・。
櫻井は、静かな瞳を再び応接室に向けた。
触覚 act.02 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
いかがだったでしょうか。ようやく(といっていいものかどうか・・・)、殺人事件発生です。仕事師の男達(この場合、刑事ですが)が、言葉を交わさなくても、互いの職務を寡黙にこなしていくっていうシュチュエーションに萌えるのは、国沢だけでしょうか?
働く男は美しい! それで優秀だったらりしたら、めちゃカッコいい!
といいつつ、でも今回は、「働く女」がでてきました。33歳、いまだ独身! 井手靜。「働く」というよりは、「戦う」という言葉が似合う女。いいんでしょうか、精神科医が、こんなにバトルして(笑)。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
