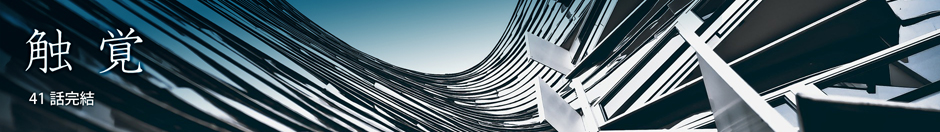
act.13
<第8章>
カチカチと電気が瞬いて、青黄色い蛍光灯の光が質素な室内を照らし出した。
潮ヶ丘署内にある待機所の一室。
櫻井の部屋は、およそ飾り気というものがなく、他の若手警官達の部屋と比べて、些かガランとした空間が広がっている。
八畳一間にクローゼットと簡単なキッチン。いわゆるワンルームというやつだ。だが、畳張りの古びた部屋は、お世辞にもワンルームとは言いがたい。若い警官達は口を揃えて不平を言い合ったが、櫻井はそんなことを口にしたことはなかった。
櫻井はクローゼットの扉を開けてハンガーを取り出し、扉の裏についているフックにそれをぶら下げた。
上着を脱ぎ、ネクタイを首から抜き取る。シャツのボタンを二つ外したところで一息ついた。
今日は本当に一日中資料室に監禁されていたも同然だった。身体を動かすことはなかったが、それがかえって身体の疲労感を呼んでいた。
櫻井は、扉の裏の小さな鏡に映る壁掛け時計に目をやった。八時を過ぎている。急がねば。
櫻井は、ワイシャツを脱いで床に落とした。スラックスも脱いで、クローゼットから取り出したカーキ色のチノパンに履き替える。そして素肌の上に白のTシャツを着た。その上から、黒の薄手のウィンドブレーカーを羽織る。
クローゼットの戸を閉め、電気を消すと、櫻井は自室を出て鍵をかけた。
待機所には特に門限はなかったが、食堂の世話もしている管理人に一言出かける旨を伝えなければならない。
櫻井が吉岡の家に招かれていると言うと、管理人夫婦は笑顔で「行って来なさい」と見送ってくれた。吉岡も結婚する前はこの待機所に住んでいたのだ。
待機所を出て、潮ヶ丘署の裏門に回ると、マスコミの記者らしき人間が数人見えた。
今世間の注目を浴びている事件の犯人が署内に留置されているのだ。皆あわよくば少しでもいいからスクープをモノにしたいと思っているのだろう。
厄介だな・・・。
櫻井は裏門から出ず、その左手にある特殊車両車庫と塀の間を歩いた。突き当たりにある身長より随分高い塀を軽い身のこなしで飛び越えて、細い路地に出る。路地の先には公園があり、周囲に張られている金網を登った。勢いをつけて向こう側に飛び降りる。記者たちは、櫻井がまんまと彼らの目を盗み、署外に出たことにはまったく気づいていない。
櫻井は、膝についた砂をパタパタと軽く払い、何食わぬ顔で大通りに出たのだった。
吉岡の家は、潮ヶ丘署からさほど遠くない。
緊急時の出勤に備えてと、吉岡が選んだ一戸建ての借家だった。
学生時代からずっと付き合っていた小夜子と吉岡が結婚したのが四年前。その時既に、潮ヶ丘署の刑事部屋にいた櫻井は、吉岡の結婚式にも招待された。
櫻井が現在の課に着任した当時から、櫻井の無愛想面のどこが気に入ったのか、吉岡は何かと櫻井を気にかけてくれる。だから、櫻井が仕事のことで落ち込んだりしている時は、必ず家に招いてくれた。確かに、吉岡の温かい家庭で過ごす時間は、櫻井にとっても心安らぐ一時であった。
木造二階建ての家のドアベルを鳴らすと、すぐさまドアが開いた。
「いらっしゃい」
小柄で色白の女性が顔を覗かせる。その穏やかな笑顔を見て、櫻井は、やはり吉岡が妻の機嫌の悪さを理由にして自分を招いたことがウソだと知る。だがそれは、吉岡流の優しいウソだ。
「今晩は。すみません、遅くなって・・・」
吉岡の妻・小夜子が大きなお腹をかがめてスリッパを取ろうとするのを素早く遮って、櫻井は自分でスリッパを出した。
「ごめんなさい。思うように動けないの」
身体を起こしてフウと溜息をつく小夜子の腕を、さりげなく支えてやった。
「もうすぐですね」
と櫻井が言うと、小夜子は笑顔を浮かべた。幸せが滲み出るような笑顔だ。
「予定日はまだ二ヶ月半ぐらい先なんだけど・・・。よく動くのよ。触ってみる?」
「えっ」
櫻井は少し躊躇ったが、小夜子が「どうぞ」と大きなお腹を向けてきたので、そっと手を這わせてみた。
「蹴ってるの、判る?」
「・・・はい」
自然と櫻井の表情が朗らかになった。手を通じて、小さな、それでも力強い振動が断片的に伝わってくる。櫻井は、不思議な感覚に包まれた。ここに、本物の生命が宿っている・・・。
櫻井は小夜子と顔を合わせ、にっこりと笑った。
滅多に浮かべることのない櫻井のそんな表情を見て、小夜子は安心したように頷き、「すぐにご飯の準備をするわね」と言って、櫻井を奥のリビングに導いた。
恐らく小夜子は、吉岡から櫻井の今の状況を聞かされていたのだろう。言葉には出さなかったが、二人の優しさが身に沁みた。
リビングに入ると、丁度二階から降りてきた吉岡と出くわした。
「おお、来たか。俺も今、帰ってきたところだ」
紺色のTシャツにグレイのスウェットという寛いだ恰好をしている。
吉岡は、冷蔵庫から缶ビールを二本出して、リビングのソファーに座る櫻井に投げてよこした。
吉岡は、櫻井の向かいに腰掛けながらビールを開ける。
「今日は、川口のじじいに掴まって大変だったそうだな」
吉岡は、刑事課の最古参・川口刑事をじじい呼ばわりして、よく怒られている。それでもまだしぶとくじじい呼ばわりしている吉岡がおかしくて、櫻井は俯いて少しふき出した。
「何がおかしいんだよ」
口調は憮然としたものだったが、顔は笑っている。
二人はしばらく黙ってビールを飲んだ。カウンターキッチン越しに、小夜子のせわしなく動くスリッパの音が響いた。煮詰まった味噌の芳ばしい香りがする。幼い頃から、家庭料理というものに縁のなかった櫻井だが、無性に懐かしい気分にさせられた。
ご飯の炊ける匂い、喉に落ちていくビール、何気なくつけられたテレビから漏れる笑い声・・・。ここには、本物の幸せがある。
「すみませんでした。ご心配をお掛けして」
そんな台詞が櫻井の口をついて出た。素直な気持ちだった。吉岡が櫻井を見て、少し鼻を啜った。
「別に、心配なんかしてねぇよ。これしきのことで潰れるお前じゃないよな」
口調はいつもの乱暴な物言いだったが、その瞳は真摯だった。櫻井は頷く。頷いて、迷いのない笑顔を向ける。
「オヤジのことも、許してやってくれ。どんな腹づもりがあるか解らないが、あれはあれでお前のことを思ってのことなんだ」
吉岡の言うことは十分判っていた。もし自分が高橋の立場だったとしたら、自分でもそうする。
櫻井は、夕べ香倉の部屋であの名を初めて耳にした時より、幾分冷静に考えることができるようになった。
北原正顕が、この事件に関わっているということについて。
その先を考えるのは、自分にとって確かに見てはならない世界なのかもしれないけれど、自分は見ずにいられないことを・・・。
だが、吉岡にはそのことを黙っていようと思った。
いずれは吉岡も知ることになるのだろうが、今はまだいい。必ず、時は熟す。それまでは、吉岡に余計な心配はかけたくない・・・。
「とにかく、事件のことは俺に任せろ。あの事件以外にも、俺たちの課には、やらなきゃらならないことは五万とある。あの事件だけがすべてじゃないさ」
櫻井が何も答えず、俯いて唇を噛み締めていると、吉岡があははと笑って櫻井の肩を乱暴に叩いた。
「少しは俺の顔も立ててくれよ。たまにはお前みたいに手柄を立ててみたいのさ。・・・な、だから、安心して事件のことは任せてくれ。いいな」
「吉岡さん・・・」
「いいな」
櫻井が、何とも複雑な心境で吉岡を見つめた時、小夜子がお盆を持ってリビングに入ってきた。
「難しいお話はそこらへんにしたら。ご飯の支度ができたから、温かいうちにどうぞ」
リビングのローテーブルに、小夜子が温かい手料理を配膳する。
さばの味噌煮に大根のサラダ、白菜のおひたし。吉岡の田舎で漬けた梅干に油揚げの味噌汁・・・。
どれもが、身体に染み込む食事だった。おいしいというよりは、ありがたい、そんな言葉が櫻井の脳裏に浮かぶのだった。
「また来てね。本当は、毎日でも来てもらっていいのよ」
「バカ、そんなこと言ったら、本気でコイツ、毎日来るぞ」
「あら、いいじゃないの。ねぇ、櫻井君」
「聞くな、櫻井。俺だって愛を育みたい時があるんだ」
「やだ、何言ってるの、この人」
ふたりのそんなやり取りに笑いながら、櫻井は吉岡家を後にした。
食事の後、風呂までごちそうになって、後は吉岡とレーシングゲームをして遊んだ。何レースしても櫻井に適わないと見るや、吉岡は「ビール、ビール!」と口を尖らせた。
吉岡さん、明日大丈夫なのかな・・・。
思わず櫻井は真剣に心配になり、早々に立ち去ることにした。
ある程度のところで終わりにしないと、とことんまで甘えてしまいそうになる。
櫻井は自分の心の弱さを悔いたが、どうにもできなかった。
そのまま寮に帰ろうと思ったが、足は素直に動いてくれない。
一人暗く静かな道路に放り出されると、途端に自分の孤独さが身に沁みた。
人気のある方へと足が向き、気がつけば電車に乗り、夜遅くてもなおネオンが瞬く繁華街に降り立っていた。
太ももぎりぎりのミニスカートで手を繋ぎながら歩く女の子達。酔いどれ顔で肩を組みながら叫び声を上げるサラリーマン。道端で座り込み、声を掛け合う若い男女。けたたましい笑い声、騒がしい客引き。眩いばかりの光の渦・・・。
そこにあるものは偽者の笑顔だらけだったとしても、今の櫻井にはどれもが幸せそうに見えた。この世に必要とされていないのは、自分ただ一人なのではないかという思いに捕らわれた。
特捜を外され、自分の存在価値を見失い、そして自分の忌まわしい過去が現実のものとなって再び目の前に迫っている。
あの人は、夢の中で何度も言った。 血まみれの喉をヒューヒューと鳴らしながら、何度も自分にこう言った。
『許されるとでも思っているのか』
そんなこと・・・ちっとも思っていないさ。
だからこそ自分は今、茨の道を歩んでいる。
それが嫌であるなら、自分で人生を終わらせることはできた。楽な方法はいくらでもあったし、そうするチャンスもたくさんあった。・・・でも自分はそれをしなかった。
自分は罪人だと心に刻み、少しでもこの世に生まれてきた意義を見出す為に、今の職業を選んだ。ひとりでも多くの弱き人たちを救いたかった。それが、自分をも救うことになるのだと信じるしかなかった。
本音を言うなら、逃げてしまいたかった。警察なんて、過去を思い起こさせるような仕事を選ばず、できることなら普通に、心穏やかに生きたかった。
だが、自分は逃げることを止めた。それが精一杯の贖罪だった。
・・・なのにあんたは、これでもまだ足りないというのだな。
どうしても、この俺が潰れてしまうまで、許してはくれないのだと言うのだな。
独りきりでいることで、もう十分じゃないか。
孤独に人生を送ることで、もう十分じゃないのか。
俺の心も身体も、独りで生きていく術しか知らない。そうとしか生きることができない。 独りでいることがどんなに辛いことかも知らないくせに、これ以上何を求めているというんだ・・・。
気づけば、通り過ぎていく人々が奇異の目を櫻井に向けていた。最初はどうしてだか判らなかったが、やがて自分がぼんやりと涙を流していることに気がついた。
櫻井は慌てて涙を袖で拭い、近くのビルの谷間に身体を滑り込ませた。
店の裏口にある小さな水道の蛇口を捻って、頭から水を被った。
排水溝に溜まったゲロの悪臭に閉口し、すぐに水を止め、頭を乱暴に振った。
ビルの合間から、通りの喧騒が聞こえる。
その世界から、自分が孤立した存在である思いは、頭から水を被ったって、決して拭えるものではない。
どうして・・・。
櫻井の中で、何度も繰り返される疑問。
どうしてなんだ、父さん。
なぜに「今」でなければならなかった。
なぜに関係のない人間の人生をメチャクチャに破壊していく。
壊すなら、直接俺自身を壊せばいいじゃないか。
俺を壊すだけなら、簡単にできる。
父さんは、その方法を知っているはずじゃないの?
それとも、それをしないだけの憎しみがそこにあるの?
どこからか、低く呻き声を上げる人間の声が聞こえた。
でもそれは、自分のはらわたから押し出されてきた嗚咽だった。
櫻井は、水滴をぽたぽたと落とす髪の毛を両手で鷲づかみし、その場に蹲った。
心が、張り裂けそうだ。いっそのこと、誰かこのまま、自分の身体を引き裂いて欲しい。
自分のこの命ひとつで、こんな悪夢が終焉を迎えてくれるのなら、喜んで差し出してやる。だから、どうか・・・。
触覚 act.13 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
お笑いテイストだった先週にくらべ、今週はかなりヘビーです。櫻井君ひとりになると、こうなっちゃうのかしら(汗)。
ついに泣いちゃいましたね、彼。でもしょうがないです、つっぱって生きてたって、人間ですもん。(書いてる本人がそんなこと言うな?)
これから彼がどう強くなっていくのか、どう人生の難所を乗り越えていくのか、国沢にとっても楽しみ(という言い方は正しいのか?)です。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
