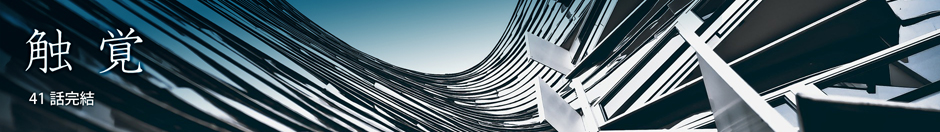
act.25
<第13章>
平日のデパートは、都心といえども客足は鈍い。銀座の一等地にあるこの百貨店も休日と比べれば閑散としていた。
一階に設けられた化粧品コーナーも例外ではなく、どの化粧品メーカーのコーナーもカウンセラー席に一人か二人の客が座るのみで、比較的ゆったりとした・・・というよりはっきり言ってしまえば暇な状態であった。
その男の客が外国の某有名化粧品メーカーのコーナーに姿を現したのは、夕刻に近い時間である。
「すみません、口紅の新色を見せてもらえますか?」
色白で文句なく美しい容姿をしたその男は、丁寧な口調で店員に声を掛けてきた。
店員は、さりげなく男の全身を観察した。品定めである。
男は黒の上下に赤のTシャツをあわせていた。大きな黒いカバンを持っている。一目見てどれも高級ブランドの一品であることが分かった。男の身体は華奢である。その身のこなしはエレガントで品があり、さしずめいいトコのお坊ちゃんといった風情であった。
「はい、少々お待ちください」
店員は最上級の笑顔を浮かべると、カウンターの後ろから口紅のサンプルディスプレイをとって男の前に並べた。
男は春の新色を代わる代わる手にとって眺める。手馴れた様子だ。
彼女へのプレゼントだろうか。だとしたらこの男、相当の伊達男ね。
店員は顔には出さないものの、じっと男を観察し続け、心の中で思った。
男というものは、女がどんな口紅をつけていようとも大抵は無頓着だ。だが女にとって、新しいシーズンが来るごとに発表される化粧品は常に重要な問題であり、手元にいくら口紅を持っていても、新作で評判のいい口紅はいつの時も欲しいものなのだ。それを彼氏から、「君に似合う色だと思って」とか、「君にはこの色をつけて欲しいんだ」だなんて言われながらプレゼントされれば、どんな女もイチコロだろう。
素敵ねぇ・・・。
店員は目を細めながら溜息をついた。男に話し掛ける。
「プレゼントでございますか?」
「え? ええ・・・、まぁ・・・」
男が顔を上げる。不思議な瞳の色をした青年だった。真っ黒く張りのある髪。少し長めの前髪が頬にかかって、肌の白さが余計に強調されている。髭は薄いのだろうか、彼の陶器のような滑らかな肌には、髭の剃り跡も見えない。薄く色づいた唇。すらりとした鼻梁。長い睫。
この男の彼女は、意外なところで苦労するかもしれない。なぜならば、並みの女より男が美しいからだ。吸い込まれそうな瞳の色をしている。
男の手元には、ローズレッドの口紅とオレンジレッドの口紅があった。どちらか迷っているようだ。
「贈られるお相手は、どのような感じの方ですか?」
店員がそう訊くと、男は「そうだなぁ・・・」と少し考えたあと、「ボクと同じ顔をしています」と答えた。
「え?」
ぎょっとして店員が訊き返すと、「ボクの妹の誕生日プレゼントなんです」と言って少し笑った。
ああ、なんだ。そういうことか。
店員は顔を赤らめながら「それでしたら・・・」とローズレッドの口紅を勧めた。
男とよく似ているのだとしたら、寒色系の色の方がよく似合うと思った。男の肌は、日本人特有のオクールとはまったく違う、白人のように透けるような白い肌だったからだ。
「ああ、そうですね。この方が彼女らしいかもしれない」
男はそういうと、「これを包んでください」と言った。
「メンバーズカードはお持ちではないですよね」
店員は、会計を済ませながら訊いた。
普通なら、男の客にメンバーズカードの誘いは掛けないのだが、この男にはまた来て欲しかった。
「特典割引もありますし、妹さんにもご利用いただいて構いませんから、ぜひ」
半ば強制的に、カードへの記入をさせた。
男は、繊細な文字で『南川直志』と書き込んだ。
南川直志は、化粧品コーナーで商品を受け取ると、さっさと上のフロアに移動した。
エレベーターに乗り込み、紳士服売り場で降り立つと、テナントが並ぶフロアには出ず、真っ直ぐトイレを目指した。
紳士服売り場のトイレは通常利用客が少ない。
南川は、よどみない足取りでそのまま女子トイレに入った。
鏡の前で髪を直す女性客と目があった。
普通なら「失礼、間違えました」と言って出て行くものだろうが、南川はただ黙って女の顔を見つめ続けた。瞬きもせず。
南川の顔を見た女性客は、一瞬不快そうな顔つきをして大声を出そうとしたが、ものの数十秒もしないうちにぼんやりとした表情を浮かべ、何事もなかったかのように再び鏡に向き合ったのだった。
南川は、口元に謎めいた笑みを浮かべると、トイレコーナーとは別に構えられているパウダーコーナーに向かった。一流デパートともあって、座り心地のいい椅子と大きな鏡、広いテーブル、明るいライトが揃えられているパウダーコーナーを南川は気に入っていた。
本来なら、自宅を出る時から化粧や着替えを済ましておきたいのだが、周囲の住人達の目もあり、そういう訳にはいかなかった。どこで誰に見られているかもしれない。
さきほどのように、面と向かって対面した相手なら、どのようにでも操ってしまえるのだが、自分の気づかないところでの人の目はどうしようもない。こんなに手間のかかるようなことになったのも、警察のせいだ。まったく、腹立たしい。
南川は、テーブルの上にカバンを置くと、中から化粧道具と女物のスーツ、ウィッグなどを出して広げた。
その間にも、女性客が南川の存在に何の疑問も持たない表情のまま、出て行く。
南川は、ウエットタイプのクリーニングシートで目に見えない顔の汚れを拭き取ると、化粧下地から念入りに顔に伸ばし始めた。
その動きは無駄がなく、落ち着いている。
また入口の方で人の気配がする。
南川がそちらに顔を向けると、掃除婦だった。
掃除婦が南川の存在に気づき、「あ」と声を上げる。
南川は再び、女をじっと見つめた。女の目が、ぼんやりとしてくる。南川の口元が微笑を浮かべると、掃除婦は「失礼しました、お客様、ごゆっくりお使いくださって構いませんので・・・」と言っておくのトイレコーナーの掃除を始めた。
南川は、軽く会釈すると、再び化粧の続きを始めた。
鏡の中の男が、みるみる美しい女性へと変貌していく。
南川は、最後に小さな箱を手に取った。
ついさっき購入した口紅だった。
包みを開けて、早速唇にのせた。
店員の睨んだ通りだ。
実際そのローズレッドの口紅は、鏡の中の女によく似合っていた。
その日の夜。夕方に深い眠りを得たせいか、櫻井は素直に寝付かれなかった。
ベッドに横たわり暗がりに包まれた天井を見つめていると、様々な感情が去来しては櫻井を押しつぶそうとする。
失われた命の重さ。我が子を失った母親の痛み。心神を喪失してまで我が子の身体の断片を離さなかった父親。そしてそれらを取り巻く人々の深い悲しみ。
自分は父親を殺そうとして、愛を与えまた与えられるはずの人々を自ら手放した。
自分の生き方は本当に正しかったのか?
本当に、これでよかったのか?
いや。
そんなはずがない。そうでないからこそ、今再び、今度は無実の人々が巻き込まれているのだ。血の宿命に。
窓の外を行く風のヒュルヒュルとした音が、小声で話す人の声に聞こえる。
櫻井は布団を被った。堅く目を閉じた。
凶器へと変質した幼い頃の記憶は、今もなおじわじわと燃えつづけ、消えることを知らない。多分、自分自身がこの世から消えない限り、この炎も消えることはないのだ。もはや記憶は、自分を形成する重要な一部であり、その記憶の上に自分というものが存在しているのだから。
『お前の血が、不幸を呼び覚ますのだ』
再び父の声が耳元でした気がして、櫻井は両手で耳を塞いだ。
これからどうすればいいか判らない。 どう生きていけばいいのか判らない・・・。
オーディオの上に置かれてあるデジタル時計は、いつしか二時を示していた。
櫻井はベッドから起き上がった。
眠れないのにベッドを占領しているのは気が引けた。
リビングに出ると、ソファーの上で香倉が眠っていた。
側に近づくと、目を閉じたまま「眠れないのか」と彼は言った。
「・・・はい。すみません・・・」
香倉が身体を起こす。
「別に謝ることじゃない」
寝乱れた髪を掻き上げながら香倉が言う。
「どうかベッドで寝てください。どうも寝つけそうにありませんから」
床に座り込む櫻井を、香倉は静かに見つめた。
「嫌なことを思い出すのか」
櫻井は、力のない苦笑を浮かべる。それを見ながら、「ま、当然と言えば当然だよな」と香倉が溜息をつく。
「どんなことを考えてる? 言ってみろよ」
櫻井は、両目の下を親指の腹で擦って鼻を啜った。
「判りません。・・・・本当なんです。もう、どうしていいか判らないし、自分が何かも判らない。今日腕を傷つけた時のことも、正直、よく覚えていないんです。単純に、父親を刺したこの腕をこの世から消し去りたかったのかもしれません。いや・・・自分の存在自体を消し去りたかったのか・・・」
膝を抱え、櫻井はぼそぼそとしゃべった。香倉は、ローテーブルの上の煙草を手に取ると、火をつけて吹かした。香倉はただ黙って聞いていた。
「自分の存在が人を傷つけるためにあるのだとすれば、俺にとって自分という存在は、生きるに値しない。これまで、それを胸に秘めて生きてきました。自分の中に渦巻く汚い部分は、全て押し殺して、そうしなければならないと、いつも言い聞かせてきました。それが、償いだと思ったからです。苦しい生き方を選ぶことで、罪が浄化されることをいつも願っていた・・・。でも、それは間違いでした。罪など、消えるはずがない。この手が・・・いや、俺がこの世にいる限り、俺の記憶がある限り、罪は消えない。この世には、罪を犯す人間とそれを赦す人間、そしてそれを赦せない人間が存在する。・・・俺の罪は、赦されない。赦すことができないと、父が言っています」
櫻井の目から、小さな涙の粒がポロリと零れ落ちた。
「・・・こんな生き方は、辛い。あなたが言ってくれた通り、俺はずっと一生懸命だった。一人きりで、耐えれるまで耐えてきました。それなのに・・・それなのに・・・。まさか、まさか吉岡さんまで、あんなことに・・・!」
父親を刺してから20年。初めて人前ではっきりと吐露した弱音だった。今まで、どうしてもできなかった。誰もそこまで、櫻井には近づけなかったからだ。
香倉は、煙草を灰皿に押し付けると、蹲る櫻井を静かに見つめてぽつりと言った。
「逃げるか」
「・・・え?」
櫻井が顔を上げる。
「何もかも忘れて、誰の手も届かないどこか遠いところへ。一緒に」
香倉の哀しげな目がそこにあった。櫻井は涙を溜めた目を大きく見開き見つめた。
それは甘い甘い誘いだった。それができたら、どんなにかいいだろう・・・。
しかし櫻井は、首を横に振った。
「・・・できません・・・。できません、自分には・・・。俺のせいで傷ついた人をそのまま置いていく訳には・・・」
「その言葉を聴きたかった」
「え?」
櫻井が香倉を見る。香倉が目を細めて見つめていた。
「お前にまだ、そういう気持ちがあるのなら、勝機はまだある。今この現状から逃げ出しても、きっとお前は自分の本質から逃げることはできないだろう。この状況を克服しない限り、お前は前に進めないんだ」
「香倉さん・・・」
「お前ならやれる。できると信じろ。事実お前は、できるんだ。普通の人間なら、とっくの昔につぶれてる。だがお前は生き抜いてきた。その力は、お前の財産なんだよ。記憶はお前を傷つけるためにあるんじゃない。お前を勇気付けるためにあるんだってことを忘れるな」
櫻井は、しばらく何も言えずに香倉を見つめた。
香倉の言葉が、ひび割れて血まみれになった心に浸透していく。
櫻井の目に、新たな涙が浮かんで、零れた。
自分の吐く息、心臓の音、指先のぬくもり。それを全て今正当化されたような気がした。
「俺・・・、生きていても、いいんですね?」
「ああ。そうじゃないと、俺が困る」
櫻井が怪訝そうに眉を顰めて顔を傾ける。香倉はさりげなく櫻井から視線を外して言った。
「実はまだ、鍋の中にチキン料理が結構残ってるんだ」
その香倉の言い草に櫻井がふふふと笑った。やがてその笑い声は大きくなり、彼は満面の笑みを浮かべて笑った。実に若者らしい、あどけない笑顔で。
香倉も、それにつられて笑う。そうしてしばらくの間、深夜だというのに、男二人で笑い合った。
触覚 act.25 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
次回はもう、新年明けてですね!
とかなんとか言いながら、皆さん、有意義なクリスマスを過ごせたでしょうか。
国沢は、何だかんだいって、仕事でした・・・。
まさにクリスマス死ね死ね団に入団できます、国沢も。
それはさておき(消えろ!クリスマス!!←実は根深いか?)、次回は、国沢渾身の一発(というと語弊がありそうですが)の回です!
ひょっとしたら、国沢だけが盛り上がってすんじゃうかもしれない!!
ひょっとして、国沢、次回登場のシーンだけを書きたいが為に、「触覚」を書き始めたのではないかしら・・・とも思ったりします。(と、あおっておいて、実際は大したことないんですけど)
ぜひ、次回、国沢の入魂シーンをお楽しみに。 (いや、ホントに大したことないんですけど)
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
