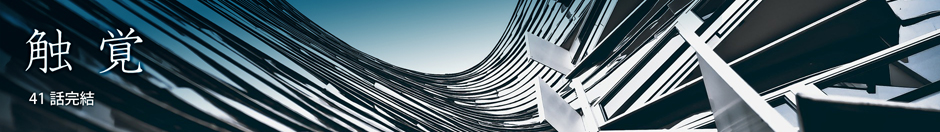
act.17
突如住宅街に現れたパトカーの姿に、野次馬が集まりつつあった。
完全に観念した顔つきの空き巣男の頭が、パトカーのドアの陰に消える。
「すまなかったな、櫻井。・・・でもなぜお前、自分で輪ッパかけなかった」
川口は櫻井の腰から下がっている手錠を見ながら訊いた。
あの後櫻井は、空き巣男を押えたまま川口に電話をかけ、場所を伝えると、川口が来るまでそのまま待っていたのであった。律儀にも、手錠をかけることなく。
確かに逮捕状を持っていたのは川口だったので、待っていることは当たり前であったにしろ、本来なら状況を考えると手錠は櫻井がかけるべきであった。それに刑事には手錠をかけることがなによりの勲章になる。その後の出世にも響く。だが、櫻井は川口にそれをさりげなく譲った。川口の八年間の努力に敬意を表してのことだろう。
まったく・・・、出世ももはや関係ないこんな老いぼれに気をつかうことはないのに・・・。 だが櫻井は、そういう青年だった。
櫻井は川口のその質問には答えず、少し肩を竦めて見せ、飛び降りた時にフェンスに引っ掛けて少し擦りむいた手のひらをペロリと舐めた。
「川口さん、もう出しますよ」
パトカーの運転席から制服警官が顔を覗かせる。
「おお、すまん、すまん」
二人してパトカーに乗り込もうとした時に、野次馬の中から声がした。
「櫻井君!」
聞き覚えのある声に、櫻井と川口も振り返った。ディープブラウンのパンツスーツに見を包んだ井手だった。
大きな黒いカバンを肩に抱えなおし、人込みをワシワシと掻き分けてくる。
「こりゃ、べっぴん先生じゃないか」
「川口刑事。ご無沙汰してます」
川口の顔が綻んだ。
「や、俺の名前も覚えていてくれているとは光栄だね」
「そんなの、当たり前じゃないですか」
井手が微笑んだ。櫻井は、井手の白いスーツ姿しか見ていなかったので、ちょっと新鮮に見えた。その視線はまたも井手に『読まれた』らしい。
「今仕事が終わったところなの。有閑マダムのための出張カウンセリング。いつもの仕事から考えると、お遊びみたいなものだけど、これでも結構まめに稼いでるのよ」
井手はそう言って、苦味走った笑みを浮かべた。櫻井は咳払いをする。
「あら、そちらも一仕事終えたようね。これからよかったら、どこかで一服しない? 話したいこともあるし・・・」
「いえ、自分は職務中ですから・・・」
櫻井がちらりと川口を見る。川口は美しい精神科医と寡黙な青年刑事を見比べた。
たまには、こんな美人とデートするのもいいさ。
川口は櫻井の腰をポンッと叩いた。
「あいつの後始末は俺ひとりで十分だよ。ちょっと息抜きしてこい」
「しかし・・・」
不安げに川口を見る櫻井に、川口は「あ~、あ~」と手を煩そうに振った。
「こんな美女が誘ってくれてるんだぞ。男なら、断るもんじゃない。課長には、俺がうまく言っとくから。しばらく帰ってくるな。どうせなら、そのまま帰ってこなくてもいいぞ」
公務員にあるまじきことを言いながら、川口はそそくさとパトカーに乗り込んでドアを閉めてしまう。
「川口さん!」
櫻井がドアに掻き付く前に、さっさとパトカーは走り去ってしまった。
三々五々、野次馬が消えていく。
櫻井は、ゆっくりと振り返った。そこには冷めた目をした井手が立っていた。
「君、逃げようとしたわね」
「はい」
「そうやって悪びれなく『はい』って答えるところがまた嫌味なんだから」
「すみません」
「・・・近所に趣味のいいカフェがあるの。来る気ある? ・・・いい? この場合、あるって答えておきなさいよ。意味判るわね。ようは脅してでも連れて行くって意味」
「判りました」
「よかったわ。判ってもらえて」
無表情でやりやう二人のやりとりを、僅かに残っていた野次馬が奇妙な顔をして見ていたのだった。
確かに井手の言う通り、趣味のいいカフェだった。
自然の緑に溢れた店内。あちらこちらにアンティークの家具がさりげなく置かれている。店内のソファーは、どれもが個性的で一セットづつデザインが違っており、どれもが落ち着いて腰を据えるにはもってこいの座り心地であった。個性的なカフェ。だが、アイボリー色の壁紙が一番目の現場を思い起させて、櫻井は少し眉間に皺を寄せた。自分が座った席の真正面に見える壁に、一瞬放射線状に飛び散った血のりが見えたような気がした。
「ブレンドを頂戴。櫻井君は何にする?」
「あ・・・。アイスコーヒーを」
「かしこまりました」
チャコールグレイの丈の長いエプロンをしたギャルソンが機敏な足取りでカウンターに戻っていく。
午後の三時を目前とした時間だったので、店内は女性客で埋め尽くされていた。観葉植物が気の効いた位置に配置されていたので、客同士が干渉するようにはなっていないが、やはり櫻井としては、自分が場違いな存在に感じてしまう。
「汗掻いてるわよ」
井手にそう言われ、櫻井は、彼女の差し出したハンカチは手に取らず、無造作にスーツの袖で額を拭った。
「せめておしぼり使うぐらいしたら?」
青年の無骨さに、井手も呆れ返ったようだ。
「夕べはちゃんと眠れた?」
ふいにそう訊かれて、なぜか櫻井はドキリとした。
井手にとっては、昨日の今日なので、純粋に心配だったのだろう。彼女も、まさか櫻井と香倉の間に起こったことは知らないはずだ。
「ちゃんと眠れてないのね」
櫻井の沈黙を井手はそう解釈したらしい。櫻井は、慌ててそれを否定した。 「夕べはよく眠れました」と。
「本当?」
井手は訝しげに櫻井を見たが、櫻井は「はい」とはっきり頷いた。
それは嘘ではない。夕べは、いつもよりよく眠れた。香倉との間の出来事のお陰で、身体は程よく疲労しており、独身寮のシャワーを浴びたら、睡魔に襲われた。布団を敷いてから後の記憶すらない。気づけば朝だった。こんなことは本当に久しぶりだった。いつもは、仕事で余程肉体を酷使していない限り、夜中に二、三回必ず目が覚める。
なんとなく井手の目線を受けるのが恥かしく、つい櫻井は俯いてしまったのだが、井手はどうやら追及してくる気はないらしい。
「・・・そ。ま、信じてあげる。櫻井君、嘘はつけない性格だものね」
彼女はそう言って肩を竦めた。その台詞は、ある意味嫌味にも取れたし、そのものの意味だとも取れた。嫌味だと感じてしまうのは、自分の心に後ろめたい感情があるからか・・・。
櫻井は、益々萎縮した。
ギャルソンが「お待たせしました」と言って、カップとグラスをテーブルの上に置いた。
「煙草、吸っていい?」
「どうぞ」
井手が懐から煙草のケースを取り出す。吸っている銘柄を見て櫻井は少し驚いた。
「女がハイライト吸ってるの、笑えるでしょ」
華やかな見かけとのギャップは確かにあったが、よくよく考えると何となく井手らしかった。
「吸う?」
煙草を差し出されたが、櫻井は断った。
井手は慣れた手つきで煙草にマッチで火をつけ、ほっと一息つくように煙を吐き出した。櫻井に煙が届かないように煙を吐くところが彼女らしい。
「北原正顕って、あなたのお父様なのね」
さりげなく井手が切り出した。
「うちの院長が知ってたわ、あなたのお父様のこと。優秀な心理学者で、精神科医だったとか」
井手は、あの夜の即席で行った催眠治療が効果を上げていることを確信していたらしい。櫻井の動向を物怖じする様子もなく北原の名前を出した。事実、その通りであったし、吉岡や香倉とのこともあって、すでに櫻井の感情は落ち着いていた。心に抱えた傷は変わりなかったが、香倉の前で感情を爆発させたせいで、櫻井の中の靄は幾分晴れていた。
「事件のことも院長から聞いた。少しだけど。・・・何があったの?」
櫻井は視線を落とす。グラスの中の氷が、触れもしないのにカタリと音を立てて動いた。
「無理に話せとは言わないけれど。でも外に出さなければ、あなたの心の傷は回復することはないのよ。そう断言できる」
櫻井は目線を上げた。真摯な目つきの井手がいた。彼女は、本当に自分を救おうとしてくれているのだということが判った。
今、こんな事件が起きて、そんな中でこうして井手や香倉に出会った事は、何かの暗示なのかもしれない。
櫻井の身体の中で、錆付いて動かなかった歯車が、再び動き出すのを感じていた。
「・・・自分は・・・、父親を刺しました。殺すつもりでした」
井手が煙草を灰皿に置く。
「自分は、姉を助けたかったんです。ただそれだけだった。父は、姉と性交渉を持っていました。多分、強制的に。母もそのことを知っていました。でも、父を止めることはできなかった。・・・毎日、毎日、誰かが家で泣いていました。母だったり、姉だったり、時には、自分だったり。そんな毎日に、自分は耐え切れなかったんです。父さえいなくなればと、そう思いました」
櫻井は口が乾くのを感じ、ストローも使わず直接グラスからアイスコーヒーを喉に流し込んだ。
「それで、刺したのね?」
井手の問いに、櫻井は自嘲の笑みを浮かべた。辛い笑顔だった。
「自分はまだ幼くて・・・・。愚かにも、他の手段を思いつきませんでした。家から果物ナイフを持ち出して、父のいる家まで歩いた・・・。凄く遠く感じて・・・。怖くなって何度も足が竦みました。でも自分は諦めなかった。諦めることができなかった。・・・今でも、後悔しています。凄く。・・・・・・・やっぱり、煙草、もらえますか」
「ええ。もちろんよ」
井手がケースを差し出す。櫻井が煙草を咥えると、井手がマッチを擦ってくれた。煙草を軽く吹かす。煙草を挟んだ手は、微妙に震えていた。無様だ、と櫻井は思った。
「家に着くと、やっぱり姉は父のベッドの中にいました。二人とも裸で。滑らかな姉の胸は、父の唾液で光っていた。自分は、背後から父に迫って、喉を刺しました。・・・簡単だった・・・!」
一瞬感情が爆発しそうなところを、自分の左手にさりげなく重ねられた井手の手がそれを抑えてくれた。井手が、「大丈夫よ」と囁く。
櫻井は瞼を閉じ、深呼吸をすると、「すみません」と呟いて目を開いた。
「その後自分は、父の家に雇われていた家政婦に取り押さえられて、直ぐに救急車とパトカーが来ました。その時です、初めて高橋警部と出会ったのは」
井手が息を長く吐いて、二、三回頷いた。初めて彼女の中で高橋と北原の存在が繋がったのだ。
「自分はまだ未成年で、家裁に送られました。あまりにも幼かった為に、家裁の人も戸惑っていて・・・。直ぐに母の元に帰されましたが、母は自分を施設に預けました。母は、親権を放棄したんです」
「そんな・・・」
苛立たしげな声を井手が上げた。櫻井は、少し苦笑を浮かべる。
「父親を殺そうとした子供です。母を責めることはできません」
櫻井が、煙草を深く吸い込み、灰を灰皿の上で弾き落とした。一方、井手の一本目の煙草は灰皿の上で既に燃え尽きており、彼女は新たな煙草に火をつけた。
「それで・・・。お姉さんは?」
「それっきり、会っていません。姉の親権は父親にありましたし、母は姉を拒絶していました。自分同様、施設に預けられたんです。高校の時、姉を探し出そうと試みましたが、辛うじて姉の預けられていた施設が判っただけで、その先はまるでダメでした。この世から、存在自体が消えてなくなったように、跡形もなく消息が消えていて・・・・。高校を卒業して、高橋警部の計らいで警察官になった後も探しましたが、ついに判りませんでした」
櫻井は、自分の唾液が苦く感じた。煙草を灰皿に押し付ける。
「捜査情報は、井手さんのところまで降りてきているんですか?」
井手が身体を引いて腕組みをする。
「断片的にはね。ただ、全てと言う訳ではないわ。そんなこと聞いてどうするつもり?」
櫻井は、その先を続けられなかった。井手が責めるような目つきで自分を見ているのが判る。
「ダメよ、櫻井君。あなたはこの事件に関わってはダメ。精神的な傷は、確かにその原因となった問題をクリアすることが治癒への道のりだけど、あなたの場合は、状況が普通と違うわ。逆にあなたが潰される危険性が高い。それは自分だって判っているんでしょう」
櫻井は奥歯を噛み締める。
「高橋警部だって、そう思って判断を下したのよ。そうでしょう?」
櫻井はガタリと席を立った。
「そんなことは、判っています! 判っているんです!」
握り締められた拳がブルブルと震えていた。
「頭で判っていても・・・。ダメなんです」
櫻井は吐き捨てるようにそう言うと、井手の制止を振り切ってカフェを出て行った。
触覚 act.17 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
最近、仕事が鬼のように忙しいとデカバンなどに書いているせいか、励ましのメールをいただくことがあります。それは、本当にありがたく嬉しいものでして、国沢、日々頂く皆様からの感想メールに支えられ、こうして何とか更新作業を続けています。
最近、よく思うんですよね~。ご自分でサイト運営されている方ならお判りになるかと思うのですが。
サイト更新において一番大事なのは、まず「根性」。そして次に大事なのが「根性」。とどめに大事なのが「根性」。・・・・・ま、ようは「根性」。これにつきるということですが。
いかに立派な男の生き様を見せつけるか、これが大切です。(といっても、男じゃないですけどね、ええ(汗))。
くそ~~~~~~~~! こげな厳しい時こそ、己が生き様見せちゃる~~~~~!! ちゃる~~~~・・・ちゃる~~~・・・・ (←エコー)
国沢柊青、ただいま29歳。青春真っ盛りです。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
