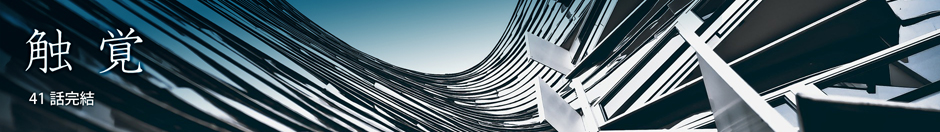
act.03
薄気味悪い事件だわ。
資料を読んだだけでこの事件の異常性は十分に伝わってきた。
そもそも、警察署に呼ばれた段階で、嫌な予感はしていた。
井手靜は、一通り資料を読んで内容を自分の脳髄の中にインプットすると、目頭を指で強く押えた。
被疑者に接見しなくとも、もう結果は現れているのかもしれない。
だが、物事をそんなに簡単に判断をしてはいけない。自分が身を置くこの世界は、特に。
井手は大きく息を吸い込むと、応接室を出た。
刑事部屋の男達の視線が一斉に自分に集まる。
そんなことはいつものことで慣れていたが、今回は妙にあの若い刑事の視線が気になった。
純粋で淀みのない美しい瞳だったが、彼には何か計り知れない闇が覆い被さっているように思える。酷く痛々しい何か。
井手はなるだけ直感というものに頼らないようにしている。科学者としては当然のことだ。だがしかし、井手が直感的に思うことは、大抵外れることがない。きっと自分は、知るべき事実、知らなくてもいい事実関係なく、肌でそれを感じてしまう体質なのだろう。
ヘンな表現だと井手自身思っていたが、それが一番しっくりくると彼女は思っていた。
「今、対象者と話すことはできますか?」
応接室の外に立っていた本庁の刑事に井手が言うと、その刑事はすぐさま取調室にとって返した。中の様子を確認して井手を振り返る。頷いて見せた。
井手もそれに頷いて、取調室までの短い道のりを歩いた。
背中にあの若い刑事の視線が刺さっているのを感じる。
これから対象者との戦いが始まるというのに。
子宮の奥が熱くなるような気がして、井手は男でも滅多に浮かべられないようなニヒルな笑みを浮かべたのだった。
噂の凄腕精神科医が取調室を出てきたのは、二時間後のことだった。
今日の午前中までで今回の事件の裏づけ調査は終了していたので、櫻井はずっと刑事部屋を出ることなく取調室の向こうの様子に神経を飛ばしていた。
時折、被疑者の「男が!あの男に命令されたんだ!」という狂気じみた悲鳴が聞こえ、この面談が難航していることが伺えた。
それにしても「あの男」というのはどういうことだろうか。
共犯がいるということか。
しかし、本庁や自分たちが調べ上げたところでは、被疑者・中谷由紀夫の後ろには誰の影も伺えなかった。
現在31歳の中谷由紀夫は裕福な家庭に育ち、潮ヶ丘署が管轄する高級住宅地に両親と共に生活していた。
金持ちのボンボン息子にありがちなことであるが、一人の大人として由紀夫は成熟しておらず、できる仕事も半人前で、母親のコネで入った会社でも極簡単なデータ入力の仕事をしていた。給料もそれなりだったが家の金が腐るほどあったので、派手な生活を繰り返しても生活に困ることはなかった。
確かに、由紀夫は母親に反発を感じていたようである。その反動からか、由紀夫はよく夜の町を遊び歩いて様々な刺激を求めていた。だが、元来臆病者である彼は、決して違法な薬や女達に手を出すことはなかった。むしろ金をかけてでも安心できる遊び場を選んでいたようだ。
しかし、母を白昼堂々と刺殺するような度胸は、櫻井が考える限り、由紀夫にはなかった。三週間前の母親の誕生日には、母親が好きだった胡蝶蘭の鉢植えをプレゼントしている。これから殺そうと思っている人間に、毎日世話をしなければならない鉢植えをプレゼントするものだろうか? それとも、あてつけに殺害後捨てようと思っていたのか。
犯行のあった当日、由紀夫は不可解としか言えない行動を取っている。
朝、いつもの時間に出社をした由紀夫は、上司から頼まれた売上のデータ分析を行うための数字を表計算ソフトに打ち込むように言われた。それは由紀夫にしてみればかなりの量があり、しかもその日の三時までに済まさねばならなかった。
資料の多さに四苦八苦している由紀夫の姿を何人もの同僚が確認している。
その由紀夫が突然机の前から離れたのが丁度10時。その日初めて彼がつけているのを見たというアラームつきのデジタル腕時計が鳴り、突然由紀夫が立ち上がった様子を、オフィスの入口近くに座っていた女子社員が見ている。黙って部屋を出て行く由紀夫を見て、「トイレにでも行くのかな」と思ったそうだ。それほど、由紀夫の行動は自然だった。
それから以後、中谷由紀夫は会社を出て、電車に乗り、駅前の量販店で果物ナイフを購入すると、その足で真っ直ぐ母のいる喫茶店を目指した。そして由紀夫は何の躊躇いもなく母親の喉を一回突き刺し、周囲が唖然としている間に再び店を出て、タクシーを拾っている。そのまま会社の前までタクシーをつけ、メーターの数字とちょうどの金額を支払って、タクシーを降りた。そして会社に戻り、血まみれのまま、また通常業務に戻っていた。
ここで問題なのは、いつ殺意が芽生えたかということだ。その時に、冷静でおれたのか。果たして、善悪の判断がつけられたのか。 衝動的殺人と計画性のある秩序型殺人とでは、裁判の結果が大きく変わってくる。ましてや、常軌を逸していたのなら起訴することすら危うくなってくるのだ。
しかし何より櫻井が気になっていたのは、犯行の手口だ。 喉元を小さなナイフで一刺し。 初めて人を刺し殺す人間は、そんな殺し方はしない。
人間を刺すという行為は案外手ごたえがないもので、初めて人を刺し殺す人間は、執拗なほどに何度も被害者に刃物を突き立てる。「めった刺し」という言葉がよくマスコミで使われるが、そういう犯行の殆どは初犯で動機に怨恨が絡んでくる。実際刺してみたけれど、手ごたえがないので相手が本当に死んだかどうか分からず、怖くて何度も刺してしまうのだ。連続殺人犯等は、犯行を重ねるにつれ、手口が洗練されてきて、自分が疲れないようにとか、後始末に困らないようにとかいう理由でシンプルになっていく。
今回の中谷由紀夫の手口は、まさしく初犯にあるまじき手際だった。 なぜ刺した場所が喉元だったのか。なぜ一度切しか刺さなかったのか。
まるで自分の苦い過去を髣髴とさせる犯罪に、櫻井の心は苦々しく濁った。 あの冷たい美貌の精神科医は、どう判断するのだろう・・・。
櫻井がそう思った矢先、取調室のドアが開いた。
「明日、また来ます」
鉄の処女と呼ばれる精神科医の顔にも疲れが見て取れた。取調室から顔を出す本庁の刑事や、高橋課長の顔にも疲労の色が浮かんでいる。
「櫻井」
高橋が再び櫻井を呼ぶ。
「井手さんをお送りしろ。大分疲れているようだから」
そういう高橋の顔色も悪い。
「何か・・・あったんですか?」
櫻井が訊くと、高橋は顔を顰めただけだった。
「じゃ、頼んだぞ」
「はい」
櫻井が、刑事課の外にいる井手の元に向かうと、井手は携帯電話でクリニックに電話をしているところだった。
「ええ・・・。そうです。集中して考えを整理したいので。ええ。この後の予約は入れていませんから大丈夫だと思います。それでは」
井手が電話をたたんで振り返る。艶やかな黒髪がサラリと流れた。
「本当に送っていただいてもいいのかしら? 私の車で来ているので、帰りの足が困ることになるけれど・・・」
目の下に艶がなくなった顔つきの井手に、「大丈夫です」と櫻井は返した。
「こういうのは慣れてますから。どうぞご心配なく。自分が運転してもよろしいですか? もしよかったら、こちらの車でお送りしますが。明日迎えにいけば済む事ですし」
井手は少し笑って首を横に振った。
「明日は、朝に必ずクリニックに寄らないといけないから、車がないと困るの。自宅の方に送ってもらいたいのだけれど」
「分かりました」
粘り強い記者達を遠めに見ながら、櫻井は井手の車に乗り込んだ。
女性の車にしては、味気がない。およそ、飾りというものが見られないし、髪の毛ひとつも落ちていない。まるで、男が乗っている車のようだ、と櫻井は思った。
斜め後ろに座る井手をバックミラーで見ながら、櫻井は高橋にした質問を再び井手にぶつけてみた。「何か、あったんですか?」と。
井手は、一瞬ミラーの中の櫻井と視線をあわせ、すぐに手元の書類に目を落とした。
「鑑定中は、その内容に関して外には漏らさないことにしてる」
井手のもっともな言い分に、櫻井は「すみません」と謝って、車を発進させた。
井手が指定したところは、麻布の高級住宅地の一角だった。
全国からカウンセリングの依頼が殺到しているクリニックのエースともあって、櫻井などが足元にも及ばないギャランティーを得ているのだろう。
職業柄、日頃考えたことを顔に出さないように勤めている櫻井だったが、井手相手では効果がなかったらしい。
半地下の駐車場に車を止めて降りると、井手は櫻井をからかうような苦味走った笑みを浮かべた。
「友人の家なの。私の本当の自宅は数ヶ月前に小火にあっちゃってね。それ以来、こっちに居候させてもらってる。・・・だから、あなたが思っているほど、私のサラリーは高くないわ」
櫻井は思わず顔を赤らめる。これを、コンクリート越しに差し込む夕日のせいにできるだろうか?と櫻井は変に焦ってしまった。
井手が居候している部屋は、高級マンションの七階にあって、最上階とは言えないもののエレベーターを降りた通路からの見晴らしはかなりのものだった。
705。東の角部屋である。
ドアの前で立ち止まると、井手は疲れた顔のままで微笑んだ。
「ありがとう。ここでいいわ。タクシーを呼びましょうか?」
「いえ、電車を使いますから」
「そう。じゃ、また明日午後にお伺いします」
「お疲れ様でした」
櫻井は頭を下げて、エレベーターへと向かった。
エレベーターのボタンを押し、身体の向きを変えると、井手がチャイムを押しているところが見えた。
どうやら友人は、部屋の中にいるらしい。
エレベーターが来て、櫻井が乗り込む頃、705のドアが開いた。
中にいる人間が井手を出迎える。
なんだ、男か。
櫻井はそう思って、目を凝らした。
櫻井の視力はとてもいい。「井手の男」であろう人間の姿を観察した。
そしてその映像がしばらく櫻井の頭から離れなかった。
「へぇ~、井手の恋人か」
署に帰ると、早速吉岡に掴まった。事の顛末を話すと、吉岡が興味津々で、櫻井を見た。
「で、どんな男だった」
吉岡は、櫻井の視力が優れていることを知っている。櫻井は、単に視力がよいだけではなく、動体視力も抜群にいい。
自分の好奇心が納まるまで、吉岡が櫻井を放さないことは分かっている。その好奇心の強さこそ「いい刑事」の証拠なので、櫻井は吉岡の話に付き合うことにした。
「年齢は、井手さんと同じぐらいか少し上。身長は185センチぐらい。身体つきは普通でしたけど、着やせするタイプかもしれません。顔は彫りが深くて、知的な感じがしました。落ち着きがあるというよりは、クールというか」
「つまり、あの鉄の処女と呼ばれる井手靜でさえ、むしゃぶりつきたくなるようないい男だったって訳だな」
吉岡の露骨な表現に、櫻井は眉を顰めた。
「その表現って・・・」
「だけど、事実だろう?」
確かに、二人は似合いだろう。あの男がどういう仕事をしているか知らないが、井手靜の隣に立っていても見劣りはしない。だが、なんだか、あの二人が付き合っているという感覚が、どうしても櫻井の頭の中に浮かんでこなかった。現場を見ている自分がそう感じるのは不思議だが、櫻井の直感がそう言っている。
しかし、そんなことはどうでもいい。
櫻井は頭を切り替えた。
事件のことに集中しなければ。裏付け捜査も少し残っているし、起訴される可能性もあるのだから。
そう思っていた矢先、またも事件が発生するのである。
触覚 act.03 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
「むしゃぶりつきたくなるようないい男」(笑)の登場です。でも台詞なし(汗)。すみません・・・、もったいぶってて(汗)。もうすぐしゃべりますからね~。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
