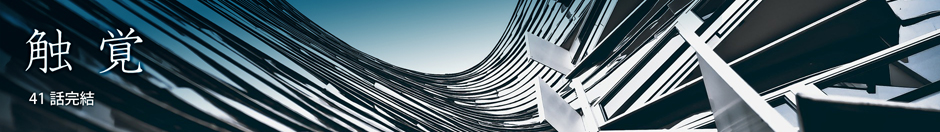
act.01
光沢のある黒い板に白いチョークの先が押し当てられる。
男の手が、カツカツと音を立てながら文字を書き付ける度に、ぱらぱらと砕け落ちた白い粉が男の足下に降り注いだ。ふいにチョークがパキンと割れて、シンプルなリーガルのローファーの上に落ちて跳ねる。
男が、長身の身体を屈ませてチョークを拾う様をいくつもの熱っぽい視線が追っていた。
「いいですか。レポートの期日は来週の金曜日まで。菅原教授の研究室まで持って行くこと。言っておくが、僕のところに持ってきても点数はつけられないので、くれぐれも勘違いしないように」
中規模の講義室の中に笑い声が起こる。露出度の高い洋服を着た女学生の数人かが、仲間内で目配せをしあっている。この教室にいる学生達は、彼女達が『わざと』勘違いして教授ではなくこの助手の元にレポートを提出したことを知っている。
さっき俯いたせいで顔にかかってきた長い前髪をかき上げながら、男は自分の手帳にスケジュールを書き込み、「はい、今日はこれで終わり。来週からは菅原先生が帰ってきますので、通常授業に戻ります」と言った。
学生がガタガタと席を立つ。ほとんどの学生がわざわざ教壇の前を通って、男に挨拶しながら教室を出て行く。教壇の上にリンゴを置いていく者、お奨めの本を置いていく者、果てはラブレターらしき手紙を置いていく者も数人いる。
「来週から元に戻るなんてショックだなぁ、東條さんの方がずっといいのに」という呟きは、女学生ばかりか男子学生の声も聞かれる。
しかし東條と呼ばれたその男は、その声に気づかぬ振りをしながら教壇の上のプレゼント達を纏めて、革製のショルダーバッグに詰め込んだ。白衣に紺色のポロシャツ、ベージュのチノパンというスタイルには少々不似合いなハードさがある鞄だ。まるでアメリカンタイプのバイクに乗るような男が好んで持つようなその鞄は、そこだけにその男の自己主張が感じられる。
男は鞄を肩に掛けると、右手の中指で銀縁のメガネをクイッと押し上げ、講義室を出た。
東條千博(とうじょうちひろ)は、去年、前期の終わり頃という異例の時期に菅原教授の研究室の助手として採用された男だ。
植物分類学の権威・菅原肇(すがわらはじめ)教授の研究は文字通り、多量の植物標本を分類するところから始まる。そのためそれ相当の人手が必要であり、なおかつ的確に間違うことなく整理が出来る人間が必要だった。菅原教授の研究室には、他の研究室より多い助手が働いていたが、東條はその中でも一番日が浅い。しかしどういう訳か菅原は、採用されてから一年程しか経っていない東條を他の誰よりも信頼していた。自分が学会の発表でカナダに行っている間の授業を東條に任せるぐらいだ。確かに、東條は助手なので授業内容はあらかじめ菅原が用意していったものだが、それを託した相手が東條だったので、他の者のやっかみも囁かれた。なまじ東條は、同じ学科の他の教授や准教授にもウケがよく、なおかつ学生にも人気があるから誰も文句がいえない、というのが実状だ。
「東條先生!」
東條が校舎を出ると、まるで待ち伏せしていたように女学生が東條を追いかけてきた。
女学生と言っても、きちんとメイクが施された顔はまるで一人前の大人の顔だ。
彼女は四年生で、菅原教授のゼミを取っている学生だ。去年のミスコンで一位に選ばれた彼女は、もちろん学科のアイドル的存在だったが、如何せん彼女の今の興味はこの東條千博である。自分の美貌を持ってしても全くなびかない堅物男に懲りず、いや懲りるどころか益々燃え上がって、日夜あれやこれやと作戦を考えているようだ。
「東條先生、待ってください!」
彼女が息を切らしながら東條の腕に縋ると、東條は立ち止まって女学生を見下ろした。
「先生、歩くのが速いんだから」
女学生の言葉に、東條は無表情で答えた。
「繰り返し言うけど、僕は先生じゃない。単なる助手」
女学生は、東條の腕を掴んだまま肩を竦める。なかなかチャーミングな仕草。
「学生の間じゃ、並の准教授より教え方がうまいって評判なんですよ」
東條は苦笑いを浮かべて見せた。女学生はそんな東條の僅かな表情でも、うっとりと見つめている。大学広しといえども、東條ほどの『いい男』はなかなか拝めない。恐らく、大学の外でもこれほどの『質』を誇った男はなかなかいないだろう。
プライベートについてあまり話さない東條は、少しミステリアスだ。おまけに長身の身体は決してか細くなく、均整の取れた身体付きをしている。少し長めの髪はいつも無造作に後ろで束ねてあるが、艶やかで不潔な感じはしない。ポールスミス製の細い銀縁メガネに隠された瞳は何とも魅力的だ。鼻梁も高くて、彫りの深い顔立ち。つまり、とても端正な顔立ちをしている。仕事もできるし、他の助手達や教授達と違って女の扱いもどこかこなれていて、卒がない。学生の間では、東條に『女』がいるかどうか賭けの対象になっている。今のところ、女性軍の希望的観測で『いない』の方に多く掛け金が集まっているようだが。
「先生、これからのご予定は?」
東條は腕時計を見る。丁度今四時を少し越えた時間だ。
「もしよかったら、卒論についてのアドバイスを頂きたいんです。今、主なテーマについてどうしようか迷っていて」
女学生が確信に満ちた表情で東條を見上げてくる。東條は悟った。彼女は、この後の東條の予定が何も入っていないことを知っているのだ。なぜなら今日は、白衣を片づけに研究室へ戻った後、家に帰って『大学の研究とは関係がないが、非常に重要な資料の整理』をしよう、と思っていたから、わざと予定を空けておいたのだ。
なかなか研究熱心だな・・・・。
内心溜息をつきながらもどう答えようか考えあぐねていると、ふいに東條は背後から自分を見つめている視線を感じた。
また他の女生徒だろうか・・・。
東條はそう思いつつ、さり気なくそちらの方向に目をやって、一瞬息を呑んだ。
東條が滅多に浮かべることのない驚きの表情を見せながら見つめている視線の先が気になり、女学生は東條の視線に自分のそれを沿わせる。
「・・・あら・・・」
女学生も思わず感嘆の呟きを盛らす。
四年間この大学に通っている女学生でも見たことのない青年が、木立の向こうにあるベンチに腰掛けて、こちらを見ていた。
程良く色落ちしたジーンズに白いTシャツ。そこから突きだした腕は小麦色で、何かスポーツをして鍛えているのか小気味よい筋肉がついている。学生にしては少し年齢が上のようにも思えるが、その場の空気に馴染んでいるところを見ると、院生と言ってもおかしくはない。切れ長の涼しげな目元やすっきりと伸びた鼻梁は、何とも清々しい。とても日本的な美しさを湛えた面差しだった。
ふいに初夏の風がふいて、ベンチに座っている青年の癖のない髪を揺らす。青年は、乱れた髪を無造作にかき上げながら、笑顔にも見える少し不器用な表情を浮かべた。青年の右目尻にある黒子がクイッと上がる・・・。
「アイツ・・・・」
ふいに東條が呟いた。
女学生には、東條のその声がいやに人間味を帯びた、生々しい呟き声に聞こえた。
生活感が薄く多くの謎に包まれている東條のプライベートを垣間見たような気がして。
女学生は内心ドキドキしながら、東條の顔を見上げた。
「お知り合いですか?」
女学生が訊くと、東條は夢から今覚めたかのように瞬きをすると、「え? ごめん、何?」と訊き返してくる。
「ご存じの方ですか? あのベンチの人」
「あ、ああ・・・まぁ・・・」
東條が言葉を濁す。
ベンチの青年が、立ち上がってこちらに歩いてくる。颯爽とした隙のない足取り。
木や花が植えられている花壇を小柄ながらひょいと軽く飛び越え、やってくる。
「お久しぶりです」
青年の声は、女学生が想像していた通り、耳に涼やかに通る聞き心地のいい声だった。
東條は青年にそう声を掛けられても、少し呆気に取られた表情のまま、声に詰まっている。まったく東條らしくなかった。
「あの・・・東條先生のお知り合いの方ですか?」
女学生がそう訊くと、青年は「東條?」と少し訊き返して、「ああ。ええ、そうです」と答えた。
「東條先生の知り合いの高橋です」
そう言って笑みを浮かべると、途端に雰囲気が柔らかくなった。東條のような華はなかったが、この高橋と言う青年もまたとても魅力的である。
「丁度一年振りですか」
青年がそう言って東條を見ると、「ああ、そうだな。一年にもなるか」と東條が答える。
「どういうお知り合いなんですか?」
女学生は、既に興味津々である。東條はそんな女学生をちらりと見ると、
「彼は大学時代の後輩なんだ。先程の話なんだけど・・・、また今度でいいかな」
と言った。女学生は「どうぞどうぞ!」と極上の笑顔を浮かべる。彼女にしてみれば、今まで誰も見たことがないであろう東條の表情と『後輩』だという青年の情報を手に入れることができただけで、大した収穫だ。
「あの娘さん、まだ手を振ってますよ。いいんですか? 東條先生」
足早に歩く東條の後を追いつつそう言う青年を、ふいに東條は振り返る。怪訝そうに青年が見つめ返すと、東條は無表情でこう言い放った。
「東條と呼んでくれるんだな。それならそれでいいが、気を付けてくれ。俺は、『先生』なんかじゃない」
今までの言葉遣いと全く違う。少し粗野で強い響きを持つ口調。
青年は、テレ臭いのかどうなのか、少し俯いて思わず浮かべてしまった微笑みを隠すような素振りを見せた。
「それじゃ、こう呼んだ方がいいですか。香倉さんって」
ふいに東條・・・香倉裕人が立ち止まる。
「今その名前で呼んでも返事はしないぞ。サクライくん」
ついに笑顔を隠せなくなったのか、青年・・・櫻井正道は、両手で顔を覆って大きく深呼吸をした。
「テレるな、バカ」
香倉が櫻井の腰を足で軽く蹴り上げて、再び歩き出す。
「これから何か予定はあるんですか?」
さっきの女学生と同じ台詞を言いながら、櫻井が後を追って小走りについてくる。
「別に。後は家に帰るだけさ。どこか飯でも食いに行くか?」
すれ違う学生の挨拶に軽い返事を返しながら、香倉が言う。櫻井は香倉の格好を見て言った。
「白衣を着たまま行くんですか?」
再び香倉が足を止める。彼は少し溜息をついた。
「そうだった。これを研究室に片づけに行くつもりだった。・・・まったく、お前がいきなりあんなところに座ってるから、調子が狂った」
香倉は白衣をその場で脱ぐと、乱暴に畳んで鞄に突っ込んだ。
「でも、その白衣にそのメガネ。そうしてるとお兄さんに益々よく似てます」
櫻井がそう言うと、香倉はメガネを押し上げ、ニヤリと笑って言った。「狙ってやってるんだよ。嫌みっぽいだろ?」と。
それを聞いた櫻井は、軽く肩を竦めてみせる。そんな櫻井の全身をみやって香倉もやり返した。
「お前もなかなか若作りしてるじゃないか」
白いTシャツにジーンズという格好は、以前の櫻井なら見せたことのない格好だった。
真面目で実直な刑事だった櫻井は、いつも濃い色のスーツ姿で、休日でもせいぜいチノパン止まり。ジーンズみたいにラフな私服は持っていなかった。
公安の訓辞式の後、一ヶ月後に香倉と再会した時は、技術系の会社員がよく着る何とも色気のない作業服を着ていた始末だ。
だからこうしてジーンズを履き、髪もラフなままというのは、今まで香倉も見たことがなかった。実年齢より随分若く見える。だが、少しゆとりのある服のシルエットは、中身がきちんと均整の取れている身体であるだけに姿が良く、とても似合っていた。
「大学で会うのは初めてですから、スーツ姿で怪しまれるといけないと思って。訓練の成果だと思ってください」
周囲に聞こえないくらいの声で、櫻井が言う。
現在櫻井は、特務員養成の最終訓練に入っている筈だった。
彼のような公安特務員候補生は、訓辞が降りて一ヶ月間、基本的訓練を施される。その訓練の結果でそれぞれの適正を見極められ、まずふるいにかけられる。表の仕事に回される者、裏の仕事のサポート・・・つまり技術者や事務・総務的仕事に就かされる者など、特務員としての適正を見極められない者。そして、潜入捜査を専門とする特務員として引き続き特殊訓練をされる者に分けられるのだ。極めてごく少数の精鋭と言われる潜入捜査官候補生は、実戦に投入される前に最終訓練が行われる。つまり、実際に使えるヤツかどうかを見極めるテストだ。そこでは、あらゆる突発的なことに対しても対処できるようにと徹底的に訓練をされる。潜入捜査官候補として推薦された時点で、その者は外界との接触を全て断たれることになっていた。だから香倉とも、一年振りの再会、となったのだ。
「それで? 時間はあるのか?」
香倉がそう訊くと、櫻井は頷いた。
「明日の夜まで休暇を頂きました」
香倉が感心したように片眉をクイッと引き上げる。
「『最終』にパスしたのか」
「ええ。しました」
「一発で?」
「はい」
「ふーん・・・。じゃ、いよいよだな」
「はい」
香倉は周囲を見回す。相変わらず人の往来は多い。
「ここでこれ以上の話は無理だな。俺の家に行こう」
「はい」
香倉と櫻井は、揃って大学を後にした。
日々 act.01 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
次回は、東條先生(じゃないって(笑))のお宅探訪です! でも渡辺篤さんは出てきません(笑)。
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
