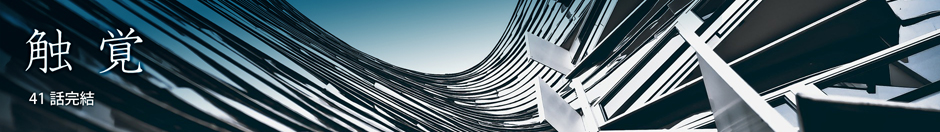
act.06
<第4章>
潮ヶ丘署刑事課の片隅にある小さなミーティングルーム。そこが、今回の奇怪な殺人事件の捜査本部となった。
公にしていないだけあって、大々的に大会議室を占拠する訳にも行かず、いたって質素にやっている。秘密裏に行っているという前提があったので、誘拐事件以外には必ずつけられるという戒名(事件の公の名称)もつけられず、もちろん、会議室の前には、墨字書きの看板もない。
現在、二回目の事件の犯人、橘は署内での簡易精神鑑定が終了し、留置されている。
橘についた鑑定人は、大学の教授とかで、井手より少々頼りない感じが否めなかった。仕方がない。井手は、同時に二人もの鑑定は無理だ。通常の仕事とは違って、刑事事件が絡んだ鑑定は、慎重に行わなければならない。
捜査本部としては、たいした手がかりもなく、今ひとつ冴えない状況が続いていた。今朝まで。
捜査員らは、その日、少し遅れて来た大石の発言に驚かされることになる。
「中谷と橘の共通点が判明した」
大石直属の捜査員達も、初耳だったのだろう。驚いた顔を隠しもせず、互いに顔を見合わせている。大石は会議室を見回し、先を続ける。
「双方とも、銀座に程近いところにある会員制高級クラブに頻繁に出入りしていた」
「うわ~。臭い! 臭くて、鼻が折れ曲がりそう」
『会員制高級クラブ』に反応して、吉岡が声を上げる。
捜査本部の一同が、一斉に吉岡を見た。吉岡は、「すんません」と一言謝って、トマトジュースを飲む。大石はひとつ咳払いした。
「これは、中谷の同僚から聞き出した情報だ。橘の周辺の者に裏を取ってみると、同じ店の名前が出てきた。ここが事件解決の何らかの糸口になるのでは、と思う」
本庁の捜査員や吉岡が、へぇと感心する中、ひとり櫻井だけは、大石の発言に疑問を持った。
捜査員が、大石に報告したことを大石が判断して糸口を見つけるというのならまだしも、大石自らが、中谷の同僚等に調書を取る(いや今回は、話を聞いただけで調書までいたっていないが)なんてことは些か不自然に感じられた。
一体そこに、何がある?
櫻井がずっと考え込んでいると、ふいに名前を呼ばれた。
はっとして顔を上げる。
「今の話、ちゃんと聞いていたのか」
大石が自分を見つめていた。
「は・・・、すみません」
「まぁいい・・・。もう一度言う。今回のこの高級クラブは、政府の要人達も多数入会しているらしい。ことを荒立てると、とんでもないことになりかねん。したがって、更に慎重に取り組まなければならない。情報の漏洩はもちろんのこと、捜査方法も内々に行いたい。間城と高柳は引き続き橘の精神鑑定に立ち会ってくれ。状況が可能であれば、橘から証言を搾り出すんだ。三井は吉岡と組んで、被疑者と被害者の関係を更に掘り下げろ。しつこいと思うだろうが、必要なことだ。それから、櫻井」
「はい」
「君は私と来たまえ。クラブを調べる」
「は・・・・」
櫻井は呆気に取られて返事を臆してしまう。隣の吉岡が、肘で櫻井を小突いた。櫻井が横を向くと、吉岡がウィンクする。
「よかったじゃん、警視庁の管理官に気に入られて」と言っている瞳だった。
店が開店する前の時間帯を狙って、大石と櫻井は問題の店を訪れた。
繁華街の外れにある、目立たないファッションビル。本当にこんなところに、政府高官や企業のトップ連中が足しげく通う高級クラブがあるかと、不安になった。
エレベーターで最上階まで上げると、世界が一変した。
豪華なエントランスホール。どうやら、この階全体が、その高級クラブとやらで占められているようだ。
櫻井が外から見た階数では七階。だが、エレベーターに示されていた最上階は「6階」だった。ビルの二階フロアを全て使っているのか。
エントランスホールは、豪華だが決して下品ではない。深く落ち着いたグリーンを基調とし、床や柱、壁にふんだんに大理石が使われてある。それが本物かどうかは、櫻井にも判らなかった。
エレベーターを出ると丸いサークルのような模様があって、一瞬西洋風の上品な洋館に来たような錯覚を受ける。
奥に進むと、入口に屈強そうな男が立っていた。「門番」というところか。
大柄で、スキンヘッド。いかにもという感じだ。
「警察の者です。事前に連絡はさせていただいておりましたが」
大石が手帳を男に見せながら言った。男は、強面の顔を崩しもせず、大石と櫻井を睨みつけてくる。だが、連絡を受けていることは知っているらしい。彼は何も言わず、道を空けた。
細い通路を通り、奥に入ると急に空間が広がった。
ああ、と櫻井は思う。だから、7階建てなのに、最上階が6階なのか、と。
このクラブは、二階フロアを吹き抜けにしている特殊な造りになっているのだ。
入口右手に小さなカウンターがあって、そこでボーイが客を出迎える。
その先にあるまるでホールのような広い空間のあちらこちらに、座り心地のよさそうなアンティークのソファーや高級そうな調度品、家具がデコレートされてある。つまり、通常のクラブとは違ってボックス席がいくつもあるわけではなく、ごく自然に各コーナーが設けられ、古びた洋館の格式深いパーティールームのような様相をしているのである。エントランスには大理石をふんだんに使っていたが、店内は寧ろ、木材とガラスに彩られている。どれもが滑らかな曲線を描いており、アールヌーヴォーの様式が取り入れられていた。
入って右手の、二段上がったところに長い一枚板のカウンターが設けられ、色とりどりの酒が、壁際に美しくライトアップされていた。洒落たショットバーのような雰囲気だ。カウンターの向こうでは、バーテンが二人、グラスを拭いたり氷を準備したりと、開店に向けてせわしなく動いている。
入口から入って真正面の一番奥に、艶やかな飴色に光る階段があって、ロフトになっている中二階へと繋がっている。中二階の廊下は少しテラスのようにせり出していて、階段を中心にして4つのドアが並んでいた。どうやら奥に個室があるらしい。VIPルームなのか。
櫻井がよく目を凝らすと、階段の奥、入口から隠れるようにして更に奥に空間があることが伺えたが、櫻井の位置からはよく分からなかった。
大石が、ボーイに「店長は」と話し掛けている。少し待たされて、バーの奥のプライベートルームから店長と思しき人物が出てきた。葛西と名乗ったその男は、こんな高級クラブの店長としては些か役不足な感があり、櫻井は少々拍子抜けした。
大石に訊くところによると、オーナーは別にいるらしく、雇われ店長らしい。
納得と言えば納得だが、それにしても少々頼りないのではないか・・・と櫻井は思った。
入口近くのコーナー席に案内される。クラブで働いている女性店員が控え室からどんどん出てきて、しきりとこちらの様子を伺っていた。
大石は、店長に中谷と橘の写真を見せていた。
「この二人なのですが。こちらの会員だったそうですね」
店長は困惑した表情を浮かべる。
「確かに、そうなんですけど・・・。参ったな、どこから会員情報が漏れたのか・・・」
「ご安心ください。この中谷、橘の関係者から聞き出した話です。彼らが自分自身で話したことですので、他の方の情報が漏れ出た訳ではありませんから」
「そうですか・・・。それならいいんですけども。いや、実は、会員規約でも、このクラブのことは他言しないようにとお客様には極力お願いをしているのですよ。うちもサービスの質が落ちないように、お客様の数を制限させていただいていることもあって、うちに相応しくないような方々が殺到されても困る。万が一会員様の情報が漏れたりすると、何かとまずいこともあるのです。ここでは、女性男性関係なく、お客様の好みで楽しい時間を過ごしていただくことになっておりますので・・・」
店長の言葉には、嫌な含みがあった。つまり、金さえあれば、アブノーマルなことでも許される環境が整っているということか。 ・・・確かに臭い。先輩の言った通りだ。
櫻井は思った。ひょっとしたら、非合法な行為もここで行われているやもしれない。
「こちらでの、この二人の様子はどうでした?」
「様子と言われましても・・・。特別変ったことは。中にはもっと派手なことをするお客様もいらっしゃいます。お二人とも、ごく普通でよいお客様でした」
櫻井は店長の目を見た。おどおどはしているが、嘘は言っていないようだ。
「いつも接客されていたホステスさんはいませんでしたか?」
櫻井が訊いた。横顔に、大石の視線を感じる。
「・・・ホステスですか・・・。ちょっと待って下さい。おい、湯江」
店長が、カウンターバーのところにたむろしているホステスの中から、一番年上と思しき女性を呼んだ。白い和服に身を包んだ、エレガントな女性だった。清潔そうで、一見見るとクラブのホステスという風情には見えない。
「なんでしょう」
湯江と呼ばれた女性は、大石の斜め向かいにある肘掛け椅子を少し寄せて、腰掛けた。
「中谷様と橘様についていた専属の女の子って、いたか」
湯江が、写真を取り上げて小首を傾げる。
「そうですねぇ・・・。特にご指名はしていなかったようだけども・・・。あ、いいえ。違います。ここ最近来られた時は、ご指名されてたわ。そう言えば、同じ娘を」
大石も櫻井も、この発言に身を乗り出した。
「でも残念ですわ。その娘、少し勤めておいてすぐに辞めてしまったの。とても綺麗な娘だったけれど。店長も、覚えているでしょう。少し変った名前の。カガミナオミちゃん」
「ああ・・・。そう言えば、香倉が休んでいた時期にオーナーが連れてきた娘か」
ぎょっとして櫻井は、店長を見た。
今、なんて言った?
「カガミナオミ・・・。どんな字ですか」
大石が差し出した警察手帳に、湯江が几帳面な字で名前を書いた。『加賀見 真実』と。
「背が少し高くて、すらりとした娘でした。本当に美しくて、気転が利く娘だったわ。普通だったら、そんなに綺麗な娘だったら、いじめられやすかったりするのだけれど。不思議と彼女はホステス仲間にも人気があって。男の人にも女の人にもウケがよかったのねぇ。こういうお仕事に向いていると思ったのだけど。なぜ辞めてしまったのかしら」
「ちょっ、ちょっと待って下さい」
湯江の言葉を遮って、櫻井が声を荒げた。彼にしては珍しいことだった。
「今、なんと仰いましたか」
三人が櫻井を見る。大人しかった男に急に食ってかかられて、店長は「俺のことか」と言わんばかりに怯えた表情を浮かべ、他のふたりに交互に目をやった。
「何って・・・」
「誰が休んでいる間にって・・・」
「ああ・・・」
言われていることの意味が分かったらしい。店長は肩の力を抜いて、言った。
「香倉です。香倉裕人。うちのバーテンなんですよ。なかなかしっかりした男で、ホールの仕切りをしてもらっているんですが、この加賀見は、香倉が私用でしばらく休んでいる間に入ってきた娘なんです。通常なら、香倉が入ってくる娘の面接を行うのですが、この娘の場合はオーナー自らが連れてきたこともあったし、容姿がなにより飛びぬけていましたから、まぁいいんじゃないかと。香倉の休みが明けた日と入れ替わるようにして辞めていったんです」
香倉・・・裕人・・・。
櫻井は声に出さず、口の中でそう呟いた。
ボクシングジムで見た横顔が思い浮かぶ。
櫻井の名前を聞いて、少し笑ったあの時の表情・・・。
「加賀見さんの写真はありますか」
大石が言う。櫻井は大石の腕を掴んだ。
「大石管理官!」
大石が櫻井を見る。
「香倉裕人という男は、井手さんと関係のある男です。何かあるのでは・・・」
大石はしばらく無表情で櫻井を見つめた。
「バーテンがたまたま精神科医の男だったとして、何の関係あるというのだ。確かに井手はこの事件のキーパーソンであるが、彼女もプロだ。捜査情報の漏洩なんてことを軽々しく行うような人間ではない」
「しかし・・・」
「バーテンのことはいい。この女のことの方が重要なんだ。・・・ありますか、写真」
厳しい二人のやり取りに、少し面食らっていた店長と湯江は、返事に出遅れた。
「ええ、残っています。一枚だけ。会員様向けのパンフレットに載せるはずだった写真が。確かカタログアルバムに挟んであったわ・・・」
湯江が席を立って、スタッフルームに消えていく。
「私物は全て持っていったのですが。てっきりアルバムの写真も持って帰ったと思っていたが、忘れていったようです」
店長が薄い笑いを浮かべる。
櫻井は、膝の上で両手を握り合わせていた。手のひらに汗を掻いている。
櫻井の刑事としての本能が、直感が、「香倉」というキーワードを逃してはならないと警告を発している。なぜ、大石はそこを見逃すのだ。
「こちらです」
湯江がバインダー形式の黒いアルバム台紙を持ってきた。B5サイズ程度の大きさだ。そこに、バストショットの女の写真が張り付いている。その下には、『鏡花』と書かれてあった。源氏名だろう。
確かに、美しい女だった。艶やかで真っ直ぐな髪が肩まで伸びている。色が白く、アーモンド形の黒目がちな瞳には独特の色気が漂っていた。案外若くない。だが、成熟した女の匂いが写真からでも伺えた。
誰かに・・・似ているな。
大石は漠然とそう思ったが、それが誰かはすぐに思い浮かばなかった。
櫻井に、見るかと促したが、櫻井は「香倉」のことで頭に血が上っているらしく、反応が鈍い。
若いな。大石はそう思いながら、「写真お借りします」と断って、写真を台紙ごとジュラルミン製のスーツケースにしまった。
加賀見の住所をひかえて、二人はクラブを後にした。
依然櫻井は不服そうな表情で、エントランスホールを大石の後を付いて歩いた。 エレベーターを待っている間、どうしても我慢できなくて、大石に食ったかかった。
「大石管理官は何も感じないんですか? 事件関係者がこんなに密接に関わりあっている。捜査する側とされる側の双方にですよ?! そこに何かあっても不思議じゃない」
「じゃ、お前は何か? 井手がこの事件の裏を引いているとでも?」
大石が斜に構えて櫻井を見る。
櫻井は、井手の顔を思い浮かべた。
『人間の一番弱い心を突いてきて、自分の手を汚さず殺人を楽しむ、卑怯な人間。あなた達が探し出すべき人間は、そんな奴よ』
そう呟いた井手の横顔。あの真摯な表情には、犯罪に対する絶対的な憎しみが込められていた。
櫻井は頭を横に振る。
「そうは、思いません」
「じゃ、なんだ。そのバーテンが井手を利用して、二人の男を洗脳したと? 二人のいう『あの男』とは、そのバーテンだと言うのか」
「その可能性はあります」
櫻井が、真っ直ぐ大石を見つめる。大石は少し笑った。
「なかなか、面白いことを考える」
エレベーターのドアが開いた。
中を見て、ぎょっとする。
黒服に身を包んだ香倉が、一人立っていたのである。
香倉は、少し驚いたような表情を見せたが、すぐに穏やかな顔をして見せた。
エレベーターを降りる。
大石をちらりと見、次に櫻井をじっと見つめてきた。
「いつかの刑事さんではないですか」
ボクシングジムとは全く雰囲気の違う香倉がそこにいた。
落ち着いた物腰。洗練されていて、エレガント。英国紳士のような気品がある。ボクシングジムの時のやや粗野な感じの荒っぽさが完全に隠れてしまっている。この男の変わり身の鮮やかさといったら、役者顔負けだ。
この男に、何かない訳がない。
櫻井は、ぎりぎりと男を睨んだ。
香倉は、いっぱしの記者共を一瞥で怯ませる櫻井の視線にもぴくりともせず、むしろ余裕の微笑を浮かべて大石を見た。
「そう言えば、今日警察の方が店に来られるとのことでしたね。お役に立てたでしょうか」
「ええ」
大石が淡白に答えた。香倉は「ご苦労様です」と頭を下げ、二人をやり過ごした。
香倉の背中に声をかけようとした櫻井の肩を大石が掴み、再度エレベーターのボタンを押して、箱の中に引きずり込んだ。
壁際に、櫻井の身体を押さえつける。
「管理官!」
怒りに目を見開く櫻井を押さえつけたまま、大石はにやりと笑った。
「お前も、しつこいな」
エレベーターのドアが閉まる。大石は櫻井を解放して、1Fのボタンを押した。
着衣の乱れを整える。
櫻井は乱れた服装のまま、胸を喘がせて大石の背中を睨んだ。
大石が笑う。
「まったく、お前の情熱には負ける。普通、所轄の刑事が捜査一課の管理官に食ってかかるか?」
大石がちらりと櫻井を見た。
「しかし・・・・・。そんなお前になら、言っても構わないだろう。・・・ただし、これから私の言うことは、完全機密事項だ。他言してはならない。守れるか?」
櫻井が、獰猛な目つきをしたまま、頷く。大石は再び背を向けて、言った。
「奴は・・・。香倉裕人は公安だ」
「え?」
「正式には、警視庁公安部の特務員として活動をしている。現在は任務のため、あのクラブに潜入しているところだ。だから、奴が中谷や橘を洗脳して殺人をさせるということはまずありえない。同期だった私が保証する」
公安・・・?
一瞬櫻井の視界がぐらついた。
公安といえば、時として非合法な捜査活動も行うような危険な部署だ。ある意味、現在の法治国家の裏世界を支えていると言える。公安職員は様々なタイプの仕事をこなすといわれているが、潜入捜査に携わっている捜査員はごく一部で、単独行動を取ることもあり、万が一職務中に殉職しても、その任務の性格上存在すら消されてしまう可能性すらある。組織から、切って捨てられることもあるのだ。
確かに、これらの話は単なる噂話だが、火のないところに煙は立たない。そこにはある程度の真実が隠されているのだろう。
しかし・・・、あの男が公安・・・。
「初めて見るか、公安の人間を」
櫻井は、はっとして顔を上げた。大石が櫻井を見つめていた。
「どう思う? 惹かれるか?」
眼鏡に光が反射して、大石の目の表情はよく分からなかった。櫻井は、ゆるく首を横に振る。一体、なんと答えていいか判らなかった。だから「判りません」と正直に呟いた。そう、何度も呟いた。
触覚 act.06 end.
| NEXT | NOVEL MENU | webclap |
編集後記
先週に引き続き、今週もアニキご出演です。今度は、ブラックタキシード。まるでコスプレですね、この小説。この分だとアニキ、毎回衣装が違ってそうです(笑)。まるでチャーリーズ・エンジェルだわ。(ノット・レイク・エンジェル。)
[国沢]
小説等についての感想は、本編最後にあるWEB拍手ボタンからもどうぞ!
